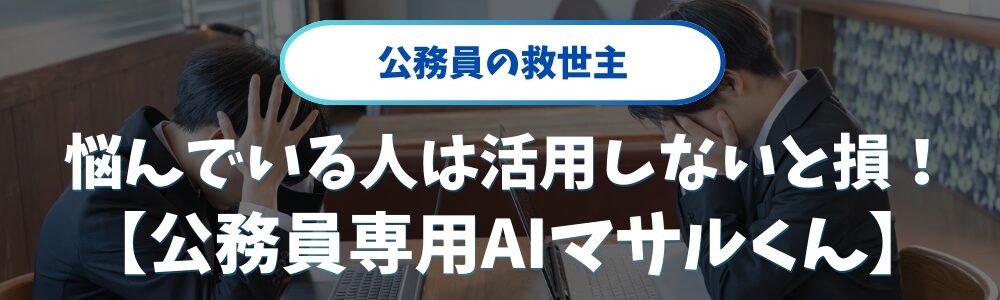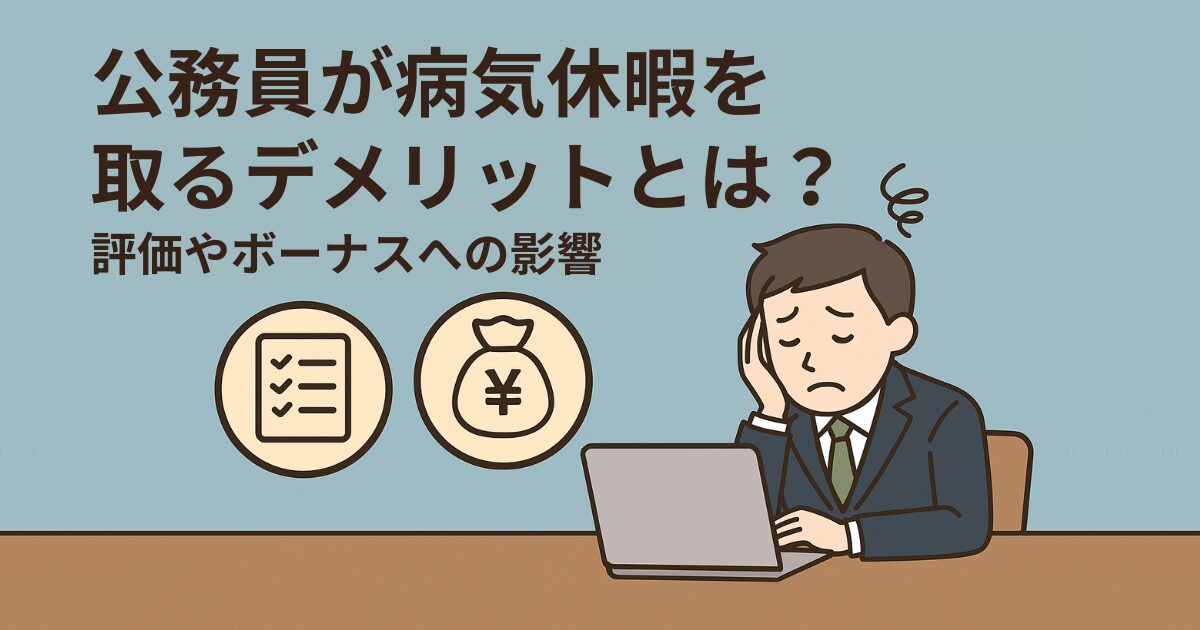公務員として働いていると、体調を崩したときに利用できる「病気休暇」という制度があります。給料が支給されるうえ、法律に守られている安心な仕組みですが、一方で「公務員が病気休暇を取るデメリット」を気にする声も少なくありません。
特に、休暇中に旅行をした場合のリスクや、診断書なしで休めるケースの注意点、人事評価や今後のキャリアへの影響など、見落としがちな問題も存在します。
この記事では、公務員の病気休暇にまつわる制度の基本から、実際に起こりうるデメリットまで詳しく解説します。信頼を失わずに制度を正しく活用するためにも、事前に知っておくべきポイントを一緒に確認していきましょう。
- 公務員の病気休暇制度の基本的な仕組み
- 病気休暇を取る際のデメリットや注意点
- 診断書なしで休む場合のルールとリスク
- 病気休暇が人事評価やキャリアに与える影響
公務員の病気休暇|デメリットを正しく理解しよう

- 公務員の病気休暇とは?制度の基本を解説
- 病気休暇の取り方と注意点
- 1週間の病気休暇|使い方と注意点
- 病気休暇中に旅行はNG?
- 診断書なしで休めるのか?
公務員の病気休暇とは?制度の基本を解説
公務員の病気休暇とは、けがや病気で働けないときに使える特別な休みです。これは体を休めて元気を取り戻すための制度で、民間企業とは違い、法律に基づいてしっかり決められています。
この休暇は「一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律」や「人事院規則」で決められており、最大90日間まで取得できます。その間は給料も全額支給されるため、安心して療養に専念できます。これが民間との大きなちがいです。
対象になるのは、以下のようなケースです。
- インフルエンザなどの感染症
- 腰のけがや骨折など外科的なもの
- がんや精神的な病気(うつ病など)
この休暇には特別な制限はなく、内科・外科・心の病まで幅広く対応できます。また、負傷や病気の重さも問いません。ただし、長く使うときには医師の診断書が必要です。
ポイントとして押さえておくべき点は以下の3つです。
- 90日以内なら給料は満額支給
- 期間が長くなると診断書が必要
- 病気の種類は問われない
つまり、公務員の病気休暇は「安心して体を休めるためのルール」です。ただし使いすぎやルール違反には注意が必要です。正しく使えば、大きな安心につながる制度といえるでしょう。
病気休暇の取り方と注意点

公務員が病気休暇を取るには、一定の手続きが必要です。急に体調をくずしたときでも、順を追って進めればスムーズに取得できます。
はじめに、体調が悪いと感じたらすぐに上司へ連絡します。このときは電話やメールで構いません。連絡をしたあと、職場の人事や総務に病気休暇を申請します。ここで必要になるのが「病気休暇申請書」です。
申請書を出すだけでなく、場合によっては医師の診断書も求められます。たとえば、以下のような場合です。
- 8日以上連続して休むとき
- 過去1ヶ月のあいだに5日以上休んでいるとき
提出する診断書は、病名や治療期間などが書かれた正式なものです。領収書や薬の記録では代用できないこともあるので注意しましょう。
病気休暇の流れは以下のようになります。
- 上司へ体調不良の報告
- 人事や総務へ病気休暇の申請
- 必要に応じて診断書の提出
- 承認後、休暇スタート
注意点としては、職場との連絡を絶やさないことが大切です。長引くときには状況を定期的に報告しましょう。また、診断書の内容にうそがあると、のちに問題になる可能性があります。
公務員の病気休暇はしっかりした制度ですが、正しい手順を踏むことが求められます。無理せず、適切に制度を利用するようにしましょう。
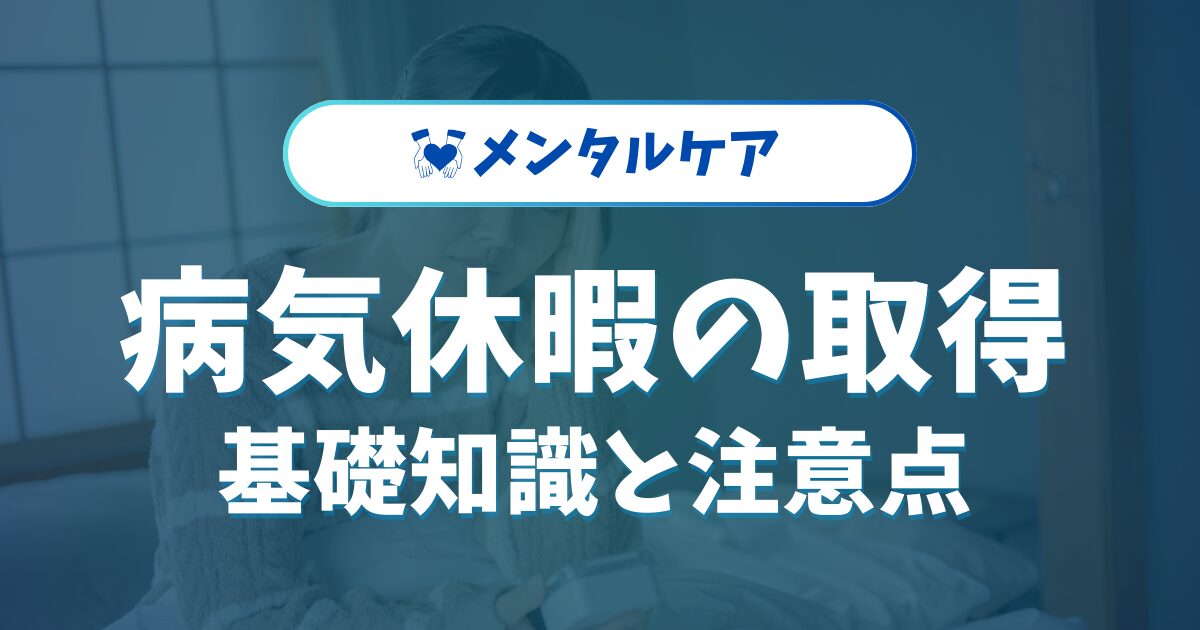
1週間の病気休暇|使い方と注意点

公務員が1週間だけ病気休暇を使うのは、短期間で体を休めたいときに有効です。インフルエンザや軽いけがなど、入院はしないけれど仕事を休む必要がある場合に役立ちます。
このような短期の休暇には、いくつかのメリットがあります。
メリット
- 無理せず療養できる
- 早めに体調を整えられる
- 病気休職に移らず復職しやすい
特に、休暇中も給与が全額支給される点は大きな安心材料です。また、1週間程度であれば職場への影響も比較的少ないとされています。
一方で注意が必要なのは、次のような点です。
注意点やデメリット
- 短期間では回復が十分でないこともある
- 病名や休む理由が不明確だと周囲の理解を得にくい
- 短い期間でも繰り返すと評価に影響する可能性がある
診断書が不要なケースもありますが、必要なときはすぐに提出できるよう準備しておきましょう。特に、過去1か月で5日以上病気休暇を取っている場合や、今後も体調を崩すしそうな場合には、早めに上司へ相談することが大切です。
1週間の病気休暇はうまく使えば心と体を整える時間になりますが、使い方をまちがえると信頼や評価に影響を与えることもあります。体調と相談しながら、必要なときに正しく活用するようにしましょう。
病気休暇中に旅行はNG?

病気休暇中に旅行をするのは、原則としてNGです。なぜなら、病気休暇は「療養のために仕事を休む」ことを前提としているからです。旅行がばれてしまうと「療養していない」と判断され、信用を失うおそれがあります。
実際に、過去には次のような事例がありました。
- 大阪の教員が病気休職中にヨーロッパ旅行をして減給処分
- 福岡の市職員がイギリス旅行をして停職6か月
これらのケースでは、「信用失墜行為」として処分されました。これは、国民の信頼を大切にするべき公務員にとって、とても重い結果です。
では、もし本当に回復のための温泉旅行などであれば問題ないのでしょうか?その場合でも、職場に相談せず無断で行くとトラブルになる可能性があります。必要があれば、医師の意見書を準備するなどして、事前に許可を取ることが望ましいです。
なお、病気休暇中の行動については法律で明確に禁止されているわけではありませんが、公務員としての立場や周囲からの信頼を考慮する必要があります。
病気休暇中にやってはいけないこと。
- 遊び目的の旅行
- 外出が多くSNSなどで行動がバレる
- 職場へ無断で出かける
病気休暇中の行動には慎重になる必要があります。周囲の目や信頼、処分のリスクまで考えて、療養に専念する姿勢を持ちましょう。何よりも、自分の回復が最優先です。
診断書なしで休めるのか?

病気休暇を取るとき、必ず診断書が必要だと思っていませんか?実は、公務員の場合でも診断書なしで休めるケースがあります。ただし、その条件やルールには注意が必要です。
診断書が不要なケース
- 休みが連続で3日以内の場合
- 年間の取得回数が少ない場合(例:10日以内など)
- 上司へ口頭や簡単な申請書で伝えた場合
このような場合、病気休暇は比較的スムーズに取れる仕組みになっています。ただし、これは「軽い体調不良」や「急な風邪」など、短期間の療養が前提です。
診断書が必要になる例
- 連続で8日以上休むとき
- 1か月間に通算5日以上の休暇を取っているとき
- 精神的な病気で長期の療養が必要なとき
診断書は、医師の診察を受けて発行される正式な書類です。お薬手帳や診療明細などで代わりに証明できる職場もありますが、あくまでも判断は職場ごとのルールに従う必要があります。
また、診断書なしで休みを取ると、次のようなリスクが生じます。
診断書なしで休むリスク
- 病気の証明ができず評価に響く可能性がある
- 繰り返し休むと「不正」と疑われる場合がある
- 信頼を失い職場での立場が悪くなることも
つまり、短期間であれば診断書なしでも休める場合はありますが、状況や取得回数によっては注意が必要です。職場のルールを事前に確認し、不安なときは上司や人事に相談するのが安全でしょう。休むときも、後のトラブルにならないようにきちんと対応しておくことが大切です。
公務員の病気休暇|デメリットとその影響

- 人事評価とキャリアへの影響
- 病気休暇のその後はどうなりますか?
- 病気休暇で給与やボーナスに影響しますか?
- 長期病気休暇はクビにつながる?制度の限界とは
- 病気休暇制度を悪用する実態と防止策
人事評価とキャリアへの影響
病気休暇を取ると、評価や出世に影響があるのか気になる人もいるでしょう。実際、公務員の場合でも休暇の長さや回数によって人事評価が左右されることがあります。
まず、数日~1か月程度の短い病気休暇であれば、大きなマイナスにはなりにくいです。特に真面目に働いてきた人であれば、職場も事情を理解してくれることが多いでしょう。ただし、休みが続いたり何度も繰り返したりすると、周りの評価が変わる可能性があります。
評価に影響が出やすいケース
- 3か月以上の長期病休を取ったとき
- 年に何度も繰り返して病気休暇を取っているとき
- 業務の遅れや成果の低下につながったとき
このような場合、業績や能力の評価に影響が出やすくなります。さらに、管理職など責任のあるポジションには選ばれにくくなることもあるでしょう。
とくに精神的な病気の場合は、「再発のおそれがある」とみなされ、配属先の決定や昇進に制限がかかることがあります。もちろん、すべてのケースで不利になるわけではありませんが、休職期間が長くなるほど注意が必要です。
対策としては、復帰後の勤務で信頼を取り戻すことが大切です。実績を積み、上司や周りと良好な関係を作ることで、評価の回復は十分に可能です。
つまり、病気休暇はキャリアに影響を与える面もありますが、復帰後の行動しだいで取り戻すことができる制度ともいえます。
病気休暇のその後はどうなりますか?

病気休暇を終えたあと、公務員はどのように職場に戻るのでしょうか。実は、復帰したあとのほうが大変だと感じる人も少なくありません。
まず、体調が安定していても、すぐに以前のように働けるわけではないこともあります。そのため、多くの職場では以下のような配慮がされます。
よくある復帰サポートの例
- 時間を短くして働く「短時間勤務」
- 負担の少ない仕事への配置転換
- 残業や夜勤などの制限
このようなサポートにより、無理なく職場に戻れる体制を整えている自治体も増えています。
一方で、復帰後に不安を感じる人も多いです。主に、次のような悩みがあるようです。
よくある復帰後の不安
- 「また体調が悪くなるかも」と心配になる
- 同僚にどう思われているかが気になる
- 以前と同じ仕事がこなせるか自信がない
さらに、昇進や評価への影響も気になりがちです。特に長く休んだ場合は、元のポジションに戻れないケースもあります。
このようなプレッシャーを軽くするには、上司とこまめに話し合いをすることが大切です。また、焦らずゆっくりと職場に慣れていくことがポイントです。
つまり、病気休暇のあとは体だけでなく心の回復も意識しながら、無理のない職場復帰を目指しましょう。周囲との良い関係があれば、安心して再スタートが切れるはずです。
病気休暇で給与やボーナスに影響しますか?

病気休暇中でも、給与やボーナスは支給されるのか心配になる人は多いです。公務員の場合、最初の90日間は「病気休暇」として扱われ、給与は全額支給されます。この期間中は出勤していない日も、給料は通常どおり振り込まれます。
しかし、90日を過ぎても回復しないと「病気休職」に切り替わります。休職になると、初めの1年間は給料の80%に減額されるのが一般的です。そして、1年を超えると無給になる自治体もあります。
ボーナス(賞与)については、少し仕組みが違います。
【ボーナスの取り扱い】
- 病気休暇中
満額支給(勤務実績とみなされるため) - 病気休職中
出勤日数に応じて減額される - 無給の期間
ボーナスも支給されない
たとえば、支給対象となる査定期間に3か月以上働いていなければ、ボーナスが大きく減るかゼロになることもあるのです。
また、勤勉手当というボーナスの一部については、病気休暇が30日を超えると減らされる場合があります。ただし、期末手当(もう一方のボーナス)は満額もらえるケースもあります。
まとめると、公務員の病気休暇では最初の3か月は金銭面の心配は少ないですが、それを超えると給与・賞与の減額があるため、長期になると経済的な負担が大きくなる点に注意が必要です。
長期病気休暇はクビにつながる?制度の限界とは
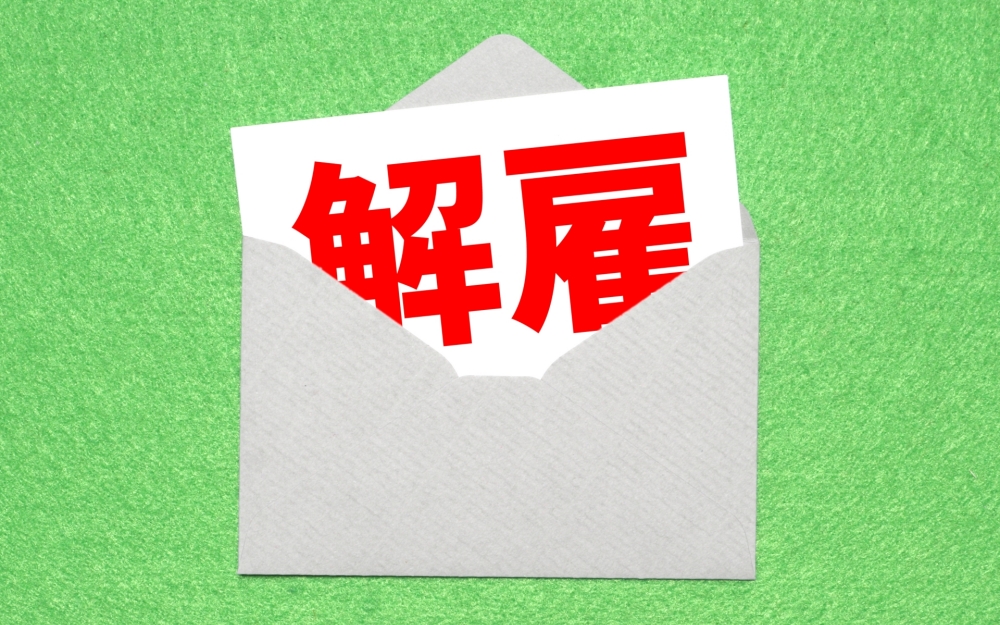
長く病気休暇を取ると、「このまま退職になるのでは?」と不安に思う人もいます。公務員には病気休暇や休職の制度がありますが、それにも限界があります。
まず、公務員の病気休暇は最大90日までとされています。それ以降も療養が必要な場合、「病気休職」に移行し、最長で2年9ヶ月まで取得できるのが一般的です。
この期間をすぎても復職ができないと、自然退職や分限免職(ぶんげんめんしょく)といって、職を失う可能性が出てきます。これは制度の仕組みによるもので、誰でも同じようにルールが適用されます。
【病気休暇と休職の期間】
- 病気休暇
最大90日(給与100%) - 病気休職
最長2年9ヶ月(給与は徐々に減額→無給へ) - 休職終了後も復帰できない場合
退職の可能性あり
さらに、「もう少しで復職できそう」と医師が判断した場合、期間の延長が認められるケースもありますが、それは例外です。はっきりした回復の見通しがなければ、延長は難しいでしょう。
退職リスクを減らすためには、会社との連絡を絶やさないことが大切です。体調の変化や医師の診断内容をこまめに伝えることで、復職のタイミングを相談しやすくなります。
このように、制度にはしっかりとした期限があるため、長期療養が必要な場合は今後の働き方や生活の計画を早めに立てることが大切です。
病気休暇制度を悪用する実態と防止策

病気休暇は、公務員が体や心の不調で働けないときに安心して休める制度です。ただ、この仕組みを使っていないのに使ったふりをする人が、一部で問題になっています。正しく使っている多くの人にとっては、とても迷惑な話です。
たとえば、ある市では、診断書を偽造して8年間にわたり1300日以上も休んだケースが発覚しました。給料として1600万円以上が支払われており、最終的にこの人は刑事告訴されました。
こうした悪用を防ぐため、以下のような対策が取られています。
【職場の防止策】
- 提出された診断書はコピーでなく「原本確認」が必要
- 必要があれば、人事課の職員が病院に同行して事実を確認
- 第三者の委員会を作り、利用状況を定期的にチェック
また、クーリング期間といって「短期間だけ出勤して再度病気休暇を取る」行為への注意も強まっています。制度を守って使っている職員が不公平にならないよう、ルールの見直しも進められています。
病気休暇は大事な制度ですが、正しく使われなければ信頼が失われます。制度を守ることは、自分だけでなく周りの人の安心にもつながるのです。
公務員の病気休暇|デメリットとその影響(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 公務員の病気休暇は最大90日間、給与全額支給である
- 法律と人事院規則に基づいた明確な制度である
- 診断書なしでも短期間なら取得可能な場合がある
- 連続8日以上や月5日以上の取得では診断書が必要になる
- 病気の種類は問われず、広い範囲に対応している
- 手続きには上司への連絡と申請書の提出が必要
- 短期間の病休は評価への影響が少ない傾向にある
- 1週間の病休でも繰り返すと人事評価に影響する可能性がある
- 病気休暇中に旅行へ行くと処分対象になるリスクがある
- SNSなどで療養にそぐわない行動が発覚すると信頼を失う
- 病休後の復職では短時間勤務や配慮された配置になることが多い
- 長期病休により昇進や責任あるポストから外されることもある
- 病気休暇が90日を超えると休職に移行し給与は減額される
- 病休・休職の合計が2年9ヶ月を超えると退職の可能性が出てくる
- 制度の悪用は実際に起きており、防止策として診断書の厳格確認や外部監査が導入されている