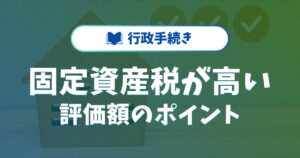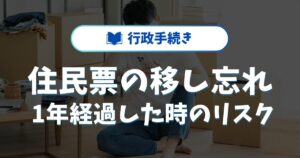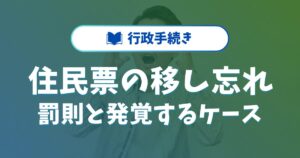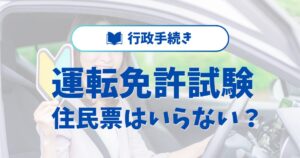選挙の時期になると、自宅の郵便受けに見知らぬ候補者からのハガキが届き、「なぜ自分の住所を知っているのだろう?」と不思議に思った経験はありませんか。候補者からハガキが届く背景には、個人情報の扱いや公職選挙法が関わっています。
この記事では、選挙ハガキが勝手に送られてくるように感じる理由から、ハガキに記載されている紹介者の役割、さらにはそのハガキが法律違反ではないのかという疑問まで、網羅的に解説します。また、不要な選挙ハガキの受け取り拒否に関する具体的な手続きについても触れていきますので、ぜひ最後までご覧ください。
- ハガキが届く法的な仕組みと個人情報の入手経路
- 選挙ハガキに関する公職選挙法の具体的なルール
- 合法なケースと法律違反になる事例の見分け方
- 不要なハガキの受け取りを拒否する具体的な方法
選挙候補者からハガキがなぜ届く?その仕組みと個人情報

- 個人情報はどこから?その入手経路とは
- 選挙人名簿における情報の出所
- 選挙ハガキに書かれた「紹介者」とは一体誰のこと?
- 個人情報保護法が適用されない選挙運動
- 知らない候補者から選挙ハガキが勝手に!これって合法?
- 選挙ハガキはいつ届く?候補者が送る本当の狙い
個人情報はどこから?その入手経路とは

候補者からハガキが届く際、多くの方が疑問に思う個人情報の入手経路は、主に公的な「選挙人名簿」によるものです。
その理由は、候補者や政党が選挙運動を目的として、市区町村の選挙管理委員会でこの名簿を閲覧することが法律で認められているからです。
例えば、候補者陣営の担当者が選挙管理委員会に出向き、名簿に記載された氏名や住所を手で書き写したり、パソコンに入力したりして、ハガキの送付先リストを作成します。
このほか、後援会の名簿や過去の政治活動で得た情報を活用するケースもありますが、現在の個人情報保護の観点から、その利用は慎重に行われています。
選挙人名簿における情報の出所
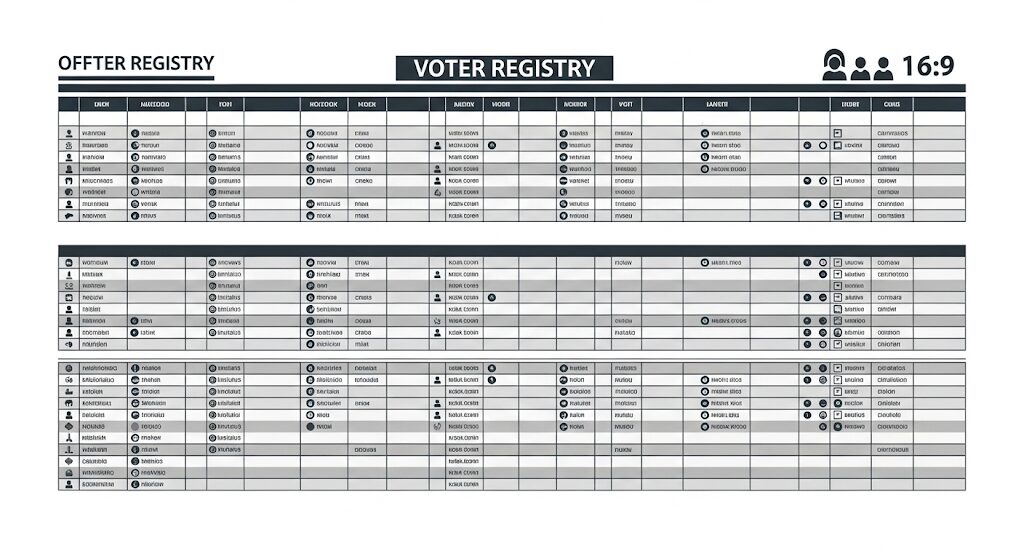
選挙ハガキの宛名に使われる個人情報の大部分は、「選挙人名簿」に由来します。
この名簿は、日本国民で満18歳以上の有権者であり、その市区町村の住民基本台帳に3ヶ月以上記録されている人を登録するものです。選挙の公正を確保するための公的な名簿であり、個人の意思で登録を拒否することはできません。
候補者陣営による閲覧は認められていますが、その際には厳格なルールが存在します。具体的には、選挙運動目的での利用に限定され、名簿のコピーや写真撮影は禁止されています。情報を書き写すことしか許可されておらず、選挙運動が終了した後は、収集した個人情報を破棄する義務が課せられています。
選挙ハガキに書かれた「紹介者」とは一体誰のこと?

選挙ハガキの中には、「紹介者」や「推薦人」として、候補者以外の個人の名前が記載されていることがあります。この紹介者とは、その候補者を応援している支援者のことです。
紹介者を記載する目的は、有権者に親近感や信頼感を持ってもらうための選挙戦略の一つです。知り合いや地元の有力者が紹介者として名を連ねていると、「この人が応援するなら」と投票を考えるきっかけになる可能性があります。
紹介者になれるのは、原則として有権者であれば誰でも構いませんが、候補者本人がなることはできません。もちろん、本人の同意なく名前を勝手に使用することは認められておらず、必ず事前に承諾を得る必要があります。この紹介者欄の記載は必須ではないため、空欄のままの選挙ハガキも多く存在します。
個人情報保護法が適用されない選挙運動

「同意なく個人情報を使うのは、個人情報保護法に違反しないのか」という疑問が生じるかもしれません。これには、法律上の特例が関係しています。
現在の個人情報保護法では、報道や著述、学術研究などと並んで、政治活動における個人情報の利用は、法律の適用除外とされています。これは、選挙運動の自由や有権者の知る権利を保障するという、民主主義の根幹に関わる活動であるためです。
ただし、どのような利用も許されるわけではありません。選挙運動の目的から逸脱して個人情報を利用したり、第三者に提供したりすることは固く禁じられています。あくまでも選挙運動という限定された目的のために、例外的な取り扱いが認められているに過ぎないのです。
知らない候補者から選挙ハガキが勝手に!これって合法?

見知らぬ候補者から突然選挙ハガキが届くと、「勝手に送られてきた」と不快に感じることがあるかもしれません。しかし、この行為の多くは合法的な範囲内で行われています。
前述の通り、候補者陣営は公職選挙法に基づき選挙人名簿を閲覧でき、また個人情報保護法の適用除外規定によって、本人の同意なく選挙運動目的でハガキを送ることが可能だからです。
したがって、あなたがその選挙区の有権者である限り、面識のない候補者からハガキが届くことは、現在の法律の枠組みの中では起こり得ることになります。この仕組みが、有権者のプライバシー意識と法律の間にギャップを生んでいる一因とも考えられます。
選挙ハガキはいつ届く?候補者が送る本当の狙い

選挙ハガキが発送されるのは、選挙の公示日(または告示日)から投票日の前日までの、選挙運動が認められている期間内に限られます。そのため、多くのハガキは選挙期間の前半から中盤にかけて有権者の元へ届きます。
候補者がコストと労力をかけてハガキを送るのには、いくつかの戦略的な狙いがあります。第一に、有権者の自宅に直接届くため、候補者の名前や顔を覚えてもらいやすいという点です。特に、インターネットをあまり利用しない層にもアプローチできる有効な手段となります。
また、政策や理念を直接伝えることで、候補者の「本気度」や人柄をアピールする狙いもあります。限られた枚数をどの地域の有権者に送るかというターゲティングも、選挙戦略の重要な一部です。
選挙候補者からハガキがなぜ届く?知るべきルールと対処法

- 選挙ハガキの全ルール解説!公選法の基礎知識
- 特に注意すべき禁止された事前運動とは
- これって公選法違反?選挙ハガキのNG事例と見分け方
- 選挙ハガキの受け取り拒否は可能?具体的な手続きを紹介
- 選挙候補者からハガキがなぜ届くのか(まとめ)
選挙ハガキの全ルール解説!公選法の基礎知識

選挙ハガキは「選挙運動用通常葉書」というのが正式名称で、その運用には公職選挙法によって細かなルールが定められています。
まず、候補者が送付できる枚数には上限があり、選挙の種類によって異なります。これを超えて送付することはできません。
選挙の種類別ハガキ送付上限枚数
| 選挙の種類 | 送付上限枚数 |
| 衆議院小選挙区 | 35,000枚 |
| 参議院選挙区 | 35,000枚から(選挙区の規模により増加) |
| 都道府県知事 | 35,000枚から(選挙区の規模により増加) |
| 市長(政令指定都市以外) | 8,000枚 |
| 市議会議員(政令指定都市以外) | 2,000枚 |
| 町村長 | 2,500枚 |
| 町村議会議員 | 800枚 |
差出方法にも決まりがあり、郵便局の窓口での手続きが必須です。ポストに投函したり、直接手渡ししたりすることは禁止されています。さらに、ハガキのデザインにも制約があり、表面に郵便局が選挙用であることを示すためのスペースを確保する必要があります。
特に注意すべき禁止された事前運動とは

選挙運動には厳しい期間の定めがあり、それに違反する行為は「事前運動」として禁止されています。
事前運動とは、立候補の届出が受理される前に、特定の候補者への投票を依頼したり、当選を目的とした活動を行ったりすることです。公職選挙法では、選挙運動期間を立候補の届出日から投票日の前日までと定めており、この期間外の選挙運動はできません。
例えば、選挙の公示日より前に、投票を依頼する内容のハガキを発送する行為は明確な事前運動と見なされます。なぜなら、全候補者が同じ条件で選挙運動をスタートするという、選挙の公正さを損なうからです。
ただし、立候補に向けた準備行為(例:宛名書きの準備、後援会内部での依頼など)は認められており、その線引きが重要になります。
これって公選法違反?選挙ハガキのNG事例と見分け方

手元に届いた選挙ハガキが、ルールを守っているか不安に思うこともあるでしょう。有権者が確認できる、公職選挙法違反が疑われる事例がいくつかあります。
一つ目は、ハガキの差出方法です。選挙ハガキは通常、「料金別納郵便」などの表示が表面に印刷されています。もし切手が貼られていたり、そうした表示がなかったりする場合は、正規の手続きを踏まずにポスト投函された可能性があり、違反が疑われます。
二つ目は、記載内容です。本人の同意なく推薦人として名前が使われていたり、事実に反する経歴が書かれていたりした場合は、虚偽表示にあたる可能性があります。このような違反が疑われるハガキを受け取った場合は、現物を保管の上、お住まいの地域の選挙管理委員会や警察に相談することが大切です。
選挙ハガキの受け取り拒否は可能?具体的な手続きを紹介
不要な選挙ハガキを受け取りたくない場合、手続きを踏むことで受け取りを拒否できます。これは、郵便法で定められた受取人の権利です。
具体的な手続きは非常に簡単です。まず、届いたハガキを開封せずに、表面の空いているスペースに「受取拒絶」または「受取拒否」と朱書き(赤字)で記載します。次に、その下に受け取りを拒否する本人の署名、または押印をします。
これを郵便ポストに投函するか、郵便局の窓口に持参、または配達員に直接渡せば、手続きは完了です。差出人にハガキが返送されることになります。
注意点
この方法は、あくまでも未開封の郵便物に限られます。一度開封してしまったものは受け取りを拒否できません。また、選挙管理委員会から送られてくる公的な「投票所入場整理券」は、この手続きの対象外となるのが一般的です。
選挙候補者からハガキがなぜ届くのか(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 選挙ハガキが届くのは公職選挙法で認められた合法的な選挙運動
- 個人情報の主な出所は市区町村が管理する「選挙人名簿」
- 候補者は選挙運動目的に限り選挙人名簿の閲覧が許可されている
- 選挙人名簿の閲覧時、コピーや撮影は禁止で手書きでの転記のみ
- 選挙運動での個人情報利用は個人情報保護法の適用除外という特例がある
- ただし選挙目的以外での個人情報の利用は固く禁止されている
- ハガキに記載の「紹介者」は候補者を応援する支援者のこと
- 紹介者の記載には本人の同意が必須であり無断掲載は違法
- ハガキを発送できるのは立候補届出日から投票日前日までの期間
- 公示日より前の発送は「事前運動」として禁止されている
- 送付できる枚数は選挙の種類ごとに上限が定められている
- ポスト投函や手渡しは禁止で郵便局の窓口での差出が必須
- 料金別納表示がないなど正規の手続きでない場合は違反の可能性がある
- 不要な選挙ハガキは「受取拒絶」と書いて返送することが可能
- 受け取り拒否は未開封の郵便物に限られ開封後はできない