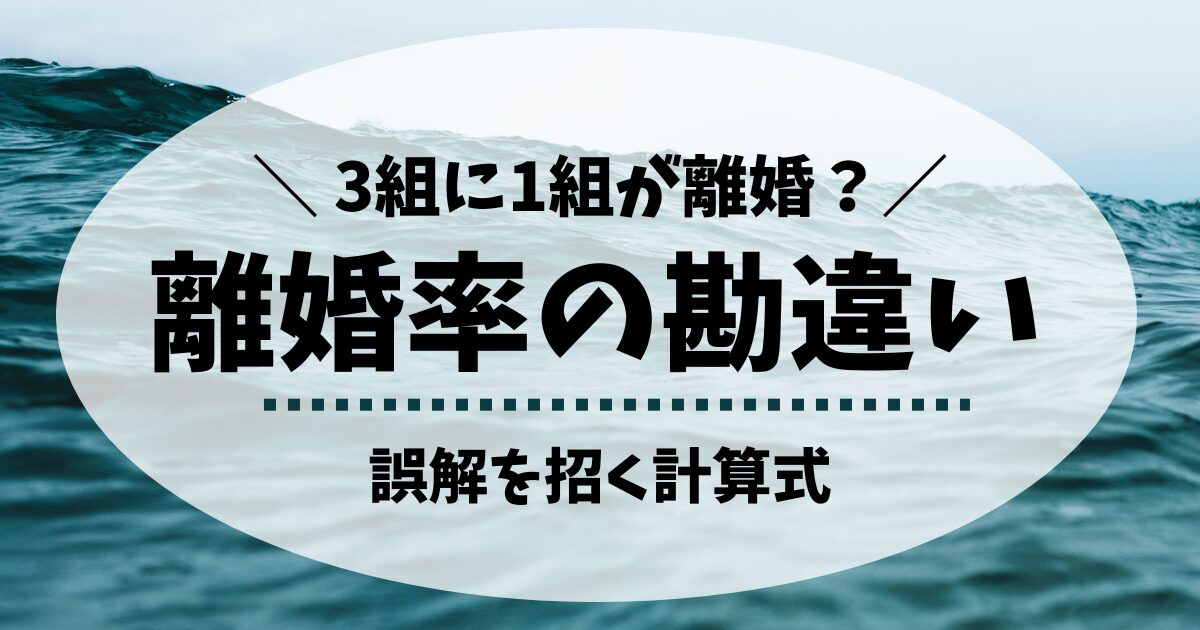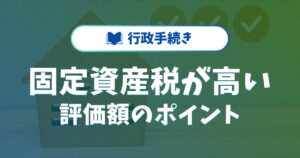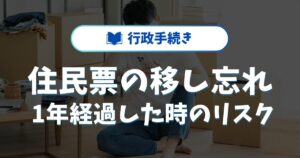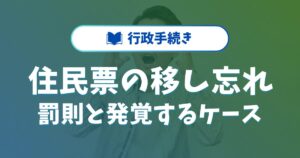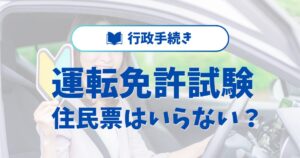離婚について調べていると、離婚率の高さに驚くことがあるかもしれません。特に「離婚率がおかしい」と感じた方は、その数字の裏にある本当の意味が気になるのではないでしょうか。実は、離婚率の計算方法や使われている指標によって、見え方が大きく変わってきます。
例えば、5年以内の離婚が多いと聞くと、結婚生活がうまくいかない夫婦が多いように思えるかもしれません。しかし、それが本当に全体の傾向なのかは、データの読み方によって違ってきます。
この記事では、「離婚は何年目が多いのか」「年代別に見るとどの年齢層で離婚が多いのか」といった疑問にも触れながら、普通離婚率や特殊離婚率のような指標の意味をわかりやすく解説していきます。数字だけにとらわれず、背景にある事情まで読み取ることで、本当の離婚の姿が見えてくるはずです。
- 離婚率の種類とそれぞれの特徴がわかる
- 「3組に1組が離婚」という表現の誤解が理解できる
- 年代別や結婚年数ごとの離婚傾向が把握できる
- 数字だけでは見えない離婚の背景や影響がわかる
離婚率がおかしいと感じる理由

普通離婚率とは?
普通離婚率とは、1年間にどれだけの人が離婚したかを「人口1,000人あたり」で示す指標です。たとえば、日本の普通離婚率が「約1.5」となっている場合は、1,000人中およそ1.5人が1年間に離婚していることを意味します。
この数字は、国ごとの離婚の多さを比較するためによく使われます。例えば、アメリカは約2.9、韓国は約2.0、日本は約1.5というように、比較しやすい指標となります。また、毎年の変化を見ることで、離婚が増えているのか減っているのかもわかります。
ただし、この指標にはいくつかの限界があります。たとえば、人口全体で見るために、子どもや高齢者など、結婚していない人も分母に入っています。そのため、結婚している人だけを対象にしたデータとは違った印象になる場合があります。
また、地域ごとの年齢構成にも影響されやすく、若い人が多い都市では高く出やすく、年配の人が多い地域では低く出る傾向があります。つまり、数字だけを見て「この地域は離婚が多い」と決めつけるのは早計です。
普通離婚率は便利な一方で、正確な離婚の実情をつかむには注意が必要です。使い方を間違えると、実際より離婚が多い・少ないという印象を与えることがあります。
特殊離婚率とは?「3組に1組が離婚」の誤解
特殊離婚率とは、1年間の離婚件数をその年の婚姻件数で割った割合を指します。この数字を基に、「3組に1組が離婚している」といった言い方が広まりました。
一見すると、とても高い離婚率のように感じるかもしれません。しかし、ここには大きな誤解があります。なぜなら、この指標は「その年に結婚したカップルがその年に離婚した」という意味ではないからです。
例えば、2023年に結婚した人たちの離婚は、実際には数年後に起こるかもしれません。一方、その年に離婚した人たちは、10年前や20年前に結婚している場合もあります。つまり、比較する対象がまったく別のグループなのです。
この指標が使われる理由は、簡単に計算できて、注目を集めやすいからです。実際、「3組に1組」という表現はインパクトがあるため、ニュースやSNSでもよく見かけます。
しかし、実態を正しく知るには、婚姻期間別の離婚データや、年齢別の傾向などもあわせて確認しなければなりません。特殊離婚率だけを見ると、誤った印象を与えかねません。
つまり、「3組に1組が離婚」という表現は、話をわかりやすくするための言い回しに過ぎません。本当に離婚の実態を知りたいなら、複数のデータを組み合わせて、正しく理解する姿勢が必要です。
離婚率の計算方法による印象の違い
離婚率は一つの計算式で出せるものではありません。計算の仕方によって、見え方が大きく変わってきます。これを知っておかないと、数字だけを見て「日本は離婚が多すぎる」と誤解してしまう可能性もあります。
主に使われている計算方法は次の3つです。
| 指標名 | 説明 |
|---|---|
| 普通離婚率 | 人口1,000人あたりの離婚件数(国際比較向け) |
| 特殊離婚率 | 離婚件数 ÷ 婚姻件数(1年での比) |
| 有配偶離婚率 | 既婚者の中で離婚した人の割合(実態に近い) |
例えば、日本の普通離婚率は約1.5とされています。これは、1,000人中1.5人が1年間で離婚しているという意味です。一方、特殊離婚率は35~39%ほどあり、これを見ると「3組に1組が離婚」といった印象になります。
また、有配偶離婚率は実際に結婚している人を基準にしているため、より現実に近い数字と言えるでしょう。例えば、若い夫婦や高齢のカップルなど、年齢層によって離婚の傾向が異なることもここから見えてきます。
離婚率の見え方は計算の仕方で大きく変わるため、正確に理解するには「何を基準にしているか」を確認する必要があります。数値の裏にある意味まで読み取る力が求められるのです。
離婚率がおかしいと感じる理由とデータを検証

年代別にみる離婚率の特徴と傾向
離婚は年齢によって起きやすいタイミングが変わります。どの年代で離婚が多いのかを知ることで、家庭の問題が見えやすくなります。
特に離婚が多いのは30〜34歳の女性で、人口1,000人あたり4.8人が離婚しています。次に25〜29歳、35〜39歳と続きます。男性では35〜39歳が一番高いです。この世代は結婚後5年以内のケースが多く、新婚生活へのストレスやすれ違いが大きな原因です。
以下のように年代ごとに離婚理由も変わってきます。
- 20代前半
生活のずれや経済の不安、親との関係 - 30代
育児や仕事の両立、性格の合わなさ - 40代
子どもの教育方針、家族との関わり - 50代以降
退職後のすれ違い、介護問題、人生の見直し
また、19歳以下の女性や20〜24歳の男性では、有配偶者あたりの離婚率が特に高くなっています。これは若くして結婚した場合、心の準備が整っていないことが原因とされます。
年齢によって離婚の理由や背景は大きく変わります。年齢ごとの特徴を知っておくと、将来のトラブルを予防しやすくなるでしょう。
離婚が多いのは何年目?婚姻期間別に解説
結婚してから何年目に離婚が多いかを見ると、2つの山があります。それは5年未満と20年以上のタイミングです。この両方で離婚がとても多くなっています。
まず、結婚5年未満の離婚が全体の約3分の1を占めています。中でも1年未満の離婚も珍しくなく、初期のすれ違いや理想とのギャップが原因になりやすいです。
反対に、結婚20年以上たった熟年夫婦の離婚も年々増えています。理由として、以下のような要因があります。
- 子どもの独立をきっかけに関係が変わる
- 退職後に生活リズムが合わなくなる
- 介護や老後の考え方にズレがある
婚姻年数ごとの離婚割合(2020年調査)は次の通りです。
| 婚姻年数 | 割合(%) |
|---|---|
| 5年未満 | 32.5 |
| 5〜9年 | 17.0 |
| 10〜14年 | 11.5 |
| 15〜19年 | 9.5 |
| 20年以上 | 21.5 |
このデータからもわかるように、結婚の初めと長く続いた後の両方に離婚のピークがあります。年数によって原因が異なるため、どの時期にも注意と話し合いが大切だといえるでしょう。
5年以内に離婚率が高くなる背景とは?
結婚してから5年以内に離婚する夫婦はとても多く、全体の約3割を占めています。この時期に別れる理由にはいくつかのパターンがあります。
まず、交際期間が短かった夫婦では、相手の性格や考え方をよく知らないまま結婚することが多くなります。特に婚活アプリを通じた結婚は急ぎやすく、2023年には結婚全体の15%以上を占めるようになりました。
5年以内に離婚しやすい主な理由は次のとおりです。
- 性格が合わない
- お金の使い方に違いがある
- 家事や育児の分担で不満がたまる
- SNSやスマホが原因のすれ違い
- 結婚に対する考え方のズレ
特に女性は、生活費をきちんと渡されないことや、精神的・身体的なつらさをきっかけに離婚を決めることが多くなっています。一方、男性は異性問題や親との関係に悩むケースが目立ちます。
結婚初期は理想と現実の差を感じやすい時期です。もし違和感を感じたら、早めに話し合いやカウンセリングを活用するのが大切です。
このような初期離婚を防ぐためには、結婚前に十分な時間をかけて将来の話をしておくことが重要でしょう。
子供あり夫婦の離婚率と影響とは?
子どもがいる夫婦の離婚は年々増えており、離婚全体の約6割を占めるまでになっています。子どもがいる家庭での離婚は、夫婦だけの問題にとどまらず、子どもの生活や気持ちにも強く関わってきます。
特に年齢の小さい子ほど、親の変化に不安を感じやすい傾向があります。0〜3歳の乳幼児では情緒が不安定になり、夜泣きや食欲の変化が見られることもあります。学童期になると、学校での集中力や友だちとの関係に影響が出る場合もあるでしょう。
離婚後に子どもとどちらの親が暮らすかという「親権」の問題も重要です。日本では現在、片方の親だけが親権を持つ「単独親権」が基本となっています。親権が取れなかった方の親も、子どもと会う「面会交流」の権利がありますが、実際にうまく行っていないケースも少なくありません。
子どもの心の安定を守るためには、次のような支えが必要です。
- 両親の話し合いによる安定した生活環境
- 公的な支援(児童扶養手当、カウンセリングなど)
- 面会交流のルール作りと実行
離婚は大人の選択ですが、子どもの未来にもつながる決断です。親の関係が変わっても、子どもに安心できる毎日を届ける工夫が求められます。
世界の離婚率ランキングと国民性の関係
世界の離婚率は国によって大きく違います。これは、文化・法律・社会の仕組みがそれぞれの国で異なるためです。単に「離婚が多い」「少ない」だけで比べると、本当の背景が見えにくくなってしまいます。
たとえば、2020年のデータでは、離婚率が高い国に次のような国があります。
| 国名 | 離婚率(人口1000人あたり) |
|---|---|
| ロシア | 4.6件 |
| アメリカ | 2.3件 |
| スウェーデン | 2.28件 |
| 韓国 | 2.0件 |
| 日本 | 1.5件 |
| イタリア | 1.1件 |
この違いには次のような要素が関係しています。
【文化の違い】
- 北欧やアメリカでは個人の自由を大切にする考え方が強く、離婚に対する抵抗も少なめです。
- 一方、カトリックの影響が強いイタリアなどでは「結婚は一生続けるべき」といった考えが根強く残っています。
【制度の違い】
- 日本では、協議だけで離婚できる制度があり、比較的手続きが簡単です。
- しかし、フィリピンのように法律で離婚を認めていない国もあります。
【経済の違い】
- 女性の自立が進んでいる国では、生活のために無理に結婚を続ける必要がなく、離婚率が高くなる傾向があります。
国ごとの考え方や仕組みが離婚のしやすさに大きく影響しています。数字だけで判断するのではなく、背景を理解することが重要です。
離婚率がおかしいと感じる理由(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 普通離婚率は人口1,000人あたりの離婚件数を示す指標
- 日本の普通離婚率は約1.5で国際的には低め
- 普通離婚率は子どもや未婚者も分母に含まれるため実態とずれる
- 地域の年齢構成により普通離婚率は高くも低くも見える
- 特殊離婚率は年間の離婚件数を婚姻件数で割った割合
- 「3組に1組が離婚」の表現は特殊離婚率に基づいた誤解である
- 特殊離婚率は比較する対象が違うため正確な実態を表していない
- 特殊離婚率は計算しやすくメディアで使われやすい指標
- 離婚率の見え方は計算方法によって大きく変わる
- 有配偶離婚率は結婚している人だけを対象とした実態に近い指標
- 年代別に見ると30代の離婚率が最も高くなる傾向
- 年齢が若いほど勢いや準備不足で離婚しやすい
- 結婚5年未満の初期離婚が全体の約3割を占めている
- 結婚20年以上の熟年離婚も年々増加している
- 世界の離婚率は文化や法律、経済状況によって大きく異なる