会計年度任用職員として働くことを検討する際、多くの方が気になるのが年収ではないでしょうか。
特に、毎月の給料から分かるリアルな手取り額や、給料が安いという話は本当なのか、また将来的に給料が上がる見込みはあるのか、といった点は生活に直結する重要な関心事です。加えて、採用されてからのボーナス、とりわけ1年目にいくらもらえるのかも気になるところだと考えられます。
この記事では、会計年度任用職員の年収に関するこれらの疑問を一つひとつ解消できるよう、制度の仕組みから気になる実態までを多角的に解説していきます。
- 会計年度任用職員の年収や手取り額のリアルな相場
- 給料が安いと言われる理由と昇給の可能性
- ボーナスや各種手当に関する具体的な仕組み
- 長期的なキャリアパスと年金などの社会保障
会計年度任用職員の年収|その実態と仕組み

- 会計年度任用職員の年収はいくら?
- 会計年度任用職員の給料から見るリアルな手取り額を公開
- 「給料が安い」は本当?正規職員との待遇の違いで比較
- 会計年度任用職員のボーナス|1年目の支給月と計算方法
- フルタイムとパートタイムで年収はどれくらい違うのか
会計年度任用職員の年収はいくら?

会計年度任用職員の年収は、勤務する自治体や働き方によって大きく変動します。全国的な平均を見ると「年収200万円未満」が多数派を占めるのが実情です。
なぜなら、給与水準は各自治体の財政状況や地域手当の有無に左右されるためです。例えば、東京都のような都市部では地域手当が上乗せされるため比較的高くなる傾向にありますが、地方の町村では最低賃金に近い水準で設定されていることも少なくありません。
具体的な年収例として、都市部で週35時間勤務するフルタイム職員の場合、年収230万~250万円前後がひとつの目安となります。一方で、地方で週20時間勤務するパートタイム職員の場合は、年収100万~150万円程度になるなど、大きな差が生じます。
| 勤務形態の例 | 年収の目安 |
| 都市部・週35時間勤務 | 230万~250万円 |
| 地方・週20時間勤務 | 100万~150万円 |
| 全国的な傾向 | 200万円未満が多数派 |
会計年度任用職員の年収は一概には言えず、働く場所や勤務時間が重要な決定要因になると考えられます。
会計年度任用職員の給料から見るリアルな手取り額を公開

会計年度任用職員として働く際、実際に受け取れる手取り額は、求人票に記載されている額面給与のおおよそ75~85%が目安となります。
これは、額面給与から社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料など)や税金(所得税・住民税)が控除されるためです。特にフルタイムで働く場合は、正規職員とほぼ同様の項目が差し引かれるため、額面と手取りの差を大きく感じることがあります。
例えば、月給22万円のフルタイム職員(独身)のケースでシミュレーションしてみましょう。
| 項目 | 金額(円) |
| 給料月額(額面) | 220,000 |
| 社会保険料(概算) | ▲ 32,000 |
| 所得税(概算) | ▲ 4,500 |
| 住民税(概算) | ▲ 10,000 |
| 手取り額(概算) | 173,500 |
この表のように、22万円の月給であっても、実際に銀行口座に振り込まれる金額は17万円台になることが分かります。パートタイムの場合も、社会保険の加入状況によって控除額は変わりますが、手取り額は額面より少なくなる点を理解しておくことが大切です。
「給料が安い」は本当?正規職員との待遇の違いで比較

会計年度任用職員の給料が安いと言われる背景には、正規職員との間に存在する構造的な待遇差があります。これは単純な月給の差額だけでなく、給与を決める仕組みや手当の有無が根本的に異なるためです。
正規職員の給与は、経験年数に応じて昇給していく「給与テーブル」に基づいて決まり、役職手当や家族手当、住宅手当といった多様な手当が支給されます。また、手厚い賞与(ボーナス)や退職金制度も用意されています。
一方、会計年度任用職員の多くは時給制や日給制であり、勤続年数に応じた自動的な昇給は基本的にありません。賞与や退職金が支給される場合もありますが、正規職員に比べると限定的です。
厚生労働省の調査では、正規職員と非正規職員の平均月給には11万円以上の差があるというデータもあり、この差が「給料が安い」という印象につながっています。
近年、「同一労働同一賃金」の原則に基づき待遇差を是正する動きはありますが、基本給や各種手当において、依然として格差が残っているのが現状と言えるでしょう。
会計年度任用職員のボーナス|1年目の支給月と計算方法
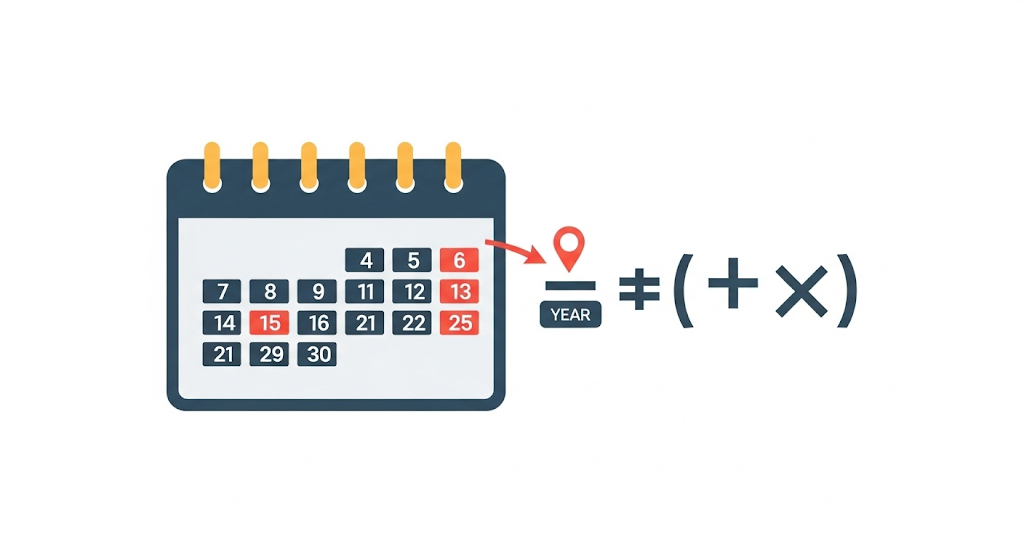
会計年度任用職員にも、多くの自治体でボーナスにあたる「期末手当」や「勤勉手当」が支給されます。支給月は、正規職員と同様に年2回、6月と12月が一般的です。
ただし、採用1年目の場合、最初の6月に支給されるボーナスは満額ではない点に注意が必要です。ボーナスの支給額は、基準日(多くは6月1日と12月1日)に在職していることに加え、その基準日以前の在職期間に応じて計算されるためです。
1年目6月期の計算例
4月1日に採用された場合、6月1日の基準日時点での在職期間は2ヶ月です。この場合、在職期間に応じて支給額を調整する「在職期間別割合」が適用されます。
具体的な計算式は以下のようになります。
例えば、基礎額が20万円、支給割合が1.25ヶ月、在職期間別割合が30%だとすると、支給額は75,000円となります。
このように、初回のボーナスは在職期間が短いために減額されることを覚えておく必要があります。なお、12月期のボーナスは、在職期間が6ヶ月を超えるため満額支給となるのが一般的です。
フルタイムとパートタイムで年収はどれくらい違うのか

会計年度任用職員の年収は、フルタイム勤務かパートタイム勤務かによって大きく異なります。この差は、単に勤務時間の長短だけでなく、社会保険の加入義務や手当の対象範囲の違いからも生じます。
フルタイム職員は、週38時間45分など正規職員と同様の時間働き、給与は月給制が基本です。社会保険への加入が義務付けられ、条件を満たせば退職手当の対象にもなります。
一方、パートタイム職員は、フルタイム未満の勤務時間で働き、報酬は時間給や日給で支払われます。勤務時間が短い場合、社会保険の加入対象外となる場合があり、その場合は国民健康保険や国民年金に自分で加入しなくてはなりません。
愛知県日進市の例を見ると、その違いがよく分かります。
| 週勤務時間 | 年収(社会保険料控除前) | 手取り額の目安 |
| 15時間 | 91万円 | 91万円 |
| 20時間 | 146万円 | 113万円 |
| 35時間 | 237万円 | 198万円 |
このように、勤務時間が長くなるほど年収は上がり、社会保険料の負担も増えます。フルタイムとパートタイムのどちらを選ぶかは、自身のライフプランや求める収入、社会保障の必要性を考慮して判断することが求められます。
会計年度任用職員の年収とキャリアの将来性

- 会計年度任用職員の給料は上がる?
- 何年も働けますか?再度の任用ルール
- 将来年金をもらえる?加入条件を解説
- 厚生年金は何号?退職後の手続きも解説
- 会計年度任用職員の年収を正しく理解しよう(まとめ)
会計年度任用職員の給料は上がる?
会計年度任用職員の給料が将来的に上がる可能性は十分にあります。ただし、正規職員のような定期昇給とは異なり、いくつかの条件や仕組みが関係してきます。
制度上、会計年度任用職員は1年ごとの任用契約であるため、自動的な昇給は保証されていません。しかし、実際には勤務成績を評価し、再度任用される際に給料が見直されるケースが多く見られます。
昇給がある主なケース
給料が上がる主なパターンは以下の通りです。
- 継続雇用による昇給
良好な勤務成績を背景に契約が更新される際、経験が考慮されて基本給が上がることがあります。 - 人事院勧告などによる給与改定
正規職員の給与が引き上げられると、それに準じて会計年度任用職員の給料表自体が改定され、給与水準が上がることがあります。 - 職務内容の変更(昇格)
より専門的で責任の重い職務に就くことで、給与表のより上位の等級に格付けされ、給料が上がります。
これらの昇給は、多くの場合、年度ごとに行われる勤務評価(人事評価)の結果に基づいて判断されます。したがって、日々の業務への取り組みや成果が、将来の給料に影響を与える重要な要素になると考えられます。
何年も働けますか?再度の任用ルール

会計年度任用職員として、同じ職場で何年も働き続けることは可能です。近年、雇用の安定化を図る動きが広まっており、長期的な勤務がしやすくなる傾向にあります。
会計年度任用職員の任期は原則1年間ですが、勤務成績などに問題がなければ、任期満了後に再度任用(更新)されるのが一般的です。かつては多くの自治体で「更新は2回まで(最長3年)」とし、それ以降は公募による選考を経なければならないというルールがありました。
しかし、この「3年ルール」は国の方針転換を受けて見直され、現在では更新回数の上限を撤廃したり、緩和したりする自治体が増えています。これにより、10年以上にわたって同じ職場で勤務を続けることも現実的になりました。
注意点
ただし、民間企業で適用される「5年ルール(無期転換ルール)」は、会計年度任用職員には適用されません。また、雇用の継続が保証されているわけではなく、あくまでも勤務評価や自治体の組織事情に基づき、年度ごとに任用が判断される点は理解しておく必要があります。
将来年金をもらえる?加入条件を解説

会計年度任用職員であっても、一定の条件を満たせば厚生年金保険と健康保険に加入でき、将来的に年金を受け取ることが可能です。
社会保険への加入は、本人の希望ではなく、法律で定められた条件に該当するかどうかで決まります。主な加入条件は以下の2つです。
| 加入基準 | 具体的な条件 |
| 4分の3基準 | 1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所の正規職員の4分の3以上であること。 |
| 短時間労働者の特例 | 上記に満たなくても、①週20時間以上勤務 ②月額賃金88,000円以上 ③雇用期間が2ヶ月を超える見込み ④学生でない、という全ての条件を満たすこと。 |
例えば、正規職員の勤務時間が週40時間の場合、週30時間以上働くパートタイム職員は「4分の3基準」により加入対象となります。また、週25時間勤務でも、月給や雇用期間の条件を満たせば「短時間労働者の特例」によって加入することになります。
これらの条件を満たす場合、自治体は職員を社会保険に加入させる義務があります。保険料は給与から天引きされますが、将来の老齢厚生年金として受け取れるため、老後の生活を支える重要な基盤となります。
厚生年金は何号?退職後の手続きも解説

会計年度任用職員が加入する厚生年金は、「第1号厚生年金被保険者」に分類されます。これは、フルタイムかパートタイムかにかかわらず、前述の加入条件を満たすすべての職員に共通です。
この資格は在職中に有効であり、任期満了や自己都合で退職した場合は資格を喪失します。そのため、退職後は自身で年金制度の切り替え手続きを行わなければなりません。
退職後の手続きフロー
退職後の状況によって、手続きは主に以下の3パターンに分かれます。
- 再就職しない場合
退職日の翌日から14日以内に、お住まいの市区町村役場の窓口で「国民年金(第1号被保険者)」への切り替え手続きが必要です。 - すぐに別の会社などで働く場合
新しい勤務先で厚生年金に加入する手続きが行われるため、個人での手続きは不要です。 - 配偶者の扶養に入る場合
年収が130万円未満などの条件を満たせば、配偶者の勤務先を通じて「国民年金第3号被保険者」になるための手続きを行います。
これらの手続きを怠ると、年金の未納期間が発生し、将来受け取れる年金額が減ってしまう可能性があります。退職時には、どの手続きが必要になるのかを事前に確認しておくことが大切です。
会計年度任用職員の年収を正しく理解しよう(まとめ)
この記事では、会計年度任用職員の年収に関する様々な側面を解説しました。最後に、重要なポイントを改めて整理します。
- 会計年度任用職員の年収は自治体や勤務形態で大きく異なる
- 都市部と地方では地域手当の有無などにより大きな差が生じる
- 手取り額は社会保険料や税金が引かれ額面の75~85%が目安
- 給料が安いと言われる背景には正規職員との構造的な待遇差がある
- 賞与や退職金、各種手当の有無が年収に大きく影響する
- ボーナスは年2回支給されるが1年目の初回は在職期間に応じ減額
- フルタイムとパートタイムでは年収だけでなく社会保障の面でも差がある
- 自動的な昇給はないが勤務評価や給与改定により給料が上がる可能性はある
- 日々の業務への取り組みが将来の昇給につながる
- 任期の更新上限を撤廃する自治体が増え長期勤務が可能になりつつある
- 民間の「5年ルール(無期転換)」は適用されない点に注意が必要
- 週20時間以上などの条件を満たせば厚生年金に加入できる
- 退職後は国民年金への切り替え手続きが必須となる
- 自身の働き方に合わせて年収とキャリアを総合的に考えることが鍵となる










