会計年度任用職員として働き始めたばかりの方にとって、最初のボーナスは大きな関心事ではないでしょうか。ボーナスが1年目から支給されるのか、具体的なボーナスの計算方法はどのようになっているのか、そして将来的にボーナスは上がる可能性があるのか、気になる点は多いはずです。
また、ボーナスだけでなく、退職金は支給されるのか、雇用継続に関わる5年ルールとは何かといった、長期的な待遇についても知っておきたいところでしょう。
この記事では、会計年度任用職員のボーナスに関する様々な疑問を、基本から分かりやすく解説していきます。
- 1年目のボーナスが支給される条件
- ボーナスの具体的な支給日と計算方法
- 働き方や経験年数による待遇の違い
- 退職金や5年ルールといった関連制度の概要
会計年度任用職員のボーナス|1年目の支給額と仕組み

- 1年目でもボーナスはもらえる?
- ボーナス支給日はいつ?夏と冬の査定期間も解説
- ボーナスの計算方法【満額もらえない理由とは】
- 【働き方別】会計年度任用職員のボーナス事情
- ボーナスの種類と支給額の目安
1年目でもボーナスはもらえる?

会計年度任用職員として働き始めた1年目であっても、所定の条件を満たせばボーナス(期末手当・勤勉手当)を受け取ることが可能です。多くの自治体で、初めての任用であっても支給対象とする制度が整っています。
主な支給条件として、まず「任用期間が6ヵ月以上」であることが挙げられます。加えて、「週の勤務時間が15時間30分以上」であることも一つの基準です。そして最も大切なのが、ボーナス支給月の基準日(通常は6月1日と12月1日)に在籍していることになります。
これらの条件を満たしていれば、4月1日に採用された新規の職員であっても、6月のボーナス支給対象に含まれます。ただし、任用期間が6ヵ月に満たない場合や、週の勤務時間が短い場合には支給対象外となるため、ご自身の雇用契約書を確認することが肝心です。
ボーナス支給日はいつ?夏と冬の査定期間も解説

会計年度任用職員のボーナスは、正規の地方公務員に準じて年2回、夏と冬に支給されるのが一般的です。具体的な支給日は自治体の条例によって定められますが、多くの場合、国家公務員の支給日に合わせて設定されます。
| ボーナス種別 | 一般的な支給日 | 主な査定期間(評価対象期間) |
| 夏のボーナス | 6月30日 | 前年の10月1日から当年3月31日 |
| 冬のボーナス | 12月10日 | 当年の4月1日から9月30日 |
※支給日が土日祝日にあたる場合は、その直前の平日に前倒しで支給されます。
ボーナスの金額は、支給日より前の約半年間の勤務実績や評価を基に算定されます。この査定期間の勤務状況が、支給される金額に直接影響を与える仕組みです。査定期間の途中で採用された場合は、在籍していた期間に応じて金額が計算されます。
ボーナスの計算方法【満額もらえない理由とは】

1年目の職員が受け取る最初のボーナスは、多くの場合、満額ではなく在籍期間に応じた「按分(あんぶん)計算」で算出されます。これは、ボーナスの金額を算定する基となる査定期間の全てに在籍しているわけではないためです。
例えば、4月1日に採用された場合、6月の夏のボーナスの査定期間である「前年10月1日~当年3月31日」には全く在籍していません。
しかし、多くの自治体では特例的な扱いで、基準日である6月1日までの在籍期間(4月・5月の2ヶ月間)を考慮して支給します。その結果、満額に対する一定の割合(例えば30%など)が支給されることになります。
| 採用時期(例) | 6月ボーナスの支給割合(目安) | 支給額イメージ |
| 4月1日採用 | 約30% | 5万円~10万円程度 |
| 5月1日採用 | 約20% | 数万円程度 |
したがって、1年目の夏のボーナスが想定より少なく感じられるのは、この期間按分によるものです。一方、4月採用の場合、12月の冬のボーナスは査定期間(4月1日~9月30日)の全てに在籍しているため、満額が支給されるケースが多くなります。
【働き方別】会計年度任用職員のボーナス事情
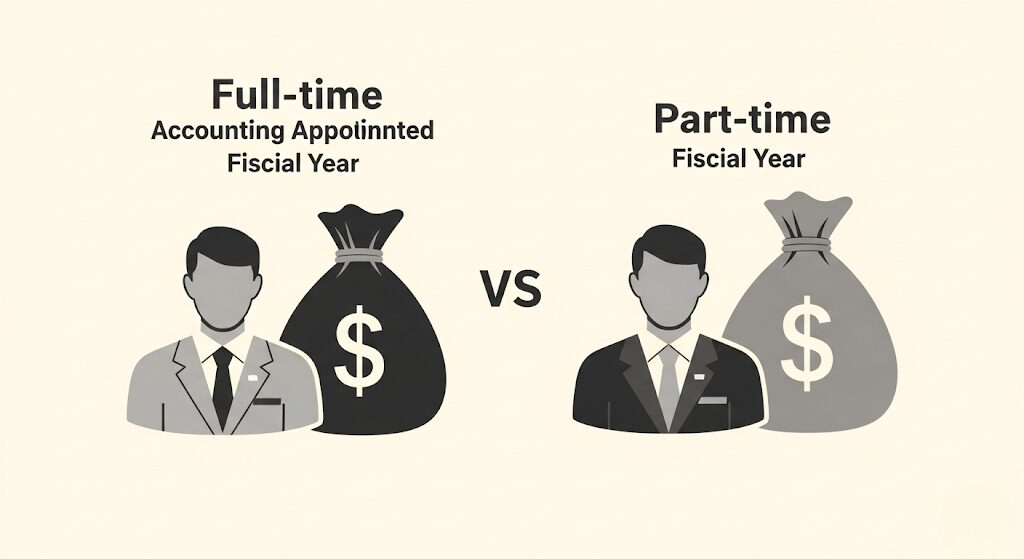
会計年度任用職員には、常勤のフルタイム職員と、短時間勤務のパートタイム職員がいます。ボーナスは、支給条件を満たしていれば、パートタイム職員にも支給されるのが大きな特徴です。
ただし、フルタイム職員とパートタイム職員では、給与体系や一部の手当に違いがあり、それがボーナス額にも影響します。
| 比較項目 | 常勤(フルタイム) | 非常勤(パートタイム) |
| 給与体系 | 月給制(給料) | 時間給制(報酬)が主 |
| ボーナス | 支給対象 | 条件を満たせば支給対象 |
| 退職金 | 条件を満たせば支給対象 | 原則として支給対象外 |
ボーナス計算の基礎となる金額が、フルタイム職員は「給料月額」であるのに対し、パートタイム職員は「報酬額」を基に算出されるため、支給額に差が出ることがあります。とはいえ、同一労働同一賃金の考え方に基づき、パートタイム職員の待遇も改善されており、勤務時間に応じた公平な支給が目指されています。
ボーナスの種類と支給額の目安
会計年度任用職員に支給されるボーナスは、主に「期末手当」と「勤勉手当」の2種類で構成されています。
期末手当
期末手当は、在籍期間に応じて一律の基準で支給される手当で、ボーナスの基本部分と言えます。週15時間30分以上、任期6ヶ月以上といった条件を満たす全ての会計年度任用職員が支給対象です。
勤勉手当
勤勉手当は、勤務成績や人事評価に応じて支給額が変わる手当です。2024年度から多くの自治体で本格的に導入され、正規職員と同様に個人の頑張りがボーナスに反映される仕組みが整いました。これにより、会計年度任用職員全体の待遇が向上しています。
年間の支給月数の合計は、人事院勧告などを反映して決定され、近年では年間で合計4.6ヶ月分前後が標準的です。1年目の場合、按分計算後の6月のボーナスは数万円から10万円程度、満額支給となる12月のボーナスは1回あたり30万円程度になるケースも見られます。
会計年度任用職員ボーナス|1年目以降の待遇と制度

- 会計年度任用職員のボーナスは経験年数で上がる?
- 知らないと損?会計年度任用職員に退職金は出る?
- 5年ルールとは
- 途中退職や非在籍時のボーナスはどうなる?
- 制度改正でボーナスは拡充されている?
- 会計年度任用職員のボーナス|1年目の重要ポイント
会計年度任用職員のボーナスは経験年数で上がる?

会計年度任用職員として働き続けることで、ボーナス額が将来的に上がる可能性は十分にあります。その主な理由は、経験年数に応じた昇給制度にあります。
多くの自治体では、正規職員と同様に「号給」という給与の格付け制度を採用しています。同じ職務で再任を重ね、経験年数を積むことでこの号給が上がり、ボーナス計算の基礎となる給料(または報酬)月額が増加します。結果として、支給されるボーナスの金額も上昇していく仕組みです。
ただし、号給の上昇幅や経験年数の換算方法は、自治体の規定によって異なります。また、人事評価の結果も勤勉手当の額に影響するため、日々の勤務成績も昇給に関わる大切な要素と考えられます。1年目は按分計算で少なめですが、2年目以降は満額支給となり、さらに勤続によって着実に増額が期待できるでしょう。
知らないと損?会計年度任用職員に退職金は出る?

ボーナスとは別に、任期満了時に退職金が支給されるかどうかも気になる点です。これについては、働き方によって扱いが大きく異なります。
結論から言うと、フルタイムの会計年度任用職員で、一定の勤続期間(多くの自治体で6ヶ月以上)などの条件を満たした場合に退職手当が支給されます。支給額は、退職時の給料月額と勤続期間に応じた支給率を基に計算されます。
一方で、パートタイムの会計年度任用職員には、原則として退職金の支給はありません。これは、フルタイム職員との勤務時間の差などを考慮した制度設計によるものです。その代わりとして、パートタイム職員にも期末手当や勤勉手当が支給されることで、年収ベースでの待遇の公平性が図られています。
5年ルールとは

雇用の安定性に関して、「5年ルール」や再任用の上限について不安を感じる方もいるかもしれません。
まず、民間企業で適用される、有期雇用が5年を超えると無期雇用に転換できる「5年ルール(無期転換ルール)」は、地方公務員である会計年度任用職員には適用されません。したがって、何年勤務しても自動的に無期雇用になることはないのです。
次に、再任用の上限回数ですが、かつては「2回まで(通算3年)」といった制限を設ける自治体が多く見られました。しかし、人材確保や専門性維持の観点から、2024年以降、国の方針でこの上限は撤廃される流れになっています。
これにより、勤務評価などの条件を満たせば、上限なく再任されることが可能となり、以前よりは長期的に働きやすい環境が整いつつあります。
途中退職や非在籍時のボーナスはどうなる?

ボーナスを受け取るためには、支給の基準日に在籍していることが絶対的な条件です。もし基準日よりも前に退職してしまった場合、その回のボーナスは一切支給されない点には注意が必要です。
例えば、夏のボーナスの基準日は6月1日です。たとえ5月31日まで勤務していたとしても、基準日に在籍していないため、6月下旬に支給される夏のボーナスを受け取る権利は失われます。これは、査定期間中にどれだけ長く勤務していたとしても覆ることはありません。
これは自己都合での退職だけでなく、任期満了日が基準日の直前である場合も同様です。ボーナスの支給を期待している場合は、ご自身の任期満了日とボーナスの基準日を正確に把握しておくことが大切になります。
制度改正でボーナスは拡充されている?

会計年度任用職員の待遇は、制度開始以降、改善が進められています。特にボーナスに関しては、近年拡充される傾向にあります。
最も大きな変化は、2024年度から多くの自治体で「勤勉手当」が本格的に導入されたことです。これにより、従来の期末手当に加えて、個人の勤務成績が反映される手当が上乗せされるようになりました。これは、正規職員との待遇格差を是正し、職員の意欲向上を図るための重要な改正です。
この制度改正によって、パートタイム職員を含む全ての会計年度任用職員が、より公平な評価と待遇を受けられる環境が整備されつつあります。今後も、社会情勢や国の動向に応じて、さらなる待遇改善が進むことが期待されます。
会計年度任用職員のボーナス|1年目の重要ポイント
記事のポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員1年目でも条件を満たせばボーナスは支給される
- 主な条件は任用期間6ヶ月以上と週15時間30分以上の勤務
- 支給基準日である6月1日と12月1日に在籍していることが必須
- 1年目の夏ボーナスは在籍期間に応じた按分計算となる
- 按分により満額ではなく支給額が30%程度になることが多い
- ボーナスは期末手当と勤勉手当の2種類で構成される
- 2024年度から勤勉手当が拡充され待遇が改善傾向にある
- パートタイム職員もフルタイムと同様の条件で支給対象になる
- ボーナスは経験年数を重ね号給が上がると増額が見込める
- 退職金はフルタイムで6ヶ月以上勤務した場合に支給される
- パートタイム職員に退職金の支給は原則ない
- 民間の「5年ルール」は適用されず無期雇用への転換はない
- 再任用の上限回数は撤廃され長期勤務が可能になっている
- 支給基準日より前に退職するとその回のボーナスは支給されない
- 詳細は必ず所属する自治体の条例や規定を確認することが大切










