選挙のたびに、「比例代表制はおかしいのではないか」という声を耳にします。特に、小選挙区で敗れた候補者が当選する比例復活はいらないと感じる方は少なくないでしょう。
この制度が抱えるデメリットを考えると、いっそ廃止すべきだという意見も上がります。しかしその一方で、この複雑な制度はそもそも誰が作ったのか、なぜ存在するのか、その理由を正確に知る機会はあまりありません。
この記事では、比例代表制に対するさまざまな疑問を解消するため、制度の基本的な仕組みから国内外の比較、そして廃止した場合の影響まで、多角的な視点から分かりやすく解説します。
- 「比例代表いらない」と感じる理由や制度の仕組み
- メリット・デメリットの両面から見た制度の評価
- 世界の選挙制度との比較から見える日本の課題
- 制度廃止の影響と有権者として賢く投票する方法
「比例代表はいらない」論が生まれる制度の仕組みとは
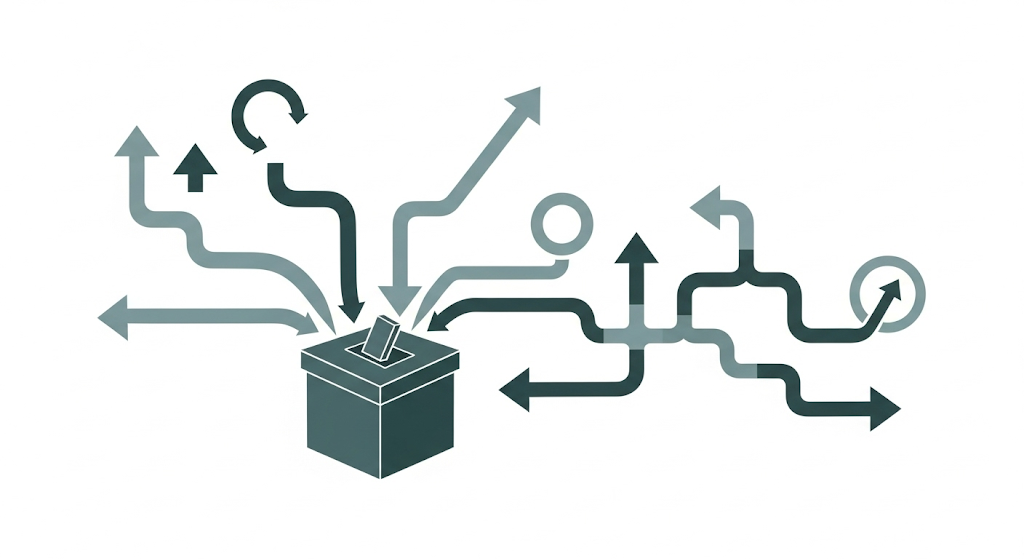
- 比例復活はおかしい!ずるい!と言われる訳
- 今さら聞けない比例代表制をわかりやすく解説
- 比例代表制は誰が作った?なぜ小選挙区と併用?
- 死票を減らす?比例代表制が持つ本来のメリット
比例復活はおかしい!ずるい!と言われる訳
比例復活という仕組みが「おかしい」や「ずるい」と批判される主な理由は、小選挙区で有権者から明確にノーを突きつけられたはずの候補者が、結果的に当選してしまうためです。これは、国民の審判と選挙結果の間に大きなズレを生じさせ、多くの人が感じる不公平感の源泉となっています。
この背景には、衆議院選挙で認められている「重複立候補」という制度があります。政党は、小選挙区で敗れる可能性のある候補者をあらかじめ比例代表の名簿にも載せておくことで、たとえ小選挙区で負けても、政党の獲得した比例議席によって救済される可能性を残せます。
具体的には、「惜敗率(せきはいりつ)」という指標が用いられます。これは、小選挙区で当選した候補者の得票数に対する、落選した候補者の得票数の割合です。
この惜敗率が高い順に、同じ名簿内の候補者が比例復活の対象となります。理論上は僅差で負けた候補者を優先する合理的な仕組みに見えますが、有権者から見れば「選挙で選ばれなかった」という事実に変わりはなく、「いらない」という厳しい声につながっているのです。
今さら聞けない比例代表制をわかりやすく解説
比例代表制とは、選挙全体で各政党が獲得した票の数(得票率)に応じて、議席を配分する選挙制度です。一つの選挙区から一人しか当選しない小選挙区制とは異なり、各政党の支持の大きさを、より正確に議席数へ反映させることを目的としています。
小選挙区制との比較
二つの制度には、以下のような違いがあります。
| 制度 | 投票対象 | 議席配分の仕組み | 死票の多さ | 有利な政党 |
| 小選挙区制 | 候補者個人 | 最も多く票を得た一人が当選 | 多い | 大政党 |
| 比例代表制 | 政党または候補者 | 得票率に比例して議席を配分 | 少ない | 小政党も議席獲得の機会あり |
日本の比例代表制の種類
日本の国政選挙では、衆議院と参議院で異なる方式の名簿式比例代表制が採用されています。
- 拘束名簿式(衆議院)
政党があらかじめ候補者の当選順位を決めた名簿を提出します。有権者は「政党名」に投票し、各政党が獲得した議席数に応じて、名簿の上位から順に当選者が決まります。 - 非拘束名簿式(参議院)
政党は当選順位を決めずに名簿を提出します。有権者は「政党名」または「候補者名」で投票でき、その政党の獲得議席の中で、個人の得票数が多い候補者から順に当選します。
比例代表制は民意の多様性を反映しやすい一方で、その仕組みは一つではなく、選挙の種類によって違いがある点を理解することが大切です。
比例代表制は誰が作った?なぜ小選挙区と併用?

現在日本で採用されている「小選挙区比例代表並立制」は、特定の誰か一人が作ったものではなく、1994年の政治改革の中で、政治的な議論と妥協を経て生まれた制度です。この改革の背景には、当時の中選挙区制が抱えていた深刻な問題がありました。
改革前の中選挙区制では、一つの選挙区から複数の議員が選出されていたため、同じ政党の候補者同士が争う場面が多く見られました。その結果、政策本位の選挙ではなくなり、派閥争いの激化や金権政治の温床になっていると厳しく批判されていたのです。
そこで、政治とカネの問題を断ち切り、政権交代可能な二大政党制を目指すため、小選挙区制の導入が議論されました。しかし、小選挙区制だけでは死票が多くなり、少数政党の意見が議会に届きにくくなるという懸念がありました。
このため、政治の安定を目指す「小選挙区制」と、民意の多様性を反映する「比例代表制」の両方の長所を組み合わせるという政治的妥協が図られました。
つまり、現在の制度は、小選挙区制を推す大政党と、比例代表制の維持を求める少数政党との間でのバランスを取った結果であり、日本の政治史における大きな転換点として導入されたものなのです。
死票を減らす?比例代表制が持つ本来のメリット
比例代表制が導入された本来の目的の一つであり、最大のメリットとも言えるのが、「死票」を少なくできる点です。死票とは、選挙で投じられたものの、候補者の当選には結びつかなかった票のことを指します。
例えば、小選挙区制では、選挙区で1位になった候補者以外に投じられた票は、すべて死票となります。有権者が5人いて、A候補に3票、B候補に2票入った場合、当選するのはA候補のみで、B候補に投じられた2票は議席に全く反映されません。実際、2014年の衆議院選挙では、小選挙区の総得票のうち約48%が死票になったというデータもあります。
これに対し、比例代表制は各政党の総得票数に応じて議席を配分するため、たとえ小さな政党であっても、全国から集めた票が一定数に達すれば議席を獲得できます。これにより、有権者の一票が政治に反映される可能性が高まり、国民全体の意思をより正確に議会構成に近づけることができます。
また、この仕組みは、特定のテーマ(環境問題など)を掲げる専門的な政党や、新しい考え方を持つ新党などが議席を得る機会を生み出し、議会における議論の多様性を確保する上でも重要な役割を担っていると考えられます。
比例代表はいらないという意見を持つ私たちがすべきこと

- 日本の制度は特殊?世界の選挙から見る比例代表制
- デメリットを知り賢く投票!後悔しない選び方とは
- もし比例代表制を廃止したら選挙はどう変わるか
- 「比例代表いらない」と考える前にできること(まとめ)
日本の制度は特殊?世界の選挙から見る比例代表制

日本の「小選挙区比例代表並立制」は、世界的に見るといくつかの特殊な点があり、必ずしもグローバルスタンダードとは言えません。特に、選挙制度のモデルケースとしてよく比較されるドイツの制度とは、似ているようで根本的な違いがあります。
ドイツが採用しているのは「小選挙区比例代表併用制」です。この制度では、全体の議席数は比例代表の得票率を基準に決定されます。小選挙区での当選は、あくまでその比例で得た議席を誰が埋めるかを決める要素の一つであり、全体の議席配分は国民の政党支持率に限りなく近くなるよう調整されます。
一方、日本の「並立制」は、小選挙区と比例代表の二つの制度が独立して並存している状態です。小選挙区で獲得した議席と、比例代表で獲得した議席を単純に足し合わせるため、小選挙区で多くの議席を獲得した大政党が、実際の得票率以上に多くの議席を得やすくなる傾向があります。これにより、比例代表制が本来持つ「民意を正確に反映する」という機能が弱まっているという指摘があります。
| 項目 | 日本 | ドイツ | 北欧諸国 |
| 制度 | 小選挙区比例代表並立制 | 小選挙区比例代表併用制 | 比例代表制(調整議席あり) |
| 議席配分の基準 | 小選挙区と比例を別々に計算 | 比例代表の得票率が基準 | 全国単位の得票率で調整 |
| 重複立候補 | あり(比例復活) | なし | なし |
| 阻止条項 | なし | あり(全国得票率5%など) | あり(国により2~4%) |
このように他国と比較すると、日本の制度は「比例復活」を認めている点や、小政党の乱立を防ぐ「阻止条項」がない点なども含め、独自に発展した特殊な仕組みであることが分かります。
デメリットを知り賢く投票!後悔しない選び方とは

比例代表制のデメリットを理解した上で、私たち有権者が後悔しない選択をするためには、制度の仕組みを知り、戦略的に投票することが鍵となります。ただ何となく投票するのではなく、一票を投じる先が最終的にどう扱われるかを意識することが大切です。
まず、衆議院の比例代表は「拘束名簿式」であり、有権者は政党名でしか投票できません。当選者は政党が事前に決めた順位で決まるため、どの候補者が上位にいるのか、その人物がどのような考えを持っているのかを事前に確認することが望ましいでしょう。
一方、参議院は「非拘束名簿式」で、政党名または候補者名のどちらでも投票できます。特定の候補者を強く応援したい場合は、候補者名で投票することで、その候補者の当選を直接後押しできます。
ただし、インターネット上で時折見られる「候補者名で書けば2票分の価値がある」といった情報は誤りです。候補者名で書いても、その候補者が所属する政党の得票として1票分がカウントされるだけであり、損得はありません。
制度のデメリットとしては、特に衆議院の比例復活や、参議院で政党が優先的に候補者を当選させられる「特定枠」の存在が挙げられます。これらの仕組みは、政党の意向が強く働くため、有権者の意思とは離れた結果を生む可能性があります。
したがって、投票前には選挙公報や報道を通じて各政党の公約だけでなく、比例代表の名簿順位や特定枠の候補者まで確認し、制度の特性を理解した上で、総合的に判断することが、後悔しないための賢い選び方と言えます。
もし比例代表制を廃止したら選挙はどう変わるか
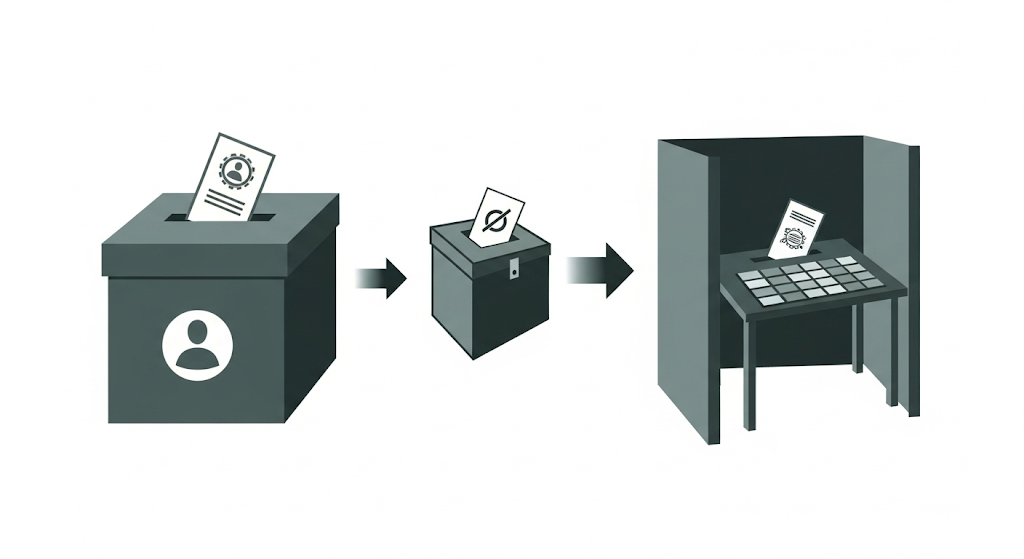
もし比例代表制を完全に廃止し、すべての議席を小選挙区制のみで選ぶことになった場合、日本の政治と選挙は大きく変化します。政権の安定というメリットが生まれる一方で、民主主義の根幹に関わる重大なデメリットも生じることが予測されます。
メリットとしては、まず政権が安定しやすくなる点が挙げられます。小選挙区制は大政党に有利なため、選挙で勝った政党が議会の過半数を占めやすくなり、政策決定がスピーディーに進む可能性があります。また、選挙区ごとに代表者が一人に定まるため、政治的な責任の所在が明確になります。
しかし、デメリットはそれを上回るほど大きいと考えられます。第一に、前述の通り、死票が大幅に増加します。半数近くの票が議席に反映されなくなることで、民意と議会の構成が大きく乖離する「民意の歪み」が深刻化するでしょう。
第二に、少数政党や新興政党が議席を得ることが極めて困難になります。これにより、多様な意見が政治の場から排除され、政治が硬直化する恐れがあります。自分の支持する政党に投票しても当選の見込みがないと感じる人が増え、結果として全体の投票率が低下する可能性も否定できません。
つまり、比例代表制の廃止は、比例復活のような批判の多い問題は解消するかもしれませんが、その代わりに「より多くの民意を切り捨てる」という、さらに大きな課題を生むことになるのです。
「比例代表いらない」と考える前にできること(まとめ)
「比例代表はいらない」という意見には、制度の複雑さや不公平感など、もっともな理由が数多くあります。この記事で解説してきた内容を踏まえ、最後に私たちが有権者として考えるべきポイントをまとめます。
- 比例復活は小選挙区の民意に反すると批判されやすい
- 比例代表制は政党の得票率で議席を配分する仕組み
- 小選挙区制は勝者総取りで死票が多くなりがち
- 日本の制度は小選挙区と比例の「並立制」という特殊な形
- 衆議院は政党が決めた順位で当選する拘束名簿式
- 参議院は個人得票で順位が決まる非拘束名簿式
- 現行制度は1994年の政治改革で導入された
- 目的は金権政治の打破と多様な民意の反映の両立
- メリットは死票が少なく少数意見が反映されること
- デメリットは政権不安定化や候補者の顔が見えにくいこと
- 日本の並立制はドイツの併用制と異なり大政党に有利
- 重複立候補や拘束名簿式は日本の制度が抱える課題
- 制度の欠点を知り賢く投票することが有権者に求められる
- 比例廃止は政権を安定させるが民意の多様性を損なう
- まず制度を正しく理解し選挙に関心を持つことが第一歩










