「会計年度任用職員として働き続けたいけれど、定年は何歳なんだろう…」 「60代になっても働けるのか、何回まで更新できるのか知りたい」 「10年以上、安定して働く方法はあるの?」
このように、会計年度任用職員の定年について、多くの方が疑問や不安を抱えています。雇用の安定性は、生活設計を立てる上で非常に大切な要素です。特に、更新しない理由が自分の評価とは別のところにある可能性を知ると、将来の見通しが立てにくくなるかもしれません。
この記事では、会計年度任用職員の定年に関する制度の基本から、年齢の上限、更新回数の実態、そして長期的に働くための具体的な方法まで、網羅的に解説します。この記事を読めば、あなたの疑問が解消され、今後の働き方を考える上での確かな指針を得られるはずです。
- 会計年度任用職員に定年制度が適用されるかどうかがわかる
- 法律上の年齢上限と、実際の任用年齢の実態が理解できる
- 契約の更新回数や、長期勤続のための具体的な方法がわかる
- 自分の評価とは無関係に契約が更新されない理由がわかる
会計年度任用職員の定年制度に関する基本知識
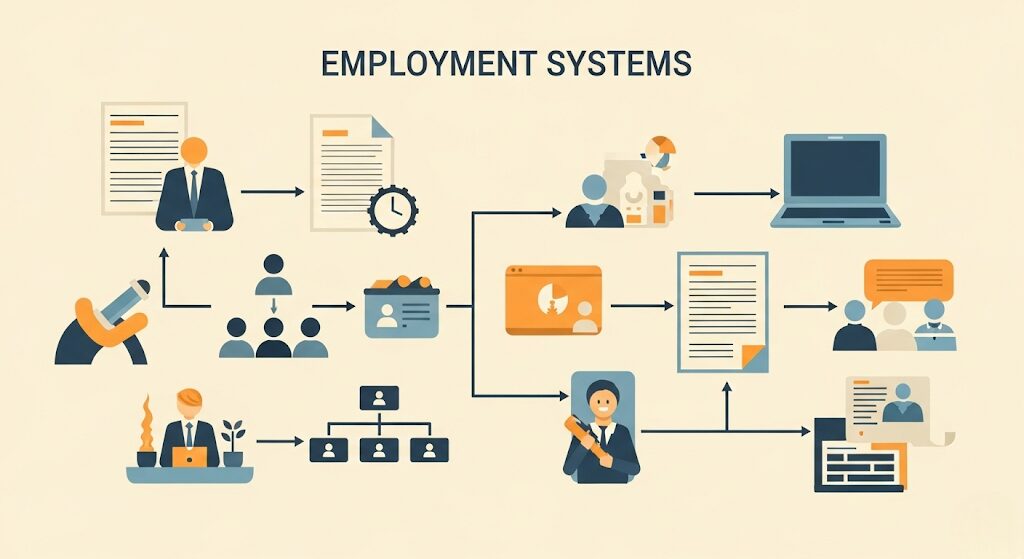
- 会計年度任用職員の定年はいくつですか?
- 結局、会計年度任用職員は何歳まで働けますか?
- 常勤とは違う?会計年度任用職員への「定年延長」の適用
- 60代から働くメリット・デメリット
会計年度任用職員の定年はいくつですか?

会計年度任用職員の定年について、まず押さえておきたいのは、法律上の位置づけです。結論から言うと、会計年度任用職員には、常勤の公務員に適用される「定年制度」そのものがありません。
地方公務員法では、定年制度の対象は常勤職員と定められています。一方で、会計年度任用職員は「任期を定めて任用される職員」に分類されるため、この定年制度の適用対象外と明確に規定されているのです。
これは、もともと会計年度任用職員が1会計年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として任用される仕組みであるためです。したがって、「定年退職」という概念自体が存在しないことになります。
ただし、定年制度がないからといって、無期限に働けるわけではありません。雇用はあくまで1年ごとの契約更新が基本となり、その判断は各自治体に委ねられています。
結局、会計年度任用職員は何歳まで働けますか?

法律上、会計年度任用職員に定年制度は適用されませんが、実際には「何歳まで働けるのか」という実務上の区切りが存在します。多くの自治体では、常勤職員の定年退職年齢である65歳を一つの目安として運用しているのが実情です。
しかし、これはあくまで目安であり、法律で定められた上限ではありません。そのため、自治体の方針や職場のニーズ、本人の健康状態や業務遂行能力によっては、65歳を超えても働き続けることが可能です。
70歳を上限とする自治体も
一部の自治体では、「70歳に達した日以後の最初の3月31日まで」を任用の上限とするなど、より柔軟な運用を行っています。特に、専門的な知識や技能が求められる職種や、人材の確保が難しい分野では、70歳を超えても継続して任用されるケースが見られます。
再任用制度の活用
常勤職員が定年退職した後に適用される「再任用制度」とは異なりますが、会計年度任用職員も任期満了後に再度任用されることで、働き続けることが可能です。
勤務成績が良好であれば、公募を経ずに次の年度も任用される場合が多く、これを事実上の「更新」と捉えることができます。長く働き続けるためには、毎年の業務評価で良い結果を出すことが鍵となります。
常勤とは違う?会計年度任用職員への「定年延長」の適用

常勤の地方公務員では、法律の改正により定年年齢が段階的に65歳へ引き上げられています。これに伴い、「勤務延長」という、定年後も特定の業務のために役職や給与を維持したまま働き続けられる制度があります。
では、会計年度任用職員にこの「定年延長」は適用されるのでしょうか。 答えは「適用されない」です。
前述の通り、会計年度任用職員には定年制度そのものが存在しません。定年というゴールがないため、「定年を延長する」という考え方自体が当てはまらないのです。常勤公務員の定年引き上げのニュースは、会計年度任用職員の雇用条件に直接的な影響を与えるものではない、と理解しておくことが大切です。
両者の制度は根本的に異なるため、混同しないように注意が必要です。会計年度任用職員の雇用継続は、あくまで1年ごとの任用(更新)によって判断されると覚えておきましょう。
60代から働くメリット・デメリット
定年後のキャリアとして、60代から会計年度任用職員を選ぶ人は少なくありません。ここでは、その働き方のメリットとデメリットを多角的に見ていきましょう。
メリット
最大のメリットは、定年退職後も社会とのつながりを維持できる点です。地域社会に貢献している実感や、人と関わることで得られる張り合いは、生活の質を高めてくれます。また、年金に加えて収入を得られるため、経済的な安心感にもつながります。
勤務形態が多様なことも魅力の一つです。週3日勤務や短時間勤務など、自身の体力やライフスタイルに合わせて柔軟な働き方を選びやすくなっています。これまでの職務経験や人生経験が活かせる専門的な職種も多く、やりがいを感じやすいでしょう。
デメリット
一方で、デメリットも存在します。前述の通り、給与水準は決して高くなく、雇用の安定性にも課題があります。契約は1年ごとであり、来年度も継続して働ける保証はありません。この不安定さは、精神的な負担になる可能性があります。
また、常勤職員の補助的な業務だけでなく、責任の重い仕事を任されることも少なくありません。しかし、待遇面では常勤職員と大きな差があり、そのギャップに不満を感じる人もいるようです。自身の健康状態が契約更新に影響する可能性も考慮しておく必要があります。
会計年度任用職員の定年制度|キャリアと雇用安定性

- 上限2回は本当?会計年度任用職員は何回まで更新できますか?
- 知っておくべき最新の法改正と今後の見通し
- 10年以上働くための具体的なキャリアプラン
- 能力だけじゃない!会計年度任用職員が更新されない本当の理由
- もし契約更新されなかった場合の具体的な対処法
- 会計年度任用職員の定年と働き方のポイント(まとめ)
上限2回は本当?会計年度任用職員は何回まで更新できますか?

「会計年度任用職員の更新は2回まで」という話を耳にしたことがあるかもしれません。これは、かつて多くの自治体で運用されていたルールで、初年度を含めて最大3年間の勤務が上限とされていました。
この背景には、特定の職員が長期間同じ職に留まることを避け、広く公平に雇用機会を提供しようという考え方がありました。
しかし、この「上限2回」というルールは、もはや全国共通のものではありません。近年、国の方針転換もあり、この上限を撤廃する自治体が急速に増えています。
現在、自治体ごとの運用は、主に以下の3パターンに分かれています。
- 上限2回(計3年)を維持する自治体
- 上限を4回(計5年)などに緩和する自治体
- 更新回数の上限を完全に撤廃した自治体
専門性の高い職種や人材確保が難しい分野では、上限を設けない傾向が強まっています。したがって、「上限2回」が絶対的なルールではないことを理解し、ご自身が勤務する、あるいは応募を検討している自治体の最新の規定を確認することが何よりも大切です。
知っておくべき最新の法改正と今後の見通し

会計年度任用職員の働き方を考える上で、近年の法改正や制度の動向を把握しておくことは不可欠です。最も大きな変化は、前述した「更新回数の上限撤廃」の流れです。
2024年以降、総務省が自治体向けのマニュアルから更新回数の上限に関する例示を削除したことを受け、多くの自治体が条例や規則の見直しを進めています。この動きは、経験を積んだ優秀な人材を確保し、行政サービスの質を維持・向上させたいという自治体側の狙いも反映しています。
今後の見通しとしては、この「上限撤廃」の流れはさらに拡大すると考えられます。ただし、これは無条件での雇用継続を保証するものではありません。あくまで勤務成績が良好であることや、担当する業務の必要性が継続していることが前提となります。
また、パートタイム職員への勤勉手当(ボーナスの一種)の支給を拡大する動きもあり、少しずつですが待遇改善も進んでいます。将来的には、一定の条件を満たした職員を対象とした正規職員への登用制度を導入する自治体が出てくる可能性も考えられます。
10年以上働くための具体的なキャリアプラン

更新回数の上限が撤廃されつつある中、10年以上の長期的なキャリアを築くことも現実的な目標になりつつあります。そのためには、戦略的なキャリアプランが求められます。
専門性の向上と実績の可視化
まず基本となるのは、自身の専門性を高め、業務実績を客観的な形で示すことです。例えば、担当業務に関する資格を取得したり、業務改善提案を積極的に行ったりすることが挙げられます。
処理件数の向上率や、市民アンケートの満足度など、具体的な数値で成果を示すことができれば、更新時の評価で有利に働きます。
公募への再応募とポジション転換
仮に更新上限がある自治体であっても、一度任期満了で退職した後に、公募選考を経て再度任用される道があります。これまでの実績をアピールして同じ職に応募するだけでなく、ITスキルや語学力など新たなスキルを身につけ、別の部署や職種に挑戦することでキャリアを継続することも可能です。
このように、ただ待つのではなく、自らキャリアを設計し、自治体にとって「必要な人材」であり続ける努力をすることが、10年以上の長期勤続を実現する鍵と言えるでしょう。
能力だけじゃない!会計年度任用職員が更新されない本当の理由

勤務評価も良好で、自分なりに職務を全うしてきたにもかかわらず、契約が更新されない場合があります。これは、本人の能力や勤務態度とは関係のない、行政側の都合が原因であることが少なくありません。
最も多い理由の一つが、担当していた事業そのものが廃止されたり、規模が縮小されたりするケースです。例えば、国の補助金が打ち切られたり、民間委託に切り替わったりすると、その業務に携わっていた職員のポスト自体がなくなってしまいます。
また、自治体の組織改編や部署の統廃合によって、人員整理の対象となることもあります。限られた予算の中で効率的な行政運営を行うため、非正規職員である会計年度任用職員の数が調整されることは珍しくありません。
これらの理由は、職員個人にはどうすることもできない要因です。そのため、会計年度任用職員として働く上では、このような「雇止め」のリスクが常にあることを理解し、万が一に備えておく姿勢が大切になります。
もし契約更新されなかった場合の具体的な対処法

予期せず契約が更新されない「雇止め」に直面した場合、冷静に対処することが求められます。慌てずに、次のステップへ進むための準備をしましょう。
失業保険(雇用保険)の手続き
まず、自身の生活を守るために失業保険の受給手続きを進めます。会計年度任用職員も、一定の加入期間などの要件を満たしていれば、雇用保険の給付対象となります。
行政側の都合による雇止めは「特定理由離職者」に該当する場合があり、その際は通常の自己都合退職よりも給付条件が有利になる可能性があります。手続きには「離職票」が必要となるため、速やかに自治体から交付してもらいましょう。
次の仕事を探す
同時に、新しい仕事を探す活動を開始します。ハローワークはもちろん、民間の転職サイトやエージェントも活用することで、より多くの選択肢から自分に合った仕事を見つけることができます。
これまでの公務経験は、民間企業でも高く評価される場合があります。視野を広げて、積極的に情報収集を行うことが大切です。不当な雇止めが疑われる場合は、労働組合や弁護士などの専門機関に相談することも一つの方法です。
会計年度任用職員の定年と働き方のポイント(まとめ)
この記事で解説した、会計年度任用職員の定年と働き方に関する重要なポイントを以下にまとめます。
- 会計年度任用職員に法律上の定年制度はない
- 定年制度の適用対象外であるため「定年退職」という概念もない
- 実務上は65歳や70歳が年齢の上限目安となることが多い
- 任用の上限年齢は法律ではなく各自治体の判断で決まる
- 定年延長や勤務延長の制度は適用されない
- 給与は常勤職員より低く退職金がない場合が多い
- 60代からでも社会貢献や収入確保のメリットがある
- 一方で雇用が不安定というデメリットも存在する
- 更新回数の「上限2回」ルールは撤廃する自治体が増加中
- 現在は更新回数に上限がない自治体が主流になりつつある
- 長期勤続には専門性の向上や実績のアピールが鍵となる
- 10年以上のキャリアプランも現実的な目標と言える
- 事業の廃止など行政側の都合で更新されないリスクがある
- 雇止めに備え失業保険や転職活動の準備も意識しておく
- 制度を正しく理解し自身のキャリアプランを立てることが大切










