家族の介護が必要になったとき、「仕事を休めるだろうか」「その間の給料はどうなるのだろう」と不安に感じる会計年度任用職員の方は少なくないでしょう。特に、会計年度任用職員の介護休暇が無給であるという事実は、生活への影響を考えると大きな心配事です。
しかし、介護のために利用できる制度は介護休暇だけではありません。この記事では、会計年度任用職員の有給休暇の基本から、最大93日間取得できる介護休暇の詳細、そして長期化した場合の休職制度まで、あなたが知っておくべき情報を網羅的に解説します。
- 会計年度任用職員が利用できる休暇制度の全体像
- 介護休暇が無給である理由と収入を補う公的支援
- 介護休暇の日数や取得単位、具体的な手続き方法
- 介護休暇を使い切った後に利用できる休職制度の条件
会計年度任用職員の介護休暇は無給?休暇制度の基本知識

ここでは、会計年度任用職員が利用できる休暇制度の全体像から、介護休暇が無給である背景、そして関連する制度との違いについて詳しく解説します。
- 会計年度任用職員は有給休暇をもらえる?取得条件を解説
- 会計年度任用職員の特別休暇と無給ケース
- 介護休暇を取得できない場合の具体的な条件とは
- 介護休暇と介護休業はどう違う?給付金の有無
会計年度任用職員は有給休暇をもらえる?取得条件を解説
会計年度任用職員の方も、正規職員と同様に年次有給休暇(年休)を取得する権利があります。これは労働基準法で定められた労働者の権利であり、任用形態に関わらず適用されます。
年次有給休暇が付与されるための基本的な条件は、「6か月以上継続して勤務していること」と「全労働日の8割以上出勤していること」の2点です。
この条件を満たせば、勤務日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。年度の途中で採用された場合でも、任用期間に応じて日数が計算され付与されるのが一般的です。
なお、会計年度任用職員の場合は、自治体によっては「採用日から付与」されるケースもあるため、具体的な付与時期は雇用先の規則を確認してください。
付与される日数は、週の所定勤務日数によって異なります。例えば、フルタイム(週5日勤務)の場合は、採用から6か月後または採用日(自治体の規則による)に10日間付与され、その後は勤続年数に応じて日数が増えていきます。パートタイム勤務の方も、勤務日数に比例した日数が付与されます。
年次有給休暇の付与日数(例)
| 継続勤務年数 | 週5日勤務 | 週4日勤務 | 週3日勤務 | 週2日勤務 |
|---|---|---|---|---|
| 0.5年(初年度) | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 |
| 1.5年 | 11日 | 8日 | 6日 | 4日 |
| 2.5年 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 |
| 6.5年以上 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 |
ただし、これはあくまで一例であり、自治体によって規則が異なる場合があるため、ご自身の雇用条件通知書や所属先の就業規則を必ず確認してください。
会計年度任用職員の特別休暇と無給ケース
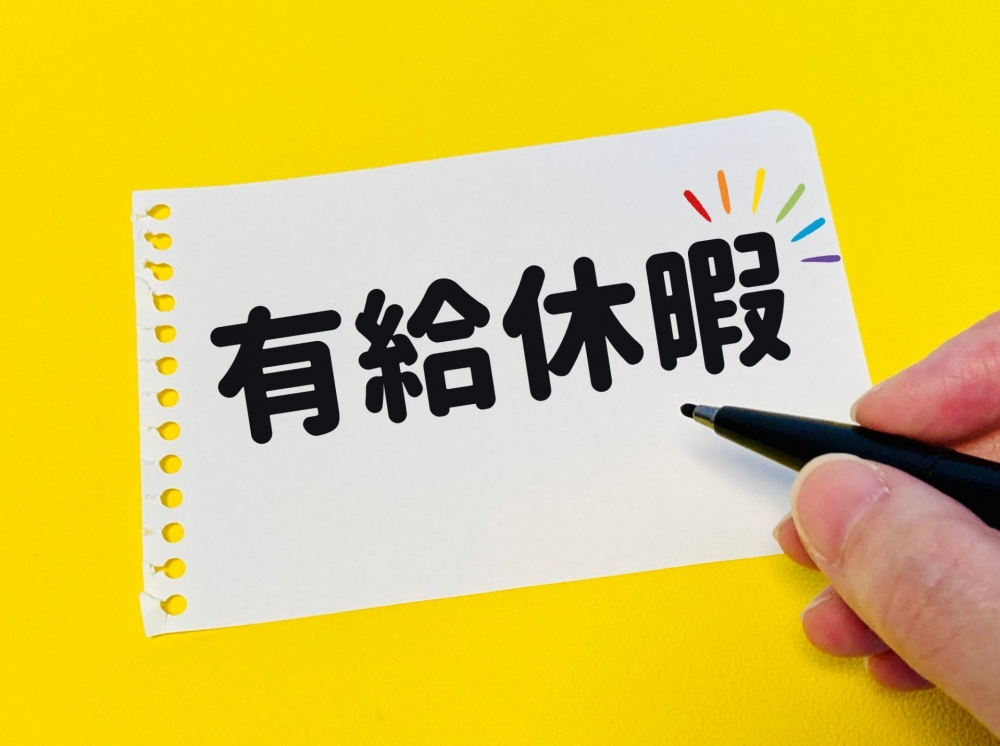
特別休暇には、給与が支払われる「有給」の休暇と、支払われない「無給」の休暇が存在します。どちらに該当するかは、休暇の種類や目的、そして各自治体の条例によって定められています。
一般的に有給となるのは、結婚、忌引、公民権の行使(選挙の投票など)、災害による出勤困難といった、社会通念上やむを得ないと認められる理由や、職員の福利厚生の観点から有給とされている休暇です。
これらは、職員が給与の心配をすることなく、必要な事柄に対応できるように配慮されています。一方で、自身の私的な傷病による病気休暇や、家族の介護を目的とする介護休暇、育児のための休暇などは、無給として扱われる場合があります。
ただし、2025年度からは会計年度任用職員にも有給の病気休暇制度を導入する自治体が増えており、病気休暇が有給となるケースもあります。これらは職員の個人的な事情に基づく休暇と位置づけられているためです。
特別休暇の有給・無給の区分例
| 休暇の種類 | 有給/無給の傾向 | 備考 |
|---|---|---|
| 結婚休暇 | 有給 | 連続5日間など日数が定められていることが多い |
| 忌引休暇 | 有給 | 対象となる親族との続柄に応じて日数が異なる |
| 病気休暇 | 有給または無給 | 2025年度以降、有給制度を導入する自治体が増加。公務災害は有給 |
| 介護休暇 | 無給 | 短期・断続的な介護のための休暇 |
| 子の看護休暇 | 有給または無給 | 有給・無給のいずれかは自治体や企業の規定によりますが、無給としている例が多いです。小学校就学前の子が対象となることが多い |
同じ特別休暇という枠組みの中でも、給与の扱いは大きく異なります。休暇を取得する際には、有給か無給かを事前に人事担当課などに確認することが不可欠です。
介護休暇を取得できない場合の具体的な条件とは
会計年度任用職員の介護休暇は、全ての職員が取得できるわけではなく、一定の要件が定められています。もし、ご自身が以下の条件に当てはまる場合は、制度の対象外となる可能性があるため注意が必要です。
最も一般的な要件は、週の勤務日数です。多くの自治体では、「1週間の勤務日数が3日以上」または「1年間の勤務日数が121日以上」であることを取得の条件としています。したがって、週の勤務日数が2日以下のパートタイム職員の方は、介護休暇を取得できない場合があります。
また、任期の見通しも重要な条件です。介護休暇の申し出があった日から93日を経過する日以降も、引き続き任用される見込みがなければ、休暇の取得が認められません。
例えば、申し出の時点で、すでに年度末での退職が決まっている場合や、任期満了まで93日未満である場合は、対象外となる可能性があります。
これらの条件は、制度の濫用を防ぎ、継続的な雇用関係にある職員を支援するという趣旨に基づいています。ご自身が対象となるか不明な場合は、申請前に所属の担当部署へ確認することをお勧めします。
介護休暇と介護休業はどう違う?給付金の有無
「介護休暇」と「介護休業」は、名前が似ているため混同されやすいですが、目的や期間、給与の扱いに明確な違いがあります。これらの違いを理解しておくことは、ご自身の状況に合った制度を選択する上で非常に大切です。
介護休暇は、要介護者の通院の付き添いや短期的な身の回りの世話など、断続的・短期的な介護ニーズに対応するための制度です。
1日単位や時間単位で、1年度につき5日(対象家族が2人以上の場合は10日)まで取得できますが、休暇中の給与については法律上の定めはなく、会社の規定によります(一般的には無給が多いです)。
一方、介護休業は、より長期的・継続的な介護が必要な場合に、まとまった期間仕事を休むための制度です。対象家族1人につき通算93日まで、最大3回に分割して取得できます。そして、最も大きな違いは、一定の要件を満たせば雇用保険から「介護休業給付金」が支給される点です。
介護休暇と介護休業の主な違い
| 項目 | 介護休暇 | 介護休業 |
|---|---|---|
| 目的 | 短期的・断続的な介護 | 長期的な介護 |
| 取得単位 | 1日または1時間 | まとまった期間 |
| 取得可能日数 | 1年度につき5日(対象家族2人以上は10日) | 通算93日(3回まで分割可) |
| 給与の扱い | 原則無給 | 原則無給 |
| 公的給付金 | なし | あり(雇用保険の要件を満たす場合) |
短時間の休みが必要な場合は「介護休暇」を、長期間の休みと収入の補填が必要な場合は「介護休業」を検討するというのが基本的な考え方になります。
会計年度任用職員が介護休暇(無給)を乗り切る方法

介護休暇が無給であるという事実は変えられませんが、制度を正しく理解し、他の支援策と組み合わせることで、経済的な負担を軽減しながら介護と仕事を両立させる道筋が見えてきます。ここでは、無給の介護休暇を乗り切るための具体的な方法を解説します。
- 介護休業給付金の受給要件
- 最大93日!介護休暇の取得単位と手続き
- 要注意!介護休暇の具体的なカウント方法
- 介護休暇を使い切ったら?会計年度任用職員の休職制度
- 会計年度任用職員の介護休暇が無給でも使える制度(まとめ)
介護休業給付金の受給要件
会計年度任用職員の介護休暇は、地方自治体の条例や規則によって「無給」と定められているのが現状です。これは、正規職員とは異なる任用形態であることや、財源上の制約などが背景にあります。休暇を取得した時間や日数分の給与は支給されないため、収入が減少することは避けられません。
しかし、収入が完全に途絶えるわけではありません。前述の通り、もしあなたが雇用保険に加入しており、一定の条件を満たして「介護休業」を取得する場合、「介護休業給付金」を受給できる可能性があります。
これは、休業開始前の賃金の67%が支給される制度で、無給期間中の生活を支える大きな助けとなります。
介護休業給付金の主な受給要件
- 雇用保険に加入していること
- 介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上あること
- 介護休業期間中の各1か月ごとに、休業開始前の1か月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
ご自身の雇用保険の加入状況を確認し、長期の介護が必要になった場合は、介護休業の取得と給付金の申請を検討することが、経済的な不安を和らげる鍵となります。
最大93日!介護休暇の取得単位と手続き
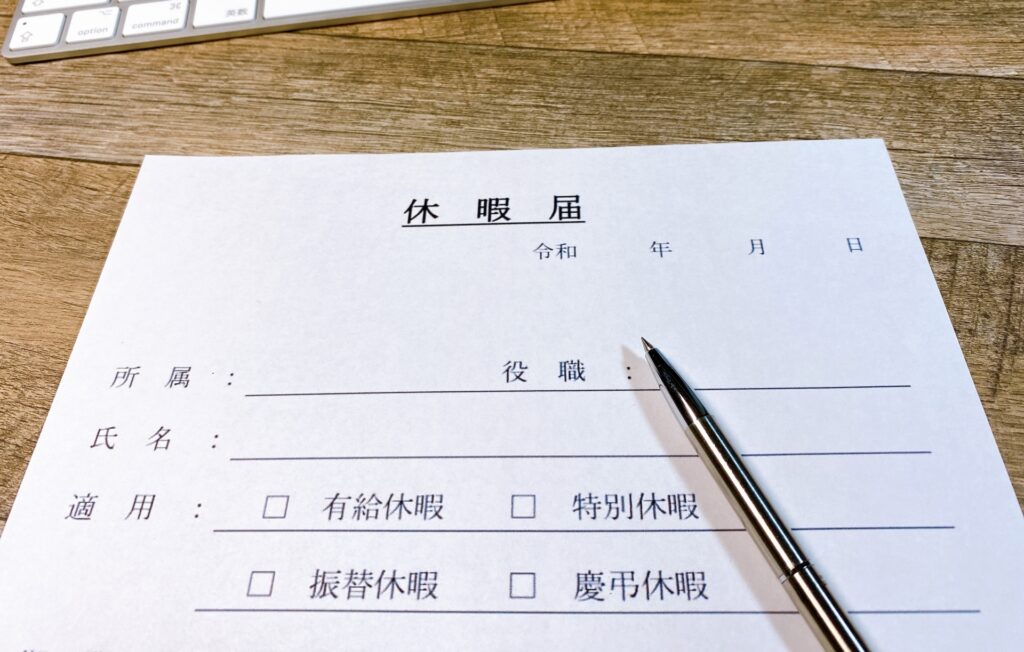
会計年度任用職員の介護休暇は、要介護状態にある対象家族1人につき、通算で93日の範囲内で取得することが可能です。この日数は、様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、分割して取得することができます。
取得する際の単位は、「1日単位」または「1時間単位」が基本です。ただし、自治体によっては「1日単位のみ」としている場合もあるため、必ず所属自治体の規定をご確認ください。
1日単位は、終日休む場合に利用します。一方、時間単位での取得は、通院の付き添いや役所の手続きなど、数時間だけ職場を離れる必要がある場合に便利です。これにより、年次有給休暇を温存しながら、必要な時間だけ介護に充てられます。
介護休暇の申請手続きの流れ
- 所属長への申し出
まず、介護休暇を取得したい旨を所属長に伝えます。 - 申請書の提出
自治体所定の申請書に、取得希望日時、介護の理由、対象家族との続柄などを記入して提出します。 - 証明書類の準備
多くの場合は不要ですが、自治体によっては介護が必要であることを証明する書類(診断書など)の提出を求められることもあります。 - 承認
申請内容が承認されれば、休暇を取得できます。
手続きをスムーズに進めるためには、介護が必要になる可能性が見えた段階で、早めに所属の担当部署に相談し、必要な手続きや書類について確認しておくことが望ましいです。緊急の場合でも、できる限り速やかに申請手続きを行うようにしましょう。
要注意!介護休暇の具体的なカウント方法
介護休暇の「93日間」という日数の数え方には、注意すべき点があります。この日数は、実際に勤務を休んだ労働日数だけを数えるのではなく、休暇を開始した日から終了した日までの「暦日数」で計算されるのが一般的です。
これは、土曜日、日曜日、祝日といった、もともと勤務が割り振られていない休日も、93日のなかに含まれることを意味します。例えば、月曜日から翌週の金曜日まで、勤務日にして合計10日間の介護休暇を取得したとします。
この場合、間にある土日2日×2週=4日間も休暇期間に含まれるため、93日の残日数は14日分減少することになります。
このカウント方法を知らないと、想定よりも早く取得可能日数を使い切ってしまう可能性があります。特に、長期間まとめて休暇を取得しようと考えている場合は、暦上の日数を正確に把握し、計画的に利用することが不可欠です。
休暇の残日数については、人事担当課などで管理されています。ご自身の残日数が分からなくなった場合は、必ず確認するようにしてください。計画的な利用が、いざというときに制度を有効活用するためのポイントです。
介護休暇を使い切ったら?会計年度任用職員の休職制度
介護休暇の93日間をすべて使い切っても、なお家族の介護のために仕事を休む必要がある場合、次の選択肢として「休職制度」の利用が考えられます。これは、職員としての身分を保持したまま、一定期間、職務に従事することを免除してもらう制度です。
休職を申請するためには、介護休暇と同様に、継続的な勤務の見込みがあることなど、自治体が定める一定の要件を満たす必要があります。休職期間中は、職務に従事しないため給与は支給されませんが、共済組合に加入している場合は、傷病手当金などが支給される可能性があります。
ただし、休職制度の利用には注意も必要です。休職期間が満了しても復職できない場合は、退職に至る可能性があります。また、休職期間は期末・勤勉手当(ボーナス)の算定や、将来の昇給に影響する場合もあります。
休職は、介護と仕事の両立を図るための最終手段の一つと位置づけられます。利用を検討する際は、制度のメリットだけでなく、デメリットやリスクについても十分に理解した上で、所属長や人事担当部署とよく相談し、慎重に判断することが求められます。
会計年度任用職員の介護休暇が無給でも使える制度(まとめ)
この記事では、会計年度任用職員の介護休暇とそれに関連する制度について解説しました。最後に、重要なポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員も年次有給休暇を取得する権利がある
- 付与日数は週の勤務日数や勤続年数によって異なる
- 特別休暇には有給のものと無給のものがある
- 結婚休暇や忌引休暇は有給、病気休暇や介護休暇は無給が一般的
- 介護休暇は原則として無給であり給与は支給されない
- 無給の根拠は各自治体の条例や規則で定められている
- 介護休暇は要介護者1人につき通算で93日まで取得可能
- 取得単位は1日単位または1時間単位が基本
- 93日間のカウントは土日祝を含む暦日数である点に注意が必要
- 介護休暇の取得には週の勤務日数などの要件がある
- 介護休暇と介護休業は目的や給付金の有無が異なる制度
- 長期の休みと収入補填が必要な場合は介護休業を検討する
- 介護休業は雇用保険の要件を満たせば給付金の対象となる
- 介護休暇を使い切った後は休職制度を利用できる場合がある
- 休職制度の利用は給与や賞与、退職の可能性など注意点を理解する










