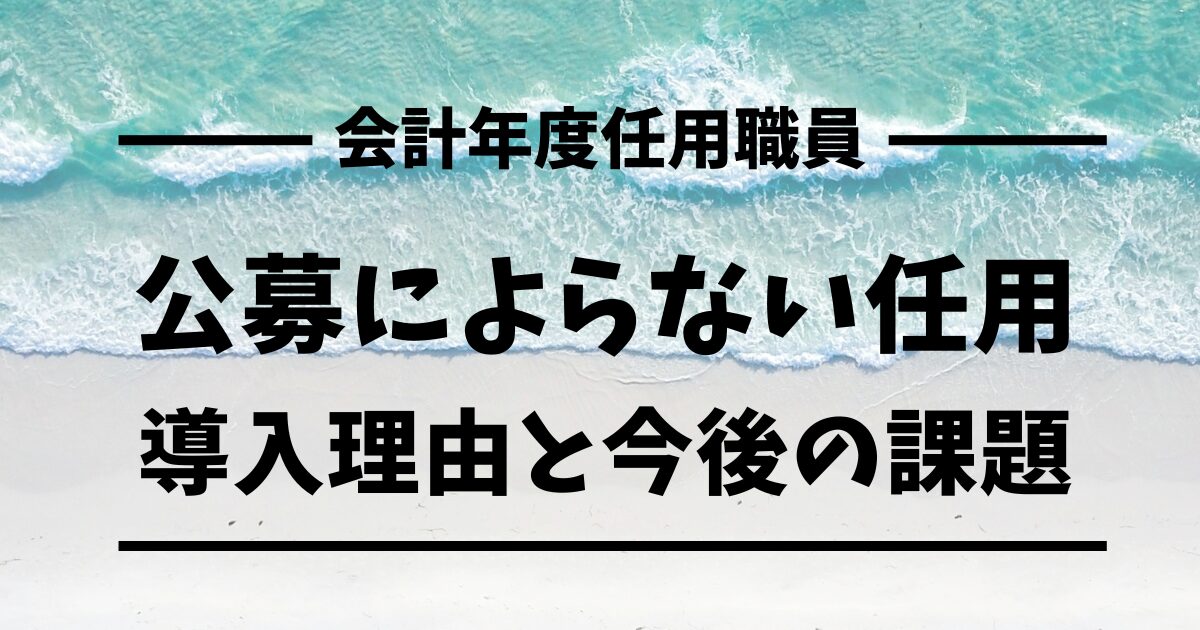会計年度任用職員制度は、地方自治体で働く非常勤職員の働き方を整えるために導入された制度です。これまで多くの自治体では毎年公募が原則とされ、契約更新のたびに応募と選考が必要とされてきました。しかし近年、公募によらない採用が一部で可能となり、大きな注目を集めています。
とくに2024年の制度改正以降は、「公募撤廃」の動きが進み、再度の任用にあたって公募を省略できるケースが出てきました。この背景には、熟練した人材を確保しやすくするための考え方や、雇用の安定化を求める声があります。実際に、同じ職員が10年以上働き続けられるような仕組みも整備されつつあります。
この記事では、会計年度任用職員における公募撤廃の根拠や実際の運用、そしてどのような場合に公募によらない任用が可能になるのかをわかりやすく解説します。
- 公募によらない任用が可能になった制度の背景と理由
- 公募撤廃の条件や適用されるケース
- 地方公務員法や総務省通知による制度の根拠
- 10年以上働くための再任用や長期勤務の工夫
【会計年度任用職員】公募によらない任用の制度理解

- 会計年度任用職員とは?
- 会計年度任用職員は毎年公募ですか?
- 公募の根拠と法的位置付け
- 公募撤廃はいつから?
会計年度任用職員とは?
会計年度任用職員とは、地方自治体が採用する臨時または非常勤職員のことを指します。この制度は、2020年4月1日に施行された「会計年度任用職員制度」に基づいています。制度の目的は、地方自治体の業務を効率的に運営するために、臨時職員を安定した条件で雇用し、働きやすい環境を提供することです。
制度の目的
会計年度任用職員制度の主な目的は、非常勤職員の労働条件を改善することです。従来の臨時職員制度では、雇用契約が不安定であったため、制度を整えたことで、より長期的な雇用が可能になりました。また、任期が1年間で更新される仕組みにより、業務の進捗管理が計画的に行いやすくなります。
制度の導入背景
これまで、臨時職員は基本的に1年ごとの契約更新であり、契約終了後に再採用されるかどうか不明な状態でした。この問題を解決するために、会計年度任用職員制度が導入されました。これにより、任用条件が明確化され、雇用の安定性が高まりました。
任用形態
会計年度任用職員は、フルタイムまたはパートタイムで採用され、1会計年度(4月1日~翌年3月31日)の間に働きます。業務内容や勤務地によって具体的な条件は自治体ごとに異なりますが、基本的に1年ごとの契約が行われます。この制度により、臨時職員も一定の福利厚生を享受できるようになっています。
会計年度任用職員は毎年公募ですか?

会計年度任用職員は、原則として毎年公募が行われます。これは、任期付きの契約職員であり、次年度の職員を選ぶためには新たに公募を行う必要があるからです。
公募が毎年行われる理由
会計年度任用職員は1年間の契約が基本です。契約が終了するため、次の年度に同じ業務を担当するためには再度公募を行うことが求められます。これにより、公平性が保たれ、各年度ごとに適任者を選ぶことができます。
法的根拠
公募が毎年行われる理由には、地方公務員法が関連しています。この法律により、公務員の採用は原則として競争的な方法で行うことが求められています。会計年度任用職員もこの基準に基づいて採用され、適正な選考を経て任用されます。また、公募を通じて選ばれた職員は、業務の透明性を高め、適切な人材を確保できます。
公募の根拠と法的位置付け
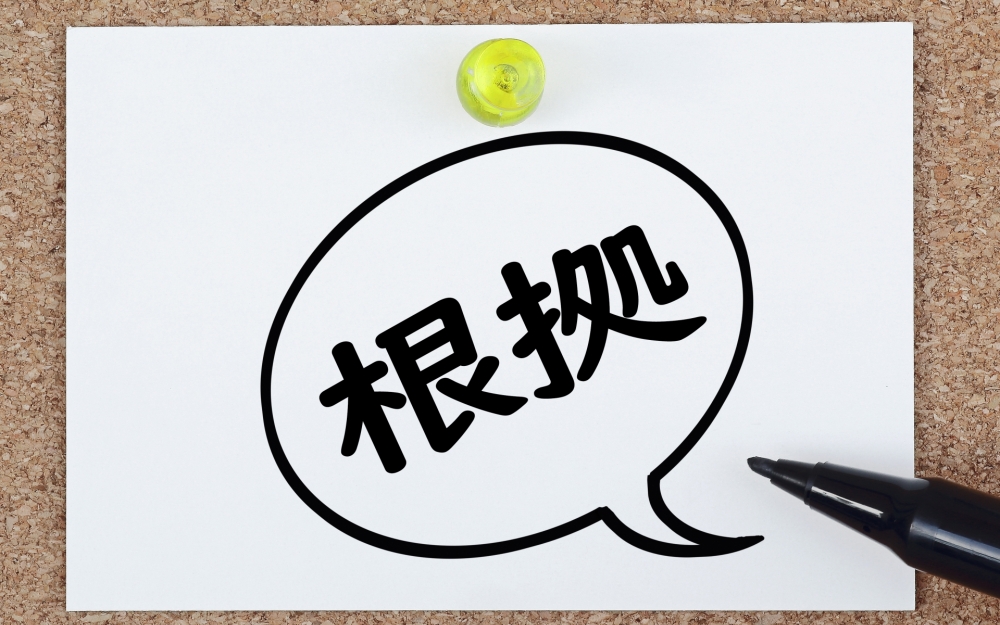
会計年度任用職員の採用では、公募が法律上必須ではありませんが、すべての人に平等に働く機会を与えるため、できる限り広く募集することが望ましいとされています。この考え方を支えているのが「地方公務員法」と「総務省の通知」です。
まず、地方公務員法では、「成績主義」と「公平な採用」が基本の考え方とされています。つまり、だれでも実力で採用されるチャンスがあります。
また、総務省の通知には、公募の方法や流れが詳しく書かれています。
たとえば、
といったルールが示されています。
このような法律や通知により、職員の採用は透明で公正に保たれています。一部では、再び同じ人を任用する「再度の任用」もありますが、その場合でも、公募を行う形は守られることが望ましいとされています。
公募撤廃はいつから?

会計年度任用職員の「公募のルール」に大きな変化が起きたのは、2024年に入ってからです。それまで、公募は毎年必ず行わなければならない決まりでした。しかしこの年、総務省が出した新しい通知によって、一部の例外として「公募をしないで任用する」ことが認められるようになりました。
この動きは「公募撤廃」と呼ばれています。実際には、すべてのケースで公募が不要になったわけではありません。次のような理由があるときに限って、例外として認められます。
- 専門的な知識や経験が必要で、人材の確保が難しいとき
- 長く同じ仕事をしていて、急に交代すると業務に支障が出るとき
- 地域の事情に合わせて柔軟な対応が求められるとき
つまり、「能力があって必要とされている人」は、再び選考しなくても続けて働けるようになってきたのです。
公募撤廃が可能になった背景には、人材不足や職員の安定した雇用を求める声があります。ただし、すべての自治体で一律に運用されるわけではありません。地域ごとに、どのように取り入れるかを決める裁量があります。
この変更により、公募にこだわらない柔軟な働き方が少しずつ広がってきています。
【会計年度任用職員】公募によらない任用の運用実態と今後
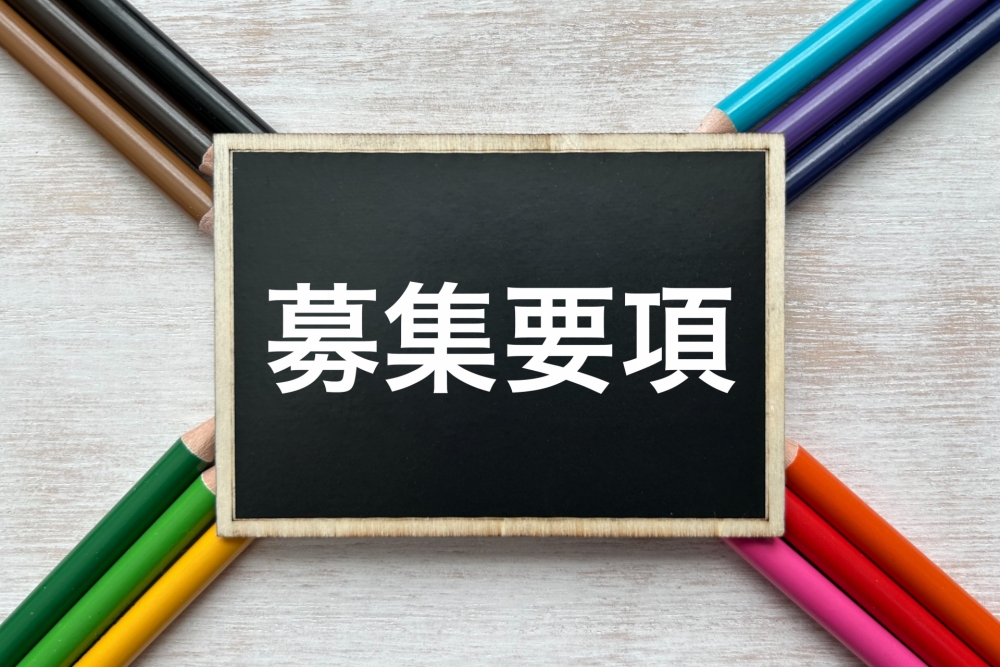
- 再度の任用は何回まで可能?回数制限の真実
- 公募撤廃のメリット・デメリットとは
- 任用が更新されなかった理由とは?
- 会計年度任用職員が10年以上働くには?
- 【会計年度任用職員】公募によらない任用の制度(まとめ)
再度の任用は何回まで可能?回数制限の真実
会計年度任用職員は、1年ごとの契約で働く職員です。では、同じ人を何回まで任用できるのでしょうか。以前は「最大で2回まで」というルールが多くの自治体で使われていました。つまり、最長3年で契約を終える仕組みでした。
しかし近年、このルールが見直され、「何回でも再任用できるようにする」動きが全国で進んでいます。総務省は2024年、再任用の回数制限をなくすよう通知しました。これにより、職員の能力や仕事ぶりを見て、必要であれば続けて雇えるようになります。
現在の運用では、以下のような対応が見られます。
- 回数の制限を完全に撤廃した自治体(例:与那原町など)
- 特定の業務や部門でのみ長期任用を認めている自治体(例:札幌市の例外規定)
- 条件付きで長期任用を認める自治体(勤務評価などで判断)
この変更により、職員にとっては安心して長く働ける可能性が広がりました。一方で、自治体側にも引き続き公平な選考や評価が求められます。
再度の任用は、働き手の経験を活かす重要な制度です。ただし、無制限に認めるわけではなく、「能力」「必要性」「手続きの透明性」がしっかりそろっていることが前提となります。
公募撤廃のメリット・デメリットとは

会計年度任用職員の採用は、これまで「毎年の公募」が基本でした。けれども最近では、公募をしない採用、つまり「公募撤廃」ができるようになりました。この制度の変化には良い面と気をつけるべき面があります。
まず、公募撤廃の【メリット】から見ていきましょう。
- 職員が安定して働ける
毎年の応募や面接が不要になるため、安心して仕事に集中できます。 - 仕事の引き継ぎがスムーズ
同じ人が続けて働くため、仕事の流れを知っている人が現場に残ります。 - 教育コストが減る
新人を一から教える手間が少なくなり、現場の負担も減ります。
次に、【デメリット】も確認しておきましょう。
- 新しい人が入りにくくなる
同じ人ばかりが選ばれると、新しい考えやスキルが入りにくくなります。 - 不公平感が出る場合もある
採用の透明性が下がると、「なぜこの人だけ?」と感じる人が出てきます。 - 地域ごとに差が広がる可能性
自治体によって運用の仕方が違うため、不公平な状況になる心配もあります。
公募撤廃には利点と課題の両方があり、使い方次第で大きく影響が変わってきます。大切なのは、職員にも市民にも納得してもらえる制度運用を行うことです。
任用が更新されなかった理由とは?

会計年度任用職員は、基本的に1年ごとの契約です。そのため、翌年も必ず更新されるわけではありません。更新されなかった場合には、いくつかの原因があります。
まず考えられるのは、予算や業務内容の変化です。年度によって業務がなくなったり、人数が必要なくなる場合があります。とくに地方自治体では、急な予算カットにより職員を減らさなければならないこともあります。
次に勤務態度や実績が見られる場合があります。仕事に遅れが多い、ルールを守らない、チームとうまくいかないなどの理由で、更新を見送られる場合もあります。
また、再度任用の回数制限が原因となることもあります。以前は2~3回までの再任用を上限とする自治体が多く、それを超えると新たな応募が必要でした。現在はこの制限が緩くなってきている自治体もありますが、完全に撤廃されていないところもあります。
さらに、公平性を保つために新規の公募を優先することもあります。同じ人ばかりを採用し続けるのではなく、新しい人にもチャンスを与える必要があるためです。
更新されない時は、こうしたいくつかの要因が重なっている場合も多いため、事前に上司との面談で確認したり、自治体の方針を調べておくことが大切です。
会計年度任用職員が10年以上働くには?

会計年度任用職員が10年以上働くには、いくつかの工夫や条件をクリアする必要があります。会計年度任用職員は、1年ごとの契約が基本となるため、長く続けるには自治体の方針と自分の努力が重要です。
まず大切なのは「再度の任用」に選ばれることです。勤務態度が良く、仕事のスキルが高ければ、次年度も採用される可能性が高くなります。これを何年も繰り返すことで、結果として10年以上働くことができます。
ただし、すべての自治体が無制限に任用を続けてくれるわけではありません。以前は「3年まで」という上限があるところも多く見られました。しかし近年では、その制限を撤廃している自治体も増えてきています。
具体的には、以下のような対応が見られます。
- 例外規定の活用
専門知識や経験が必要な業務では、同じ人を続けて雇うケースもあります。 - 部署の移動
同じ自治体内で部署を変えて勤務を継続する例もあります。 - 実績評価の導入
能力や過去の仕事ぶりで判断される制度が広がっています。
また、長く働きたい場合は、自分から自治体の採用情報をこまめにチェックし、ルールの変更などを早めに知ることも大切です。制度や方針は変わることがあるため、常に情報を集めておきましょう。
【会計年度任用職員】公募によらない任用の制度(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員は地方自治体が採用する非常勤の職員である
- 2020年4月から制度が始まり、臨時職員制度を整備したものである
- 任期は原則1年間で、フルタイムまたはパートタイムで任用される
- 採用は基本的に毎年公募によって行われる
- 公募の背景には公平性と成績主義の原則がある
- 地方公務員法と総務省の通知が公募の根拠となっている
- 公募では書類選考や面接などが実施される
- 2024年に総務省の通知で公募撤廃が一部認められた
- 公募によらない採用が可能な例は専門性や継続性が必要な場合である
- 公募撤廃はすべてのケースに適用されるわけではない
- 再度の任用は以前は2回までが多かったが、今は回数制限を撤廃する自治体もある
- 公募撤廃には職員の雇用安定や引き継ぎの簡略化というメリットがある
- 一方で新規採用の機会が減るなどのデメリットも存在する
- 任用更新がされない理由には予算不足や評価不良などがある
- 10年以上勤務するには継続的な任用と自治体の柔軟な対応が必要である