「市役所職員になりたい」と考えたとき、多くの人が直面するのが「試験は難しいのだろうか」という不安ではないでしょうか。公務員試験に落ちてしまう確率や、そもそも公務員試験で1番難しいのはどの区分なのか、気になる点は多いことでしょう。
しかし、市役所試験の過去問を正しく活用したり、自治体によっては市役所を教養試験のみで受験したりと、戦略次第で合格の可能性は大きく変わります。また、実は市役所には受かりやすい市というのも存在します。
この記事では、客観的なデータに基づいて市役所試験のリアルな難易度を解説するとともに、合格に向けた具体的な学習法や戦略的な自治体の選び方まで、あなたの疑問を解消します。
- 市役所採用試験の客観的な難易度と合格率
- 他の公務員試験との難易度の違い
- 合格に必要な勉強時間と具体的な対策法
- 学習負担を減らす戦略的な自治体の選び方
「市役所の採用試験が難しい」と言われる客観的な理由

- 試験の難易度は?倍率とボーダーで見る事実
- 公務員試験で1番難しいのは?市役所・県庁・国家の違い
- 試験に落ちてしまう確率は?
- 市役所の試験内容は?教養・専門・面接の対策法
- 市役所合格にはどのくらい勉強が必要?科目別の配分術
試験の難易度は?倍率とボーダーで見る事実
市役所の採用試験は、客観的なデータを見ると決して簡単な試験ではないことが分かります。感覚的な難しさではなく、具体的な数字を把握することが対策の第一歩となります。
まず、近年の市役所試験の平均倍率は約5~7倍、合格率は15~17%前後で推移しています。これは、限られた採用枠に対して、安定性や地域貢献といった魅力から多くの志願者が集まるためです。特に人気の高い市区や小規模な自治体では、倍率が10倍を超える場合も珍しくありません。
| 地域・区分 | 合格率の目安 | 平均倍率の目安 |
| 市区 | 約15~17% | 約5~7倍 |
| 都道府県 | 約20%前後 | 約3.9~4.5倍 |
| 町村 | 約20%前後 | 約3.9~4.1倍 |
また、筆記試験の合格ライン(ボーダーライン)は、一般的に教養科目で6~7割程度の得点率が求められます。倍率が高い自治体ほど合格ラインも上がる傾向にあり、7割以上の正答が必要になるケースも考えられます。
これらの数字から、市役所試験に合格するためには、しっかりとした準備と戦略が不可欠であると言えます。
公務員試験で1番難しいのは?市役所・県庁・国家の違い
公務員試験と一括りに言っても、その種類によって難易度は大きく異なります。市役所試験が全体の中でどの程度のレベルに位置するのかを理解することも大切です。
公務員試験の中で最も難易度が高いとされるのは、将来の幹部候補を採用する「国家総合職」です。一方で、市役所は公務員試験全体の中では、中下位レベルに位置づけられる場合が多いです。
ただし、これはあくまで一般的な序列であり、「市役所だから簡単」と考えるのは誤りです。横浜市などの人気の政令指定都市では、倍率が10倍を超え、県庁の試験を上回る難易度になることもあります。
仕事内容も、県庁が広域行政(都市計画や産業振興など)を担うのに対し、市役所は住民票の発行や税金の徴収など、市民の生活に密着した業務が中心となります。求められる役割が異なるため、試験の内容や重視される能力にも違いが生まれるのです。
試験に落ちてしまう確率は?

前述の通り、市役所採用試験の合格率は決して高くなく、地方公務員試験全体では約8割の人が不合格になるというデータもあります。この厳しい現実を乗り越えるためには、不合格になる人の特徴を知り、それを避けることが有効です。
市役所試験で不合格になる人には、主に3つの共通点が見られます。
1. 面接対策の不十分さ
筆記試験の対策に時間をかけすぎ、面接準備が後回しになるケースです。近年の公務員試験は人物重視の傾向が強く、面接での評価が合否を大きく左右します。
2. 明確な志望動機の欠如
「なぜ公務員なのか」「なぜこの市役所なのか」という問いに、具体的で説得力のある回答ができないと、意欲が低いと判断されかねません。
3. 学習計画の不足
市役所採用試験の範囲は広いため、計画性のない学習では全範囲をカバーしきれません。合格には大卒程度で800時間以上の勉強が必要とされており、計画的な学習習慣がなければ、この時間を確保するのは困難です。
これらの特徴を反面教師として、バランスの取れた対策を進めることが合格への道を拓きます。
市役所の試験内容は?教養・専門・面接の対策法

市役所試験は、主に「筆記試験」と「人物試験(面接など)」の2段階で構成されています。それぞれの内容を理解し、適切な対策を講じることが求められます。
筆記試験は、多くの自治体で課される「教養試験」と、主に大卒程度の試験で課される「専門試験」に分かれます。
教養試験は、数的処理や文章理解といった知能分野と、社会科学や人文科学などの知識分野から出題される、いわば公務員試験の基礎です。
一方、専門試験では、憲法や民法、経済学といった大学レベルの専門知識が問われます。
そして、筆記試験を突破した先に待っているのが面接試験です。個別面接が一般的ですが、自治体によっては集団討論が実施されることもあります。ここでは知識だけでなく、コミュニケーション能力や公務員としての適性が厳しく評価されます。
対策としては、出題数の多い教養試験の数的処理を最優先で固めることが基本です。専門試験がある場合は、自身の得意分野や併願先を考慮して科目を選択し、深く学習することが大切です。
面接対策は、自己分析と自治体研究を徹底し、模擬面接などを通じて実践練習を重ねることが鍵となります。
市役所合格にはどのくらい勉強が必要?科目別の配分術

市役所試験の合格に必要な勉強時間は、試験の区分や個人の学力によって異なりますが、一つの目安として大卒程度の行政職では800~1500時間程度が必要とされています。これは、1日3時間の勉強を1年弱続ける計算になり、長期的な計画が不可欠です。
この膨大な勉強時間を効率的に使うためには、科目別の時間配分が重要になります。特に教養試験では、全問題数の中で「数的処理」と「文章理解」が占める割合が非常に高いため、これらの科目に学習時間の多くを割くのがセオリーです。
例えば、学習時間全体の約半分を知能分野(数的処理・文章理解)に充て、残りを知識分野(社会科学・人文科学など)に配分する計画が考えられます。専門科目がある場合は、さらに憲法・民法・行政法といった主要科目に時間を重点的に配分する必要があります。
いきなり全科目を始めるのではなく、まずは数的処理などの重要科目から着手し、基礎が固まってきたら他の科目に広げていくという段階的な学習が、挫折を防ぎ着実に力をつけるためのポイントです。
市役所の採用試験は難しい|具体的な戦略
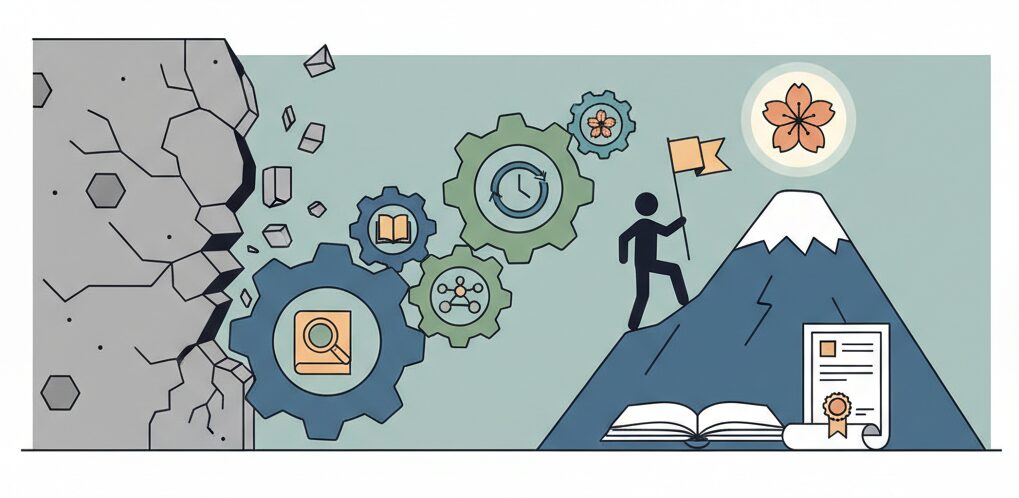
- 過去問はいつから何年分解く?活用術
- 筆記より重要?人物重視の面接試験を突破するコツ
- 受かりやすい市役所はある?
- 市役所の採用試験は難しい?その実態と対策(まとめ)
過去問はいつから何年分解く?活用術

試験対策において、過去問演習は最も効果的な学習方法の一つです。過去問は、単に力試しをするためのものではなく、合格への最短ルートを示す道しるべと考えるべきです。
過去問に取り組む最適な時期は、基礎学習と並行して進めるのが理想です。学習を始めて早い段階で一度過去問に目を通し、どのような問題が出題されるのか全体像を掴むと、その後の学習方針が立てやすくなります。
解くべき年数としては、最低でも3年分、できれば5年分を繰り返し解くことが推奨されます。これにより、頻出のテーマや問題形式を体で覚えることができます。
最も大切なのはその活用法です。ただ解いて丸付けをするだけでは効果は半減してしまいます。間違えた問題は必ず解説を読み込み、なぜ間違えたのかを分析する「解き直し」を徹底してください。
また、本番と同じ制限時間を設けて解くことで、時間配分の感覚を養うこともできます。過去問を徹底的に分析し、自分の弱点を克服していくと、合格をぐっと引き寄せるのです。
筆記より重要?人物重視の面接試験を突破するコツ

近年の採用試験では、筆記試験の成績が良くても面接で不合格になるケースが少なくありません。これは、知識量だけでなく、公務員として働く上での人間性やコミュニケーション能力を重視する「人物重視」の傾向が強まっているためです。
したがって、面接対策は筆記試験対策と同等、あるいはそれ以上に重要と考える必要があります。面接を突破するためのコツは、付け焼き刃のテクニックではありません。
まずは「自己分析」を徹底し、自分の長所や短所、これまでの経験を整理し、なぜ市役所職員になりたいのかという原点を明確にすることがスタートです。次に、志望する自治体の政策や課題を調べる「自治体研究」を深め、その市で働きたいという熱意を具体的に語れるように準備します。
そして、これらの準備を土台として、大学のキャリアセンターや予備校などを活用し、模擬面接を繰り返し行うことが不可欠です。第三者からの客観的なフィードバックを受けることで、自分では気づかない話し方の癖や内容の矛盾点を修正し、自信を持って本番に臨むことができます。
受かりやすい市役所はある?

「受かりやすい市役所」の明確な定義はありませんが、戦略的に受験先を選ぶことで、合格の可能性を高めることは可能です。そのためのコツは、主に3つの視点から考えられます。
一つ目は「採用人数の多さ」です。横浜市や大阪市などの政令指定都市は、職員数が多いため毎年の採用予定者数も多い傾向にあります。合格者の枠が広い分、チャンスも大きいと考えられます。
二つ目は「試験日程」です。公務員試験は、A日程(6月)、B日程(7月)、C日程(9月)など、自治体の規模によって主要な試験日が分かれています。他の主要な公務員試験や民間企業の選考と日程が重ならない自治体を選ぶことで、有力なライバルが分散し、相対的に競争が緩やかになる可能性があります。
三つ目は、言うまでもなく「倍率の低さ」です。ただし、倍率が低い自治体は採用人数が極端に少ない場合もあるため、数字の表面だけを見るのではなく、過去数年間の採用実績と合わせて判断することが大切です。
これらの視点を組み合わせて、自分にとって有利な条件の自治体を見つけ出すことが、賢い受験戦略と言えるでしょう。
市役所の採用試験は難しい?その実態と対策(まとめ)
最後に記事のポイントをまとめます。
- 市役所採用試験の平均倍率は約5〜7倍、合格率は15〜17%前後である
- 人気の市区や小規模な自治体では、倍率が10倍を超える場合もある
- 筆記試験の合格ラインは、教養科目で6〜7割程度の得点率が求められる
- 公務員試験の中で最も難易度が高いのは「国家総合職」である
- 市役所は公務員試験全体の中では、中下位レベルに位置づけられる
- 地方公務員試験全体では約8割の人が不合格になるというデータもある
- 近年の公務員試験は人物重視の傾向が強く、面接での評価が合否を大きく左右する
- 合格には大卒程度で800時間以上の勉強が必要とされている
- 筆記試験は「教養試験」と「専門試験」に分かれる
- 面接対策は、自己分析と自治体研究を徹底し、模擬面接などを通じて実践練習を重ねることが鍵となる
- 過去問は最低でも3年分、できれば5年分を繰り返し解くことが推奨される
- 間違えた問題は必ず解説を読み込み、なぜ間違えたのかを分析する「解き直し」を徹底する
- 採用人数の多い政令指定都市は、合格者の枠が広くチャンスも大きい
- 他の公務員試験や民間企業の選考と日程が重ならない自治体を選ぶと、有力なライバルが分散する可能性がある
- 倍率の低い自治体は採用人数が極端に少ない場合もあるため、過去数年間の採用実績と合わせて判断することが大切である










