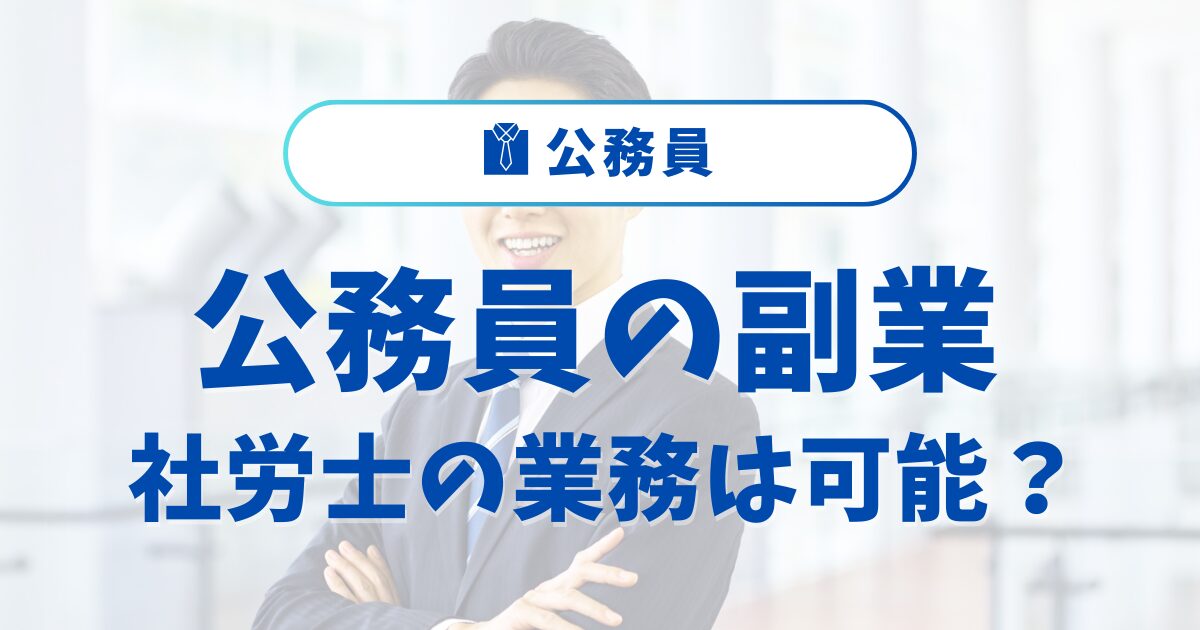公務員として働きながら社労士資格を取得し、副業として活かすことは可能なのかと気になる方も多いでしょう。公務員の副業には厳しい制限がありますが、一定の条件下で可能な副業も存在します。
特に、社労士資格を取得すれば、公務員としての業務に役立てたり、退職後に独立開業する選択肢も広がります。では、勤務しながら社労士登録して開業することはできるのでしょうか。公務員の副業には法律上の規制があり、開業には制限があります。
本記事では、公務員が社労士を目指すメリットや副業の可否、社労士資格の活かし方について詳しく解説します。公務員としてのキャリアを考えながら、社労士資格をどのように活用できるのかを一緒に確認していきましょう。
- 公務員が副業として社労士業務を行う際の制限と許可条件について
- 公務員が可能な副業の種類と社労士資格の活用方法
- 公務員が社労士登録をする際の条件と手続きの流れ
- 社労士資格を取得後、公務員の仕事や転職にどう活かせるか
公務員は社労士として副業できる?

- 公務員のダブルワークは禁止されていますか?
- 公務員が可能な副業は?
- 公務員は勤務しながら社労士登録して開業できる?
公務員のダブルワークは禁止されていますか?
公務員は原則としてダブルワーク(副業)が禁止されています。これは、公務員が公正で公平な職務を行うためのルールとして法律で定められています。
なぜ公務員は副業が禁止されているのか?
公務員の副業禁止は、主に以下の3つの理由によります。
- 職務専念義務があるため
公務員は国民全体の奉仕者として、職務に専念する義務があります。副業によって本来の業務に支障が出ることを防ぐため、副業は制限されています。 - 信用失墜行為の防止
公務員が特定の企業や個人と利益関係を持つと、公正な業務ができなくなる可能性があります。また、不適切な副業が発覚すれば、公務員全体の信用を損なうことになります。 - 利益相反の回避
副業によって、本来の公務と副業先の利益が対立する場面が生まれる可能性があります。たとえば、公務で得た情報を副業に活用するなど、不適切な行為が生じるリスクを防ぐためです。
公務員が可能な副業は?

公務員の副業は、法律で制限されています。ただし、すべての副業が禁止されているわけではありません。近年では規制緩和の動きもあり、副業が認められるケースが増えています。
許可なくできる副業
以下のような活動は、公務員でも許可なく行うことができます。
- 資産運用(株式・投資信託・仮想通貨)
金融資産を運用することは、副業には該当しません。ただし、インサイダー取引は禁止されています。 - 不動産投資(一定の範囲内)
5棟10室以下の規模での賃貸経営は、問題ありません。それ以上の規模になると「営利目的」とみなされ、許可が必要になります。 - 執筆・講演活動(単発)
書籍の執筆や講演活動は、副業ではなく「社会貢献活動」として認められることが多いです。ただし、継続的な報酬が発生する場合は許可が必要になります。
許可を得れば可能な副業
次のような活動は、勤務先の許可を得ることで可能になります。
- NPO法人や公益団体の活動
社会貢献活動として認められる場合があり、勤務先の判断で許可されることがあります。 - 家業の手伝い
家族経営の農業や小規模な商売を手伝うことは、許可が下りやすいです。ただし、収益の規模によっては制限されることもあります。
公務員が禁止されている副業
以下のような活動は、公務員として行うことができません。
- 会社を経営すること
代表取締役や個人事業主としての活動は禁止されています。 - アルバイト・パート勤務
飲食店や小売店でのアルバイトなどは、原則禁止です。 - 他企業での就業
一般企業の従業員として働くことも認められていません。
最近の規制緩和について
2025年現在、公務員の副業に関する規制緩和が進んでおり、一部自治体では営利目的の副業を認める動きがあります。特に大阪府では、公務員が営利目的で副業を行うことが正式に許可されています。また、2025年1月には石破茂首相が通常国会で「地方公務員の兼業・副業の弾力化」に言及しており、副業可能な範囲がさらに広がる可能性があります。
副業を考えている場合は、勤務先のルールを確認し、許可が必要かどうかを事前に確認しましょう。
公務員は勤務しながら社労士登録して開業できる?

公務員が社労士資格を取得することは可能ですが、公務員のまま社労士として業務を行うことは法律で制限されています。副業は禁止されており、開業登録をするには退職が必要です。しかし、資格を活かす方法はいくつかあります。ここでは、公務員が社労士資格を取得する際の制限と、活用方法について詳しく解説します。
公務員は社労士として開業できるのか?
公務員には副業禁止の規定があり、報酬を得る形で社労士業務を行うことはできません。社労士として活動するには、以下の登録方法があります。
| 登録種類 | 公務員の登録可否 |
|---|---|
| 開業登録 | ×(不可) |
| 勤務登録 | ×(不可) |
| その他登録 | ○(可能) |
公務員のままでできるのは「その他登録」のみであり、社労士業務を行うことはできません。
社労士資格を活かす方法
公務員のまま副業として社労士業務を行うことはできませんが、以下の方法で資格を活用することが可能です。
- 公務員の業務に活かす
社労士資格を取得することで、労務管理や社会保険関連の業務に強くなります。特に人事や年金業務に関わる部署では、専門性が評価されるでしょう。 - 退職後に社労士として開業する
退職後に開業登録をすれば、正式に社労士として独立できます。開業には営業力や経営の知識も求められるため、事前準備が重要です。 - 転職して社労士業務を行う
社労士事務所や企業の人事部門へ転職することで、資格を活かすことができます。公務員時代の知識や経験を活かしつつ、労務の専門家としてキャリアを築けます。
公務員は法律上、副業として社労士業務を行うことはできません。しかし、資格を活かして公務員としての仕事に役立てたり、退職後に社労士として独立する道もあります。自分のキャリアプランを考え、どのように資格を活用するかを計画的に検討しましょう。
公務員は社労士として副業できる?メリットと注意点

- 社労士登録に必要な実務経験
- 公務員が社労士を目指すメリットと注意点
- 公務員は社労士として副業できる?(まとめ)
社労士登録に必要な実務経験
社労士として活動するには、試験に合格した後、登録手続きを行う必要があります。その際、一定の実務経験が求められます。公務員としての経験が社労士登録に活かせる場合もあるため、詳しく解説します。
社労士登録に必要な実務経験とは?
社労士登録をするには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 労働社会保険に関する実務経験が2年以上あること
会社の人事・総務部門などで、労働保険や社会保険の手続きを担当していた場合、実務経験として認められます。 - 事務指定講習を修了すること
実務経験がない場合は、日本社労士連合会が実施する「事務指定講習」を受講し、修了することで登録が可能になります。
実務経験がない公務員はどうすればいい?
社労士登録に必要な実務経験がない場合は、「事務指定講習」を受けることで登録が可能です。講習は通信教育とスクーリングで構成され、約6か月で修了できます。試験合格後、すぐに実務経験を積む機会がない人は、この講習を利用するのが一般的です。
公務員が社労士を目指すメリットと注意点

公務員が社会保険労務士(社労士)の資格を取得することには多くのメリットがあります。しかし、一方で注意すべき点もあるため、慎重に検討することが大切です。
公務員が社労士を目指すメリット
- 専門知識の向上
社労士の勉強をすることで、労働法や社会保険制度の知識が深まり、公務員としての仕事にも役立ちます。特に、総務や労働関連の部署で働く人には大きなメリットがあります。 - 転職や独立の選択肢が広がる
社労士資格を持つことで、公務員を退職した後のキャリアの幅が広がります。例えば、社労士事務所や企業の人事部に転職することも可能です。また、独立して開業する道もあります。 - 収入アップの可能性
資格を持っていることで、転職や独立後に安定した収入を得やすくなります。特に、社労士として成功すれば高収入を目指すこともできます。
社労士を目指す際の注意点
- 試験の難易度が高い
社労士試験は合格率が10%未満の年もある難関試験です。公務員として働きながら合格を目指す場合、勉強時間の確保が大きな課題となります。計画的に学習を進めることが重要です。 - 開業にはリスクがある
退職して開業する場合、収入が安定するまで時間がかかることがあります。特に、人脈や営業力がないと、最初のうちは顧客を獲得するのが難しくなるでしょう。事前に十分な準備をすることが大切です。
公務員が社労士を目指すことには、多くのメリットがあります。知識を深めることで公務員の仕事に活かせるだけでなく、将来のキャリアの選択肢も広がります。ただし、副業ができない点や試験の難しさ、独立のリスクを理解した上で、計画的に準備を進めることが成功の鍵となるでしょう。
公務員は社労士として副業できる?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 公務員は原則として副業が禁止されている
- 副業禁止の理由は「職務専念義務」「信用失墜の防止」「利益相反の回避」
- 許可なくできる副業として「資産運用」「小規模な不動産投資」「単発の執筆・講演」がある
- 許可を得れば「NPO活動」「家業の手伝い」などは可能
- 公務員が社労士として副業することは法律で認められていない
- 社労士として活動するには「開業登録」または「勤務登録」が必要
- 公務員は「その他登録」は可能だが、業務は行えない
- 社労士資格を活かす方法として「公務で活用」「転職」「退職後の開業」がある
- 社労士資格を持つと、公務の労務管理や社会保険関連業務で専門性を発揮できる
- 退職後に社労士として開業するには、事前の準備が必要
- 転職先として社労士事務所や企業の人事部が考えられる
- 社労士登録には2年以上の実務経験または事務指定講習の修了が必要
- 近年、公務員の副業規制が一部緩和される傾向がある
- 2025年以降、一部の自治体では公務員の副業が認められる可能性がある
- 公務員が社労士資格を取得するなら、将来のキャリアプランを明確にしておくことが重要