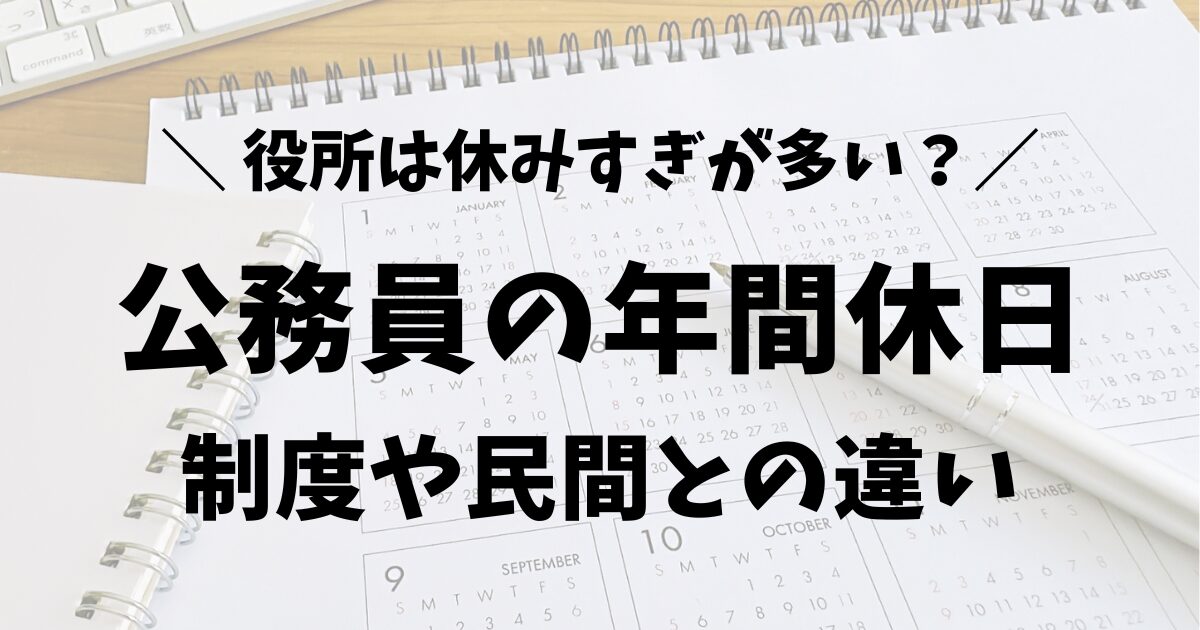公務員の年間休日はどれくらいあるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。最近では、公務員は休みすぎだという声や、公務員の有給取得状況にも注目が集まっています。
本記事では、2025年と2026年の年間休日の見通しや、制度の変化についても詳しく解説します。制度上は休日が充実していても、実際には部署によって休みにくい環境があることも事実です。
この記事では、公務員の年間休日の制度と実態をわかりやすく紹介し、今後の動きやポイントを丁寧にお伝えします。これから公務員を目指す方や、働き方を見直したい現職の方にも役立つ内容となっています。
- 公務員の年間休日の日数とその内訳
- 2025年・2026年の休日スケジュールの特徴
- 有給休暇の制度と取り方の注意点
- 部署による休みやすさ・休みにくさの違い
公務員の年間休日はどれくらい?制度と実態を解説

- 年間休日の基本制度
- 2025年の年間休日はどう変わる?
- 2026年の年間休日|予想と注目点
- 有給の取り方と注意点
- 公務員は休みすぎ?その真相とは
- 公務員と民間の年間休日を比較
年間休日の基本制度
公務員の年間休日は、民間よりも充実しているとよく言われます。実際、国家公務員や地方公務員の多くは年間でおよそ125日から130日の休日が確保されています。この数字は、土日祝日に加えて年末年始や夏季休暇などを含んだ合計です。
ここで、年間休日のおおまかな内訳を見てみましょう。
| 区分 | 目安の日数 | 内容 |
|---|---|---|
| 土日 | 約104日 | 毎週完全週休2日制 |
| 祝日 | 約15日 | 国の祝日が該当 |
| 年末年始 | 6日 | 12月29日~1月3日まで |
| 夏季休暇 | 3〜6日 | 自治体や省庁によって異なる |
これらに加えて、有給休暇や特別休暇(結婚、病気、育児など)も整備されているため、年間を通じて計画的に休める仕組みになっています。
なお、公務員の休日制度には法律的な裏付けもあります。たとえば、国家公務員は「国家公務員法」や「勤務時間法」により、地方公務員は「地方公務員法」や各自治体の条例でルールが決まっています。
法に守られた安定的な制度である点が、公務員の休日制度の大きな特長です。ただし、実際の取得状況は職種や部署によって差があるため注意しましょう。
2025年の年間休日はどう変わる?

2025年の公務員年間休日は、前年より1日多くなる見通しです。これは、カレンダー上で祝日と土日の重なりが少ないため、単純に休日が増える年となっているからです。
次の表に、2025年度の年間休日の内訳をまとめました。
| 区分 | 国家公務員 | 地方公務員 |
|---|---|---|
| 土日 | 104日 | 104日 |
| 祝日・振替休日 | 15日 | 15日 |
| 夏季休暇 | 3日 | 3日~6日 |
| 年末年始(土日祝除く) | 4日 | 4日 |
| 合計 | 126日 | 126~129日 |
特に注目すべき点は週休3日制の拡大です。2025年4月から、国家公務員で「選択制週休3日制」が本格導入される予定です。希望者が1日多く休めるようになりますが、1日の勤務時間はやや長くなります。
一方、地方公務員の中でも東京都や千葉県などでは、すでに試験的に導入が進められています。ただし、すべての部署が対象ではなく、現場では業務の偏りや不公平感を懸念する声もあります。
【ポイント】
- 2025年はカレンダーの並びがよく、休日が増える
- 週休3日制の導入により、働き方の幅が広がる
- 一部では導入への準備や調整が必要
2025年は公務員にとって「休みやすくなる年」と言えます。ただし、制度をうまく活用するには、職場の理解やスケジュール管理も欠かせません。
2026年の年間休日|予想と注目点

2026年の公務員年間休日は、前年と同じく国家公務員で126日、地方公務員で126~129日前後になると予想されます。大きな制度変更はありませんが、カレンダーの並びや祝日の配置がポイントになります。
注目すべきは、連休の取りやすさと週休3日制の広がりです。特に9月は「敬老の日」と「秋分の日」がうまく並ぶため、最大で9連休になる可能性があります。また、ゴールデンウィークも土日と祝日が連続して、長めの休みが期待されます。
以下は2026年の休日構成の予測です。
| 区分 | 日数(国家) | 日数(地方) |
|---|---|---|
| 土日 | 104日 | 104日 |
| 祝日 | 16日 | 16日 |
| 夏季休暇 | 3日 | 3日~6日 |
| 年末年始(土日祝除く) | 3日 | 3日 |
| 合計 | 126日 | 126~129日 |
【注目ポイント】
- カレンダー次第で大型連休が増える
- 週休3日制が浸透しはじめる
- 地方公務員の方が休みが多い傾向
2026年の休日は、うまくスケジュールを立てることで、より充実した私生活を送れるチャンスです。家族行事や旅行、資格取得など、早めに予定を立ててみましょう。
有給の取り方と注意点

公務員の有給休暇は、働き方の中でも重要な制度の一つです。基本的に国家・地方問わず毎年20日間の有給休暇が付与されます。初年度は勤務開始日によって、15日程度からスタートする場合もあります。
この有給休暇は、「年次休暇」とも呼ばれ、法律により最低でも年5日は取得しなければならない決まりになっています。実際には多くの職場で15日前後が消化されており、民間企業よりも取得率が高い傾向があります。
ただし、以下の点に注意する必要があります。
【注意したいポイント】
- 有給は最大40日まで保有可能
- 付与から2年で消滅する(使わなければ失効)
- 繁忙期や行事が重なる時期は取りにくい
- 職場の雰囲気によっては申請しづらい場合もある
例えば、夏季休暇や祝日と組み合わせれば10連休も実現可能です。一方で、急な病気や家庭の都合に備えて、数日はあえて残しておくという考え方もあります。
取得方法については、通常は事前申請制です。休む理由を細かく伝える必要はありませんが、上司やチームとの調整が円滑に進むよう、前もって相談するのが望ましいです。
有給休暇をしっかり活用するには計画性とバランスが大切です。仕事と私生活の両方を大事にするためにも、自分に合った使い方を見つけていきましょう。
公務員は休みすぎ?その真相とは

「公務員は休みすぎ」という意見がネットやSNSでよく見られますが、実際の働き方と比べると、このイメージはややズレています。制度としては公務員は休日が多く、年次休暇や特別休暇も整っています。ただし、必ずしも全員がそれをフルに使えているわけではありません。
この声が広がった背景には、次のような理由があります。
【休みすぎと感じられる要因】
- 平日に役所が閉まっている時間が多い
- 「担当者不在」が目立ち、休んでいる印象を与える
- 窓口での対応が少ない職種は見えにくく、誤解されやすい
実際、公務員の年次休暇取得率は国家公務員で約77%、地方公務員で約61%です。たしかに民間より少し高いですが、すべてを使い切る職員は多くありません。
また、休暇が多いからといって楽な仕事とは限りません。中には月100時間以上の残業がある部署も存在し、精神的にきついという声もあります。見た目と実態のギャップが「休みすぎ」というイメージにつながっていると考えられます。
公務員と民間の年間休日を比較
公務員は本当に民間より休みが多いのか。数字で比べると、その差ははっきり見えてきます。
【年間休日の比較表】
| 区分 | 年間休日数 | 有給付与日数 | 有給取得日数 |
|---|---|---|---|
| 国家公務員 | 約126日 | 20日 | 約16日 |
| 地方公務員 | 約129日 | 20日 | 約13〜15日 |
| 民間企業 | 約110〜115日 | 10〜20日 | 約11日 |
このように、公務員の年間休日は民間より10日以上多いです。さらに、最初から有給が20日つくため、取りやすさの面でも有利と言えます。
ただし、民間でも大企業や一部のホワイト企業では、公務員並みの休日数を用意している場合もあります。
休日数だけを見ると公務員が有利ですが、それが直接「楽な仕事」につながるとは限りません。公務員には突発的な対応や市民対応も多く、休日返上で働く職員もいます。
表面的な数字だけで判断するのではなく、それぞれの働き方の特徴を理解することが大切です。
公務員の年間休日を有効に活用する方法

- 休みやすい部署トップ3
- 休みにくい部署の現状と課題
- 公務員の年間休日を有効に活用する方法(まとめ)
休みやすい部署トップ3
公務員の中でも、部署によって休みの取りやすさはかなり違います。特に休みやすいとされる部署には、共通した特徴があります。
【休みやすい部署トップ3】
- 公民館などの出先機関
- 地域の出張所や包括支援センター
- 税務課の課税係(※繁忙期を除く)
これらの部署に共通しているのは、「突発的な仕事が少ない」「業務スケジュールが決まっている」「代わりの人が見つけやすい」といった点です。また、イベントがある時以外は定時で帰れることも多く、職場の雰囲気も穏やかな傾向にあります。
例えば、税務課では繁忙期は忙しくなりますが、それ以外の時期は休みをまとめて取りやすくなっています。公民館や出張所も比較的仕事量が安定していて、有給休暇も取りやすいです。
こうした職場では、有給消化率が高く、年15日以上取得している職員も少なくありません。
休みにくい部署の現状と課題

全ての公務員が気軽に休めるわけではありません。部署によっては、休みづらい環境にあるところもあります。
【休みにくい主な理由】
- 人手が足りない
- 仕事の量が多すぎる
- 急な対応が必要になることが多い
- 上司や同僚の目を気にする雰囲気がある
特に、福祉関係や児童相談、災害対応などの部署では、いつ何が起こるかわからないため、計画的に休みを取るのが難しくなります。警察や消防なども、交代勤務が多く、長期で休みを取るには工夫が必要です。
【改善への動き】
- 業務をデジタル化して効率を上げる
- 育休や有給を取りやすい制度づくり
- 職員の数を見直す取り組み
今後は、職員の働きやすさを重視した改革が進むと見られます。働く人の健康ややる気を守るためにも、こうした改善は欠かせません。
公務員の年間休日を有効に活用する方法(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 公務員の年間休日はおおよそ125〜130日とされている
- 土日祝日に加え、年末年始や夏季休暇も含まれている
- 年間休日数は民間企業より10日以上多い場合が多い
- 国家公務員と地方公務員で多少の差がある
- 各種休暇制度は法律や条例に基づいて整備されている
- 2025年は祝日と土日の重なりが少なく休日が増える見通し
- 2025年から国家公務員で選択制週休3日制が本格導入される
- 地方自治体でも週休3日制を試験導入する動きがある
- 2026年はカレンダー上の祝日配置により大型連休が期待される
- 有給休暇は年20日付与され、最大40日まで保有可能
- 有給は2年で失効するため計画的な取得が求められる
- 実際の有給取得率は国家約77%、地方約61%である
- 公務員は休みすぎと言われるが、実態は部署により差がある
- 休みやすい部署は公民館・出張所・税務課(繁忙期除く)など
- 休みにくい部署では人手不足や急な対応が休暇取得を妨げている