公務員として勤務する中で、体調不良により休暇を取得する際、「診断書はいつから必要なのだろうか」と疑問に感じた経験はありませんか。特に、公務員の病気休暇で診断書が不要となる条件については、多くの方が具体的な日数や手続きを正確に把握したいと考えているテーマです。
例えば、公務員が病気休暇を1週間連続で取得する場合や、定期的な通院のために休むケースでは、どのような書類を準備し、どのように申請すればよいのでしょうか。また、病気休暇を取得することによる公務員のキャリアへのデメリットや、周囲への影響に関する不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
この記事では、そのような疑問や不安を解消するため、公務員の病気休暇における診断書の要否について、具体的な日数や法的根拠、ケース別の申請フローから、取得に伴う注意点やリスクまで、網羅的かつ詳細に解説していきます。
- 診断書なしで病気休暇が取れる具体的な日数や条件
- 風邪や通院などケース別の病気休暇申請フロー
- 診断書が必要な場合の手続きと注意点
- 病気休暇取得に伴う給与や評価への影響
公務員の病気休暇は診断書なしで何日まで休める?

- 診断書不要の条件と法的根拠
- 診断書は何日から必要?日数の目安
- 病気休暇を1週間取得する際の流れ
- 通院で病気休暇を使う際の注意点
診断書不要の条件と法的根拠
公務員が病気休暇を取得する際、必ずしも医師の診断書が求められるわけではありません。結論から言うと、原則として連続する勤務日の日数が7日以内の短期的な病気休暇であれば、診断書の提出は不要とされています。
制度の背景と法的根拠
この運用の背景には、明確な法的根拠が存在します。国家公務員の場合は「人事院規則15-14(職員の勤務時間、休日及び休暇)」および、その具体的な運用方法を示した通知が根拠となります。地方公務員の場合も、多くは国の制度に準じた内容の条例や規則を各自治体で定めています。
これらの規定は、職員が軽微な体調不良から回復するために、過度な負担なく療養に専念できるようにする、という福利厚生の観点から設けられています。
数日の静養で回復が見込める症状のたびに、医療機関を受診し診断書を取得するのは、職員にとっても医療機関にとっても非効率です。そのため、手続きを簡素化し、職員が休みやすい環境を整える目的があるのです。
注意すべき自治体ごとの違い
ただし、「7日以内」という基準は全国的な標準ではあるものの、一部の自治体では「連続3日まで」「年間10日まで」といった独自の基準を設けている場合もあります。
したがって、ご自身の勤務先の人事・服務規程を一度は確認しておくことが、誤解やトラブルを避ける上で非常に大切になります。
診断書は何日から必要?日数の目安

診断書が不要なケースがある一方で、客観的な療養の必要性を示すために、提出が必須となる基準も明確に定められています。これらの基準を正しく理解しておくことが、スムーズな手続きの鍵となります。
連続8日以上の休暇
一般的に、診断書が必要になる最も代表的なケースは「連続して8日以上」病気休暇を取得する場合です。この「連続」という考え方には注意が必要です。これは単に勤務日だけを数えるのではなく、土日や祝日といった非勤務日(週休日や休日)も含めてカウントするのが原則です。
例えば、金曜日から翌週の月曜日まで4勤務日休んだ場合、間の土日を含めると「連続6日間」となります。もし、水曜日から翌週の水曜日まで休む場合は、間に土日を2回挟むため「連続8日間」となり、診断書の提出が必要になるのです。長期の療養に入る際は、この日数の数え方を念頭に置いておく必要があります。
過去の取得実績による要件
もう一つの重要な基準が、過去の取得実績に基づくものです。具体的には「過去1か月以内に通算して5日以上」の病気休暇を取得している場合にも、診断書の提出を求められることが一般的です。
これは、休暇が頻回になることで、職場として職員の健康状態をより正確に把握し、適切な労務管理を行う必要性が高まるためです。断続的であっても、体調不良が続いている状況を客観的な医学的知見から確認する目的があります。
| 取得日数・条件 | 証明書類の要否 | 備考 |
|---|---|---|
| 7日以内 | 原則不要(医療機関の領収書等で可) | 自治体ごとの規定を必ず確認 |
| 8日以上連続 | 医師の診断書が必要 | 土日や祝日も含めた連続日数で計算 |
| 1か月に通算5日以上 | 医師の診断書が必要 | 休暇が頻回になる場合に適用 |
| 感染症(インフルエンザ等) | 診断書または治癒証明書 | 復職時に求められる場合がある |
これらの日数や条件はあくまで全国的な標準運用です。ご自身の勤務先の規則によって細かな違いが存在する可能性があるため、不明な点があれば、必ず人事担当部署へ事前に確認することをお勧めします。
病気休暇を1週間取得する際の流れ
インフルエンザへの罹患や怪我など、1週間程度の療養が必要となるケースも少なくありません。公務員が連続して7日間の病気休暇を取得する場合、手続きはどのように進めるのでしょうか。
手続きの流れ
連続7日間の休暇の場合、原則として診断書の提出が必要とされるケースが多いですが、職場によっては6日以下の場合は不要とされる場合もあります。申請時に診断書の要否を必ず確認してください。
休暇中は療養に専念し、回復状況に応じて復帰日を上司に報告します。職場に復帰した際は、不在中の業務をカバーしてくれた上司や同僚への感謝の言葉を伝えることを忘れないようにしましょう。こうした配慮が、良好な職場関係を維持する上で役立ちます。
通院で病気休暇を使う際の注意点

定期的な診断や治療のために、勤務時間の一部を使って休暇を取得することも、もちろん可能です。この場合、1日単位だけでなく「時間単位」や「半日単位」での病気休暇が認められています。これにより、治療と仕事の両立がしやすくなっています。
「勤務時間内の必然性」が鍵
ただし、時間単位での取得には「勤務時間内に通院する必然性」が求められるという重要な注意点があります。これは、誰でも自由に時間休が取れるわけではなく、合理的な理由が必要であることを意味します。
必然性が認められやすい例としては、以下のようなケースが挙げられます。
- 治療を受けられるのが特定の専門医に限られており、その医師の診察が特定の曜日・時間帯しかない場合。
- 遠隔地の医療機関でしか受けられない高度な治療である場合。
- 検査や処置の都合上、どうしても平日の日中の時間が必要となる場合。
逆に、近所のクリニックで、自身の都合で予約時間を変更できるような場合は、業務時間外での受診を求められる可能性もあります。
申請・証明の方法
申請書には「〇〇病院にて定期検査のため」といった具体的な理由と、取得したい日時(例:〇月〇日 14:00~16:00)を正確に記入します。
この際、医師に診断書を依頼する場合は、こうした時間単位での通院の必要性や、定期的な治療が求められる旨を具体的に記載してもらうと、職場への説明が円滑に進み、承認が得やすくなります。
公務員の病気休暇|診断書なしで休めない場合
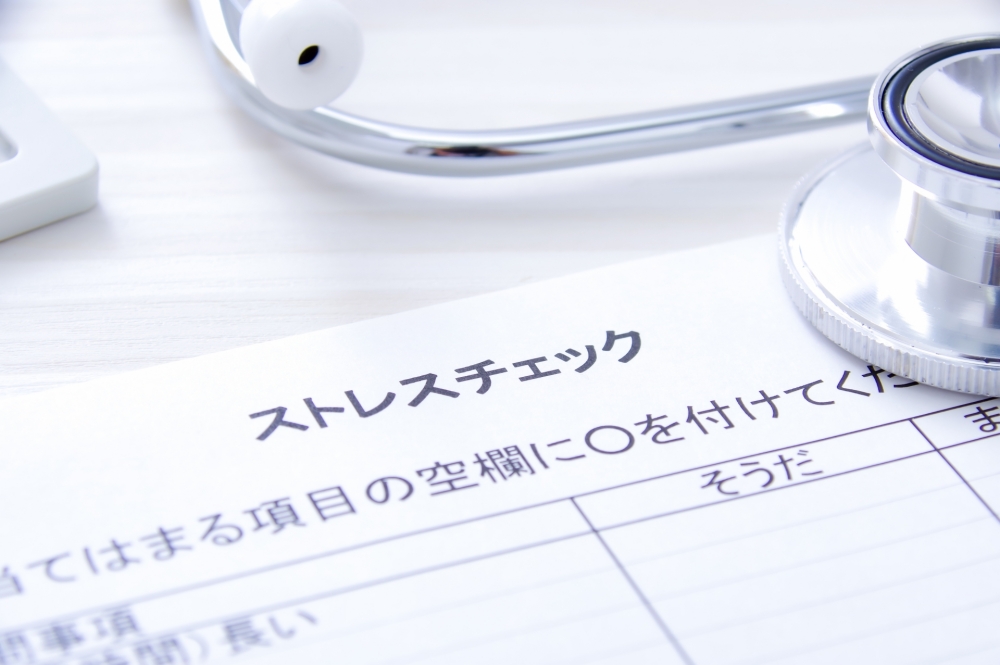
- 診断書の書き方と医師への依頼法
- 病気休暇と年次有給休暇の違いとは
- 公務員の病気休暇のその後はどうなりますか?
- 病気休暇から休職へ移行する条件
- 病気休暇取得のデメリットとリスク
- 公務員の病気休暇は診断書なしで何日まで休める?(まとめ)
診断書の書き方と医師への依頼法
病気休暇の取得日数が8日以上に及ぶ場合や、通算で規定日数を超えるなど、診断書の提出が必要になった際は、医師に適切な内容を記載してもらい、職場へ提出する必要があります。
1. 指定様式の確認
まず最初に行うべきは、所属する自治体や部署で診断書の指定様式があるかどうかの確認です。人事担当部署に問い合わせれば、所定のフォーマットがあるか教えてくれます。もし指定様式があれば、それを医療機関に持参して作成を依頼します。指定がなければ、医療機関が通常発行する様式で問題ありません。
2. 診断書の必須記載項目
診断書には、主に以下の項目が漏れなく記載されていることが求められます。
- 患者氏名・生年月日
休暇を取得する職員本人であることの証明。 - 病名
具体的な傷病名(例:インフルエンザA型、腰椎椎間板ヘルニアなど)。 - 療養を要する期間
「〇年〇月〇日から〇週間(または〇月〇日まで)の安静加療を要する」といった具体的な期間。この期間が休暇期間の根拠となります。 - 診断年月日
医師が診察を行った日付。 - 医療機関の名称・所在地
診断を行った医療機関の情報。 - 医師の氏名・押印
診断書作成者の証明。
3. 医師への依頼時のマナーと費用
医師に依頼する際は、「公務員の病気休暇を取得するために必要です」と用途を明確に伝えることが大切です。診察時に口頭で伝えるか、受付で事前に申し出ておくとスムーズです。
なお、診断書の発行は健康保険の適用外であるため、全額自己負担となります。費用は医療機関によって異なりますが、一般的には3,000円から5,000円程度が相場です。発行には数日かかる場合もあるため、提出期限から逆算して余裕を持って依頼しましょう。
病気休暇と年次有給休暇の違いとは

病気休暇と年次有給休暇は、どちらも給与が支払われる休暇ですが、その法的な性質や目的は全く異なります。この違いを理解しておくことは、適切な休暇取得のために不可欠です。
年次有給休暇は、労働基準法で定められた「労働者の権利」です。一定期間勤務した労働者に対して自動的に付与され、取得理由を問われることなく、労働者が心身のリフレッシュなどを目的に自由に利用できます。
一方、病気休暇は、各職場(国や自治体)が福利厚生の一環として設けている「特別休暇」に位置づけられます。そのため、取得には「職員本人の負傷または疾病による療養」という明確な目的が必要となり、理由を問わず使えるわけではありません。
| 項目 | 病気休暇 | 年次有給休暇 |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 人事院規則・各自治体の条例等 | 労働基準法 |
| 目的 | 傷病の療養 | 理由を問わない(心身のリフレッシュ等) |
| 位置づけ | 特別休暇(福利厚生) | 労働者の権利 |
| 取得要件 | 療養の必要性の証明(診断書等) | 原則として不要 |
体調不良の際は、まず療養を目的とする病気休暇を取得するのが基本的な考え方です。診断書が提出できない場合や、軽微な不調で療養とまでは言えない場合に、本人の判断で年次有給休暇を利用する、という使い分けが一般的です。
公務員の病気休暇のその後はどうなりますか?
病気休暇を取得し、無事に体調が回復した後の職場復帰には、本人と職場の双方が安心して業務を再開するための、いくつかの段階的な手続きが伴います。
1. 復帰可能の診断書提出
療養期間が終わり復帰の目処が立ったら、まずは主治医に診察を受け、「就業可能」「通常勤務に支障なし」といった内容を記載した診断書を作成してもらいます。これを職場の上司や人事担当部署へ提出することが、復帰手続きの第一歩となります。
2. 産業医等との面談
特に長期の休暇であった場合や、精神的な不調が理由であった場合には、復帰前に職場の産業医や保健師との面談が設定されることが多くあります。
この面談は、職員の健康状態を客観的に評価し、復帰後の業務内容や必要な配慮について検討するために行われます。本人の状態を正しく伝え、無理のない復帰プランを一緒に考える良い機会となります。
3. 試し出勤(リハビリ出勤)
職場によっては、本格的な復帰の前に、心身の状態を業務に慣らしていくための「試し出勤(リハビリ出勤)」制度を利用できる場合があります。
これは、短時間勤務から始め、徐々に勤務時間を延ばしていくといった形で、段階的に職場復帰を目指すものです。これにより、復帰直後の負担を軽減し、再発を防ぐ効果が期待されます。
復帰直後は、たとえ体調が万全に感じられても無理は禁物です。自分の体調としっかり向き合い、上司や同僚とコミュニケーションを取りながら、徐々にペースを取り戻していくことが大切です。
病気休暇から休職へ移行する条件
病気休暇は、職員が療養に専念するための重要な制度ですが、取得できる期間には上限があります。原則として連続90日までと定められていますが、がん・脳卒中・心臓疾患や特定疾患等は180日、結核性疾病は1年を超えない範囲、公務上の負傷又は疾病の場合は必要と認められる期間など、特定の疾病等については例外があります。
もし療養が長引き、原則の90日(例外を含む上限)を超えても復帰が難しい場合は、「病気休職」という別の制度に移行することになります。
休職への移行は自動的に行われるものではなく、改めて医師の診断書に基づき、任命権者(知事や市町村長、各省の大臣など)の判断と承認が必要です。
病気休暇と休職の主な違い
病気休暇と病気休職は、給与や身分保障の面で大きく異なります。この違いを理解しておくことは、長期療養の際の生活設計において非常に重要です。
| 項目 | 病気休暇(原則最大90日、特定疾病等は例外あり) | 病気休職(最大3年) |
|---|---|---|
| 給与 | 全額支給 | 最初の1年:8割支給、以降:無給(共済組合から傷病手当金が支給される場合あり) |
| 身分保障 | 職員としての身分を保有 | 職員としての身分を保有 |
| 期間 | 原則最大90日間(特定疾病等は例外あり) | 最大3年間 |
| 復帰 | 比較的容易 | 復帰審査が必要な場合あり |
休職期間中は給与が減額または無給となるため、経済的な負担が大きくなります。ただし、多くの場合は加入している共済組合から「傷病手当金」が支給されるため、生活を支えることは可能です。
休職期間は最長で3年間と定められており、この期間内に復帰できない場合は、分限免職(退職)に至る可能性もあります。
病気休暇取得のデメリットとリスク

病気休暇は職員に認められた正当な権利ですが、その取得がキャリアや職場環境に全く影響しないわけではありません。考えられるデメリットやリスクについても客観的に理解し、適切な対応を心がけることが大切です。
人事評価・昇進への影響
数日程度の短期的な病気休暇であれば、人事評価やその後の昇進に直接的な悪影響が出ることはほとんどないと考えてよいでしょう。
しかし、数か月にわたる長期の休暇や、短期間でも繰り返し取得するような場合は、注意が必要です。評価期間中の勤務実績が少なくなるため、成果や能力の評価が低くなる可能性があります。
また、重要なプロジェクトや責任あるポストから一時的に外れることで、キャリアパスに遅れが生じることも考えられます。特に管理職を目指す上では、健康管理能力も評価の一つと見なされる傾向があります。
職場関係への影響と配慮
自分が休むことで、その業務は他の誰かが分担して担うことになります。お互い様という文化が根付いている職場がほとんどですが、長期化・頻回化すれば、同僚に過度な負担をかけ、不満やストレスの原因となり得ます。
休暇を取得する際は、丁寧な引き継ぎと感謝の気持ちを伝えること、そして復帰後は、不在中の業務をカバーしてくれた同僚への配慮を忘れないことが、良好な職場関係を維持する上で不可欠です。
療養中の行動に関するリスク
病気休暇はあくまで「療養」を目的としています。その期間中に、旅行やレジャーを楽しむ様子をSNSに投稿するなど、療養の事実に疑念を抱かせるような行動は厳に慎むべきです。万が一、虚偽の申請が発覚した場合は、懲戒処分の対象となる可能性もあります。
公務員の病気休暇は診断書なしで何日まで休める?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 7日以内の短期的な病気休暇は原則として診断書が不要
- 診断書なしで休める具体的な日数は勤務先の条例や規則で定められている
- 全国の標準では連続8日以上の休暇から診断書の提出が必須となる
- 過去1か月以内に通算5日以上休んだ場合も診断書を求められることがある
- 連続日数の計算には土日や祝日などの非勤務日も含まれる点に注意
- 軽症で休む際も始業前の迅速な電話連絡と上司への報告が基本マナー
- 1週間程度の病休であれば給与や賞与(ボーナス)への影響はほぼない
- 通院目的で時間単位の休暇を取る際は勤務時間内に通院する必然性が問われる
- 診断書が必要な場合はまず職場の指定様式の有無を確認することが第一歩
- 医師には病気休暇取得の用途を伝え必要な期間を明記してもらう
- 病気休暇は療養を目的とする「特別休暇」であり「年次有給休暇」とは性質が異なる
- 療養が90日を超えると給与が減額される「病気休職」へ移行する
- 長期または頻回の病気休暇は人事評価やキャリアに影響をおよぼす可能性がある
- 休暇取得時は周囲の同僚への業務負担に配慮し感謝の気持ちを伝えることが大切
- 制度の内容で不明な点があれば必ず勤務先の人事担当部署に確認する


-12.jpg)







