会計年度任用職員として働く中で、「この仕事を続けても将来性はあるのだろうか」「いっそ、やめたほうがいいのでは?」と悩んでいませんか。会計年度任用職員は誰でもなれるというイメージは、実は大きな勘違いかもしれません。
実際には、会計年度任用職員として働くデメリットは多く、正規職員との待遇差から馬鹿にされると感じてしまったり、雇用の不安定さに不安を抱えたりする方は少なくありません。
この記事では、会計年度任用職員という働き方に疑問を感じているあなたのために、客観的な情報に基づき、仕事を続けるべきか辞めるべきかの判断材料を詳しく解説します。後悔のない選択をするための一助となれば幸いです。
- 会計年度任用職員として働く具体的なデメリット
- 雇用の安定性や将来性に関するリアルな実態
- 仕事を続けるか辞めるかの客観的な判断基準
- 後悔しないために今からできること
会計年度任用職員はやめたほうがいい?

- そもそも会計年度任用職員とは?制度の概要
- 会計年度任用職員は「誰でもなれる」という勘違いと採用の現実
- 会計年度任用職員として働く「待遇面」のデメリットとは?
- なぜ会計年度任用職員は「馬鹿にされる」と感じてしまうのか?
- 「安定」は嘘?会計年度任用職員が抱える「雇い止め」のリスク
- 会計年度任用職員を10年以上続けても市場価値は上がらないのか?
そもそも会計年度任用職員とは?制度の概要
会計年度任用職員とは、地方自治体などで1会計年度(原則4月1日から翌年3月31日まで)を任期として任用される非正規の公務員を指します。この制度は、2020年度から本格的に導入されました。
導入の背景には、それまで自治体ごとに異なっていた臨時・非常勤職員の採用基準や待遇を統一し、雇用の透明性と公平性を高める目的があります。地方公務員法上の一般職に位置づけられていますが、正規職員と異なり、1年ごとの契約更新が基本となる有期雇用である点が最大の特徴です。
そのため、正規職員と同様の業務を担う場合でも、雇用形態や待遇面で明確な違いが存在します。
会計年度任用職員は「誰でもなれる」という勘違いと採用の現実
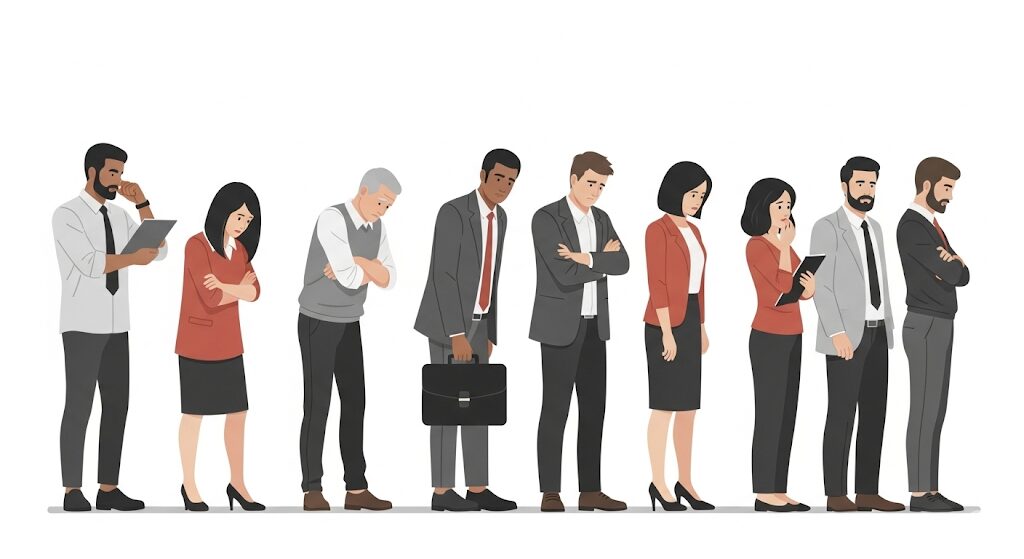
「会計年度任用職員は誰でもなれる」というイメージが一部で広がっていますが、これは大きな誤解と言えます。確かに、多くの職種で年齢や学歴を問わず、正規の公務員試験のような難関の筆記試験も課されないため、応募のハードルは低いように見えます。
しかし、実際には応募後に厳正な選考が行われます。採用プロセスは、一般的に「書類選考」と「面接選考」の二段階です。書類選考では履歴書や職務経歴から適性が判断され、面接では志望動機やコミュニケーション能力などが評価されます。
人気の自治体や一般事務職などでは応募が殺到し、採用倍率が5倍から10倍を超えることも珍しくありません。したがって、応募すれば必ず採用されるわけではなく、しっかりとした準備と対策が求められるのが現実です。
会計年度任用職員として働く「待遇面」のデメリットとは?

会計年度任用職員として働く上で、待遇面でのデメリットは避けて通れない課題です。結論から言うと、給与、期末手当(ボーナス)、昇給、退職金の全てにおいて、正規職員との間に大きな格差が存在します。
なぜなら、制度上あくまで非正規雇用としての位置づけであり、人件費を抑制する目的も含まれているからです。
| 項目 | 会計年度任用職員の実態 | 正規職員との比較 |
|---|---|---|
| 給与 | 平均年収200万円未満が多数派。月給16〜17万円程度が一般的。 | 年功序列で昇給が見込め、安定した収入がある。 |
| 期末手当 | 2025年の基準は年間4.6か月分(期末手当+勤勉手当)だが、実際の支給額は自治体や勤務形態によって異なる。 | 年間4.6か月分前後が安定して支給される。 |
| 昇給 | 制度がないか、あっても数百円程度の微増にとどまるケースがほとんど。 | 毎年定期的に昇給する仕組みが整っている。 |
| 退職金 | フルタイムで一定期間勤務しないと支給されない。パートは対象外。 | 勤続年数に応じた退職金が保障されている。 |
生活に直結する金銭面での待遇は決して良いとは言えず、一人暮らしや家計を支えるには厳しい水準であることが大きなデメリットと考えられます。
なぜ会計年度任用職員は「馬鹿にされる」と感じてしまうのか?

会計年度任用職員の方から「職場で馬鹿にされる」「見下されている」といった声が聞かれるのは、制度上の曖昧な立場と、正規職員との間に存在する明確な壁が原因と考えられます。
その理由は、1年ごとの契約更新という立場から「一時的な存在」「入れ替え可能な人材」と見なされやすく、重要な情報共有や意思決定の場から排除されることがあるためです。
また、本来の能力に関わらず、責任の軽い補助的な業務や雑用ばかりを任されることで、「軽く扱われている」という疎外感を抱くことにもつながります。
実際に「臨時の人だから」という言葉をかけられたり、業務に必要な権限を与えられなかったりするケースも報告されています。このような経験が積み重なると、自身の努力が正当に評価されていないと感じ、自己肯定感の低下を招いてしまうのです。
「安定」は嘘?会計年度任用職員が抱える「雇い止め」のリスク

「公務員だから安定している」というイメージは、会計年度任用職員には当てはまらないのが現実です。最大の理由は、1年ごとの有期雇用契約であり、毎年「雇い止め」のリスクにさらされるためです。
勤務成績に問題がなくても、自治体の方針や予算の都合、あるいは「公募」という形式的な選考によって、契約が更新されない可能性があります。
特に多くの自治体では、2回もしくは4回の更新上限を設けた後、再度公募にかけるルールを採用していましたが、2024年以降、国や一部自治体でこの上限を撤廃する動きも広がっています。ただし、すべての自治体で撤廃されたわけではありません。
これは、現職者であっても新規応募者と同じ土俵で選考を受け直さなければならないことを意味し、継続雇用を保証するものではありません。
実際に、十分な勤務実績があるにもかかわらず、説明もなく雇い止めになった事例も各地で報告されています。労働契約法上の「無期転換ルール」も適用されないため、法的な保護が弱い点も、この働き方の不安定さを助長していると言えるでしょう。
会計年度任用職員を10年以上続けても市場価値は上がらないのか?

残念ながら、会計年度任用職員として長期間勤務しても、民間企業で評価されるような市場価値は上がりにくいと考えられます。その背景には、業務内容の特性とキャリアパスの欠如があります。
会計年度任用職員の業務は、多くの場合、正規職員の補助的な役割や定型的な事務作業が中心です。そのため、高度な専門性や、転職市場でアピールできるような実績を積む機会が限られてしまいます。
また、正規職員のような体系的な研修制度や昇進の道が用意されていないため、10年以上働いても役職や責任範囲が大きく変わらないケースがほとんどです。
このような環境では、個人のスキルアップが難しく、いざ転職を考えた際に、自身の経験をどう評価してもらえばよいか悩むことになります。ただし、保育士や看護師など、資格が活かせる専門職の場合は、実務経験として評価されることもあります。
会計年度任用職員をやめたほうがいいか判断する前に知るべきこと

- 会計年度任用職員は何歳まで?更新上限と年齢のリアルな壁
- 転職するなら?公務員経験を活かす方法
- 会計年度任用職員はやめたほうがいい?後悔しないための判断基準
- 会計年度任用職員はやめたほうがいい(まとめ)
会計年度任用職員は何歳まで?更新上限と年齢のリアルな壁

会計年度任用職員として働く上で、年齢に関する不安を抱く方も多いですが、法律上の明確な年齢制限はありません。地方公務員法では定年制が適用されないため、募集要項でも「年齢不問」とされていることが一般的です。
しかし、自治体によっては内部規定で「65歳まで」といった実質的な上限を設けている場合があります。また、法律上の制限がないからといって、何歳までも安泰というわけではありません。
更新時に問われる年齢の壁
契約更新の際には、業務遂行能力が評価されます。年齢を重ねることで体力や健康面に不安があると判断されれば、更新が見送られる可能性も出てきます。
再応募のプレッシャー
多くの自治体では数年ごとに公募が行われます。その際は新規応募者との競争になるため、年齢が不利に働く可能性は否定できません。
2024年以降、国の方針で更新回数の上限を撤廃する動きが広がっていますが、依然として毎年の契約更新という不安定な立場に変わりはないのが現実です。
転職するなら?公務員経験を活かす方法

会計年度任用職員からの転職は不利だと考えられがちですが、経験の活かし方次第で可能性は広がります。もし転職を決意した場合、公務員経験を強みとしてアピールすることが鍵となります。
まず、キャリアの棚卸しを行い、これまでの業務内容を具体的に整理することが必要です。例えば、「どのような書類を作成し、業務効率をどう改善したか」「窓口業務でどのように市民対応を行ったか」など、具体的なエピソードをまとめておくと良いでしょう。
次に、民間企業でも評価されるポータブルスキルを強調します。公務の現場で培われた正確な事務処理能力、法令遵守の意識、多様な人と接するコミュニケーション能力や調整力は、多くの企業で求められる能力です。
これらのスキルを具体的な経験と結びつけてアピールできれば、転職活動を有利に進めることができます。
会計年度任用職員はやめたほうがいい?後悔しないための判断基準
会計年度任用職員をやめたほうがいいかどうかは、個人の価値観やライフプランによって結論が異なります。後悔しない選択をするためには、客観的な視点で自身の状況を整理することが求められます。
最初に、現在の仕事に対する不満(待遇、人間関係、将来性など)と、続けることのメリット(ワークライフバランス、安定した勤務時間など)を書き出して比較検討します。
| 項目 | 続けるメリット | 続けるデメリット(辞めたい理由) |
| 雇用 | 公的機関での勤務経験が積める | 1年ごとの契約更新で常に雇用の不安がある |
| 給与 | 毎月決まった収入が得られる | 低賃金で昇給もほぼなく、生活が厳しい |
| キャリア | 事務処理能力などが身につく | 専門性が身につきにくく、市場価値が上がらない |
| 働き方 | ワークライフバランスを保ちやすい | 責任ある仕事が少なく、やりがいを感じにくい |
その上で、健康状態に問題はないか、将来的にどのようなキャリアを築きたいのかを考え合わせます。もし心身に不調をきたしていたり、キャリアアップへの強い意志があったりするならば、退職も有力な選択肢となるでしょう。
会計年度任用職員はやめたほうがいい(まとめ)
この記事では、会計年度任用職員をやめたほうがいいか悩んでいる方へ、客観的な判断材料を提供してきました。最終的な決断を下すために、これまでの重要なポイントを以下にまとめます。
- 会計年度任用職員は1年契約の非正規公務員である
- 「誰でもなれる」は誤解で実際には書類選考や面接がある
- 給与水準は低く年収200万円未満が多数派を占める
- 昇給や退職金は正規職員と比べて大きな格差が存在する
- 「公務員だから安定」というイメージはこの職には当てはまらない
- 1年ごとの契約更新で常に雇い止めのリスクを抱えている
- 専門スキルが身につきにくく市場価値が上がりにくいのが現実
- 正規職員との待遇や立場の違いから疎外感を感じやすい
- 法律上の年齢制限はないが自治体独自の上限が設けられている場合がある
- 更新上限回数は撤廃傾向にあるが再応募のプレッシャーは残る
- 辞めるかどうかの判断は自身の優先順位を明確にすることが鍵となる
- 健康に支障が出ている場合は退職を真剣に検討すべきである
- 続ける場合はスキルアップなど主体的な行動で現状を変える努力が大切
- 公務員としての経験も整理すれば転職活動でアピールできる
- 後悔しない選択のためにメリットとデメリットを正しく理解し判断する










