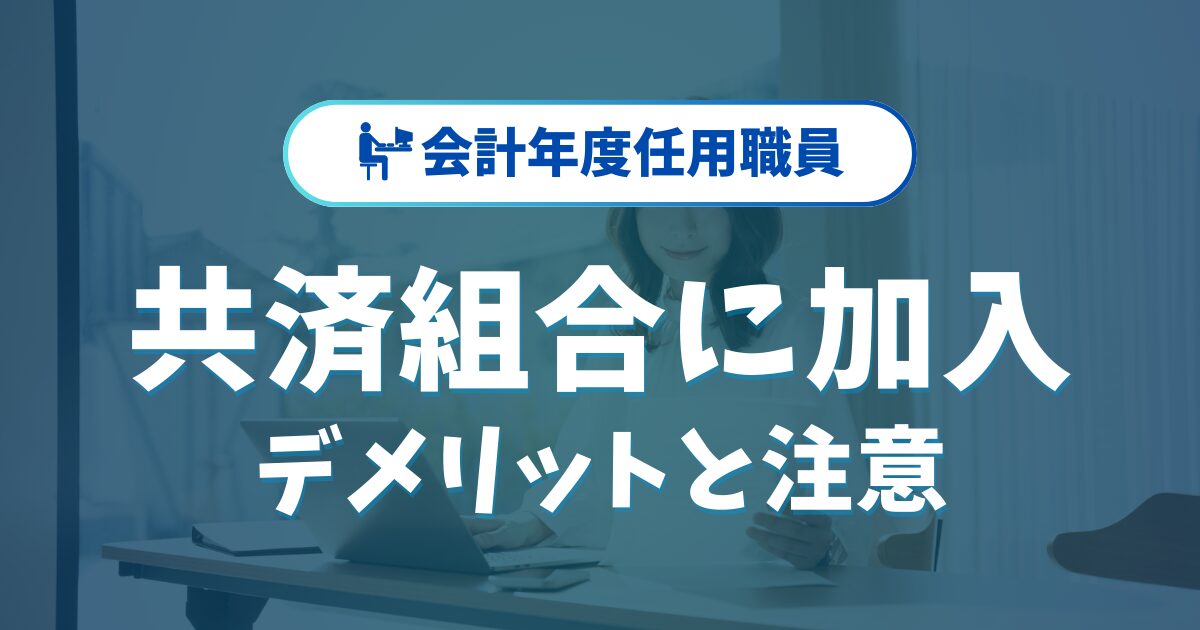会計年度任用職員として働いている方や、これから働く予定の方の中には、共済組合に加入することで本当に自分にとってプラスになるのか気になっている方も多いのではないでしょうか。
特に「会計年度任用職員が共済組合に加入するデメリット」と検索している方は、加入後にどのような影響があるのか、慎重に判断したいはずです。
この記事では、共済組合に加入する際の加入条件をわかりやすく解説しつつ、実際にどのようなメリットとデメリットがあるのかを具体的にご紹介します。
また、退職後も保険を続けたい場合に必要となる任意継続の手続きと注意点についても触れていきます。働き方やライフプランによって損得が分かれる部分ですので、しっかりと理解して自分に合った選択をしていきましょう。
- 共済組合に加入するための条件が分かる
- メリットとデメリットの具体的な違いが理解できる
- 任意継続制度の内容と注意点が分かる
- 自分の働き方に共済組合が合うか判断できる
【会計年度任用職員】共済組合のデメリットはある?

- 共済組合の加入条件をわかりやすく解説
- 共済組合のメリット・デメリットとは?
- 会計年度任用職員の保険証の何が変わる?切り替えのポイント
共済組合の加入条件をわかりやすく解説
会計年度任用職員が共済組合に加入するためには、一定の条件を満たす必要があります。特に、フルタイムとパートタイムで基準が異なるため、それぞれの条件を詳しく説明します。
フルタイム職員の加入条件
フルタイムの会計年度任用職員は、原則として全員が共済組合に加入します。これは、勤務時間や雇用期間が常勤職員と同じであるため、健康保険や厚生年金の適用対象になるためです。
【加入の主な基準】
- 週の労働時間が常勤職員と同じ(おおむね38時間以上)
- 採用当初から勤務期間12月以下で2カ月を超えて使用されることが見込まれる者
この条件を満たすと、自動的に共済組合に加入となり、健康保険証が発行されます。
パートタイム職員の加入条件
パートタイム職員は、一定の条件を満たせば共済組合に加入できます。
【加入できる基準】
- 週の労働時間が常勤職員の3/4以上
- 週の労働時間が20時間以上
- 月額給与が8.8万円以上
- 雇用期間が2カ月以上見込まれる
- 学生でない
これらの条件を満たすと、健康保険や厚生年金に加入でき、退職後の年金受給額も増える可能性があります。ただし、給与から保険料が控除されるため、手取り額が減る点には注意が必要です。
加入の手続き
共済組合に加入するには、勤務先を通じて手続きを行います。
【必要な書類の例】
- 組合員資格取得届
- 被扶養者がいる場合は「被扶養者申告書」
- マイナンバー確認書類
この書類を提出し、審査が完了すると、共済組合の健康保険証が発行されます。
加入条件を満たさない場合
加入条件を満たさない職員は、国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。そのため、勤務時間が短い人は、自身のライフプランを考えた上で、どの保険制度が最適かを検討することが大切です。
共済組合のメリット・デメリットとは?

共済組合に加入することで、会計年度任用職員はさまざまな恩恵を受けることができます。しかし、すべての人にとって必ずしもメリットばかりではありません。ここでは、加入することで得られるメリットと、注意すべきデメリットについて解説します。
共済組合のメリット
共済組合には、一般的な社会保険と比べて以下のようなメリットがあります。
- 手厚い医療保障
- 医療費の自己負担額が3割で済む
- 付加給付制度があり、一定額を超えた医療費は払い戻される
- 年金の充実
- 厚生年金に加入できるため、老後の年金受給額が増える
- 障害年金や遺族年金の保障も手厚い
- 福祉事業の利用
- 健康診断の補助やインフルエンザ予防接種の助成が受けられる
- 保養施設の利用補助などがあり、福利厚生が充実
- 休業給付の支給
- 病気やケガで働けなくなった場合、一定期間の給与補償が受けられる
- 産前産後休業や育児休業中も手当が支給される
共済組合のデメリット
一方で、共済組合に加入することで次のようなデメリットもあります。
- 掛金の負担が発生する
- 毎月の給与から健康保険料や年金保険料が引かれるため、手取り額が減る
- 特にパートタイム勤務者にとっては負担が大きくなる場合も
- 退職後の継続利用には制限がある
- 退職後も共済組合を利用するには「任意継続」が必要
- 任意継続すると、事業主負担がなくなり保険料が倍額になる
- 加入できる条件がある
- パートタイム勤務の人は、労働時間や給与額によっては加入できない
- 短期間の任用では、共済組合の恩恵を十分に受けられない
- 保険証の切り替えが必要になる
- 加入時や退職時に、健康保険証の切り替え手続きが必要
- 扶養家族の手続きも発生し、手間がかかる
どんな人に向いている?
共済組合は、長期間安定して働く人にとっては大きなメリットがあります。一方で、短期間の任用を繰り返す人やパートタイム勤務者には、掛金負担が大きく感じられるかもしれません。
| 項目 | メリットが大きい人 | デメリットが大きい人 |
|---|---|---|
| 健康保険 | 高額医療を受ける可能性がある人 | 健康で病院をほぼ利用しない人 |
| 年金 | 長期間働く予定の人 | 短期間で退職する人 |
| 福利厚生 | 各種補助を活用できる人 | 福利厚生にあまり関心がない人 |
共済組合への加入が向いているかどうかは、自身の働き方やライフプランによって異なります。加入前に、掛金負担と受けられるメリットをしっかり比較し、自分に合った選択をしましょう。
会計年度任用職員の保険証の何が変わる?切り替えのポイント
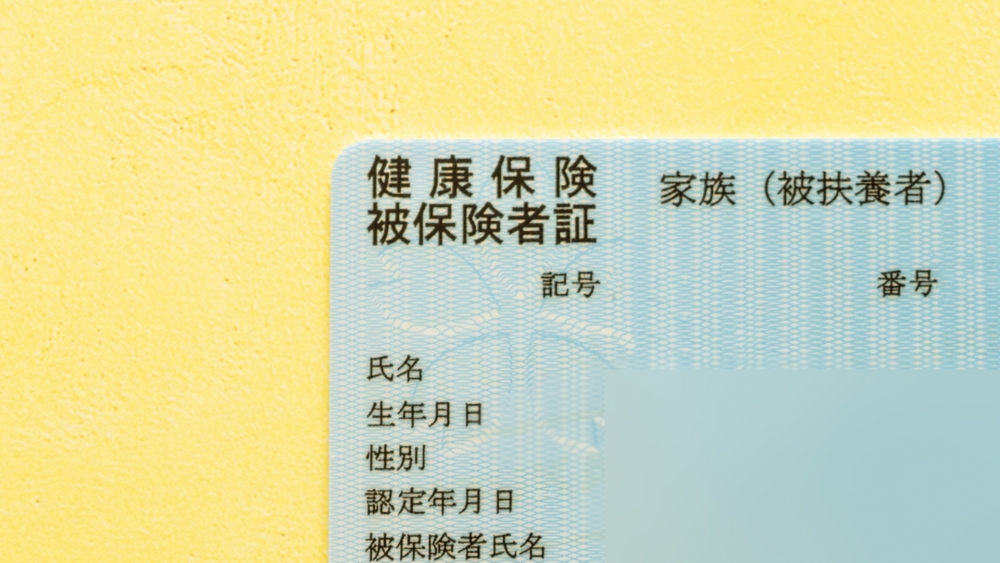
会計年度任用職員の保険証は、令和4年(2022年)10月1日からの制度変更により大きく変わりました。従来は国民健康保険を利用していた職員の一部が、共済組合の健康保険に加入できるようになりました。ここでは、主な変更点と切り替えの際に注意すべきポイントを解説します。
保険証の発行元が共済組合に統一
これまでは、フルタイムの職員は共済組合の保険に加入していましたが、パートタイム職員の多くは国民健康保険に加入していました。しかし、勤務時間が週20時間以上で、報酬月額8万8千円以上の職員は、新たに共済組合の保険へ加入することになりました。
【保険証の変更前後】
| 項目 | 変更前(国民健康保険) | 変更後(共済組合保険) |
|---|---|---|
| 発行元 | 自治体が発行する保険証 | 共済組合が発行する保険証 |
| 自己負担割合 | 3割 | 変わらず3割 |
| 任意継続制度 | なし | 退職後も任意継続可能(最大2年) |
※ 2024年12月2日以降は保険証の新規発行が廃止され、マイナンバーカードが保険証の役割を担います。
保険料の負担が変わる
共済組合の保険に加入すると、給与から健康保険料が天引きされます。共済組合の保険料は一般的な健康保険と比べて約1割程度安い場合が多いです。また、共済組合には「付加給付」があり、一定額以上の医療費は還付されるため、医療費の負担は軽減される可能性があります。
被扶養者の認定が必要
共済組合に加入すると、家族を被扶養者として登録する必要があります。被扶養者がいる場合は、収入条件などを満たす必要があるため、事前に申請を行いましょう。
保険証切り替え時の手続き
保険証が切り替わる際には、以下の手続きが必要になります。
- 新しい保険証の受け取り
共済組合から郵送または勤務先で受け取る - 旧保険証の返却
国民健康保険の保険証は、自治体の窓口へ返却する - 被扶養者の申請
配偶者や子どもを扶養に入れる場合は、共済組合へ申請を行う。
注意点
- 手続きの期限を守る
新しい保険証が届いたら、すぐに旧保険証を返却すること - 医療機関での確認
病院にかかる際は、保険証の変更を事前に伝えておくとスムーズ - 保険料の変動をチェック
給与の手取り額が変わる可能性があるため、事前に確認しておく
共済組合の保険に切り替わることで、医療費の補助が受けられるなどのメリットがあります。一方で、保険料の負担や手続きが増えるため、事前に準備をしておきましょう。
【会計年度任用職員】共済組合のデメリットはある?待遇や将来の資産

- 退職金はどのくらい?
- 任意継続の手続きと注意点
- 【会計年度任用職員】共済組合のデメリットはある?(まとめ)
退職金はどのくらい?
会計年度任用職員は、フルタイムとパートタイムの勤務形態によって退職金の有無が異なります。ここでは、退職金が支給される条件や金額の目安について詳しく解説します。
退職金の支給条件
退職金を受け取れるのは、フルタイム会計年度任用職員に限られます。
パートタイム会計年度任用職員には退職金制度がありません。
【退職金の支給条件】
- フルタイム勤務である(1週間当たりの通常の勤務時間が常勤職員と同じ38時間45分)
- 1月あたりの勤務日数が18日以上ある月が、引き続き6月を超える場合に至った場合
- 退職理由によって支給率が異なる可能性がある(自己都合の場合も支給される可能性あり)
退職金の金額の目安
退職金の計算は、基本給と勤続年数に応じて決まります。具体的な金額は自治体ごとに異なりますが、以下の要素が考慮されます。
- 基本給
- 勤続年数
- 退職事由(自己都合、定年、勧奨等)
- 自治体の条例で定められた支給率
一般的に、勤続年数が長いほど退職金の額も増えます。
退職金を受け取る際の注意点
- 支給までに時間がかかる
退職金は申請後すぐには支給されず、数か月かかることが多い - 税金がかかる
退職金には一定の税金がかかるため、手取り額は少し減る可能性がある - 短期間の勤務では支給されない
6か月以下の勤務では退職金はもらえない
退職後の生活を考えると、退職金を受け取れるかどうかは重要なポイントです。自分の勤務形態を確認し、計画的に働くようにしましょう。
任意継続の手続きと注意点

会計年度任用職員が退職後も共済組合の健康保険を継続できる任意継続制度について解説します。この制度を利用することで、退職後も最大2年間、共済組合の保険に加入できます。
任意継続できる条件
任意継続を利用できるのは、以下の条件を満たした場合です。
- 1年以上、共済組合に加入していた
- 退職日から20日以内に申請を行う
- 再就職先で別の健康保険に加入しない
任意継続の手続きの流れ
任意継続を希望する場合は、以下の手続きを行います。
- 申請書の提出
共済組合から「任意継続申請書」を取り寄せ、必要事項を記入する - 初回保険料の納付
退職日から20日以内に初回の保険料を支払う - 被扶養者の申請
家族を扶養に入れたい場合は、別途申請が必要
任意継続の注意点
- 保険料の全額負担が必要
在職時は保険料の一部を自治体が負担していましたが、退職後は全額自己負担となります。そのため、保険料が高くなる可能性があります。 - 支払いが遅れると資格を失う
保険料の支払いが遅れると、即座に資格を失い、再加入できなくなります。期限をしっかり確認し、払い忘れのないようにしましょう。 - 途中で辞めることはできない
一度任意継続を選択すると、最大2年間は原則として継続する必要があります。ただし、再就職して他の健康保険に加入した場合は途中解約が可能です。
退職後も医療保険が必要な人にとって、任意継続は有益な制度です。ただし、保険料負担が増えるため、他の選択肢(国民健康保険への切り替えなど)と比較して決めるようにしましょう。
【会計年度任用職員】共済組合のデメリットはある?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 共済組合に加入すると給与から保険料が引かれ手取りが減る
- パートタイム職員は加入条件を満たさないと共済に入れない
- 任意継続を選ぶと保険料が全額自己負担となり高くなる
- 退職金はフルタイム職員のみで、パートには支給されない
- 加入や切り替えの際に手続きが多く時間がかかる
- 保険証の返却や受け取りなどの事務処理が面倒
- 被扶養者の登録にも追加の書類提出や条件確認が必要
- 加入条件に満たないと国民健康保険と国民年金に戻る必要がある
- 任期が短いと福利厚生の恩恵を十分に受けられない
- 病院にかかる前に保険証の変更を知らせる必要がある
- 保険料の支払い遅れで任意継続の資格を失う可能性がある
- 継続中は原則2年間やめられず途中解約しづらい
- 退職金が出るまでに時間がかかり手取りも減る
- 短時間勤務では加入できず制度の恩恵を得にくい
- 制度変更で条件が変わるため常に最新情報の確認が必要