会計年度任用職員として働きながら、ご家族の介護が必要になったとき、「介護休暇を93日取れると聞いたけれど、具体的な制度がよく分からない」と悩んでいませんか。特に、会計年度任用職員の介護休暇は無給なのか、給与面での不安は大きいことでしょう。
また、似ているようで少し違う介護休暇と介護時間の違いや、実際に休むために必要な介護休暇の申請方法と必要書類について、正確な情報を探している方も多いはずです。
この記事では、会計年度任用職員の介護休暇93日制度について、これらの疑問を一つひとつ丁寧に解消していきます。制度の全体像から具体的な注意点まで網羅的に解説しますので、安心して制度を活用するための知識を得ることができます。
- 介護休暇93日の制度と具体的な取得条件
- 介護休暇中の給与(無給)とそれを補う給付金制度
- 介護時間や有給休暇など、他の休暇制度との違いと使い分け
- 休暇取得に必要な申請手続きの流れと注意点
会計年度任用職員の介護休暇(93日)|制度と概要

- そもそも会計年度職員の介護休暇は何日?
- 介護休暇は93日が上限
- 介護休暇を取得できる家族の範囲とは
- 介護休暇の分割取得は3回まで可能
- 介護休暇と介護時間の違いを解説
そもそも会計年度職員の介護休暇は何日?
会計年度任用職員が利用できる介護のための休暇は、大きく分けて2種類あります。一つは、突発的なお世話が必要なときに利用する「短期介護休暇」、もう一つは、まとまった期間の介護が必要なときに利用する「介護休暇(93日)」です。
短期介護休暇は、要介護者である家族が1人の場合は1年間に5日、2人以上の場合は10日を上限として取得できます。
一方で、この記事で詳しく解説する介護休暇は、より長期的な介護に対応するための制度となっています。介護の状況に応じて利用できる休暇制度が複数用意されている点をまず理解しておきましょう。
介護休暇は93日が上限
まとまった期間の介護が必要な場合、会計年度任用職員は、要介護状態にある同一の家族1人につき、通算で93日間を上限として介護休暇を取得することが可能です。この「通算93日」という日数は、介護が必要な期間に応じて、柔軟に使うことができます。
例えば、一人のご家族の介護のために93日を使い切った後、別の家族が要介護状態になった場合は、そのご家族のためにも新たに93日間の介護休暇を取得できます。介護休暇制度は対象となる家族ごとに適用される仕組みです。
介護休暇を取得できる家族の範囲とは

介護休暇の対象となる家族の範囲は、法律で広く定められています。具体的には、以下の続柄の方が対象です。
- 配偶者(事実婚の関係にある方を含む)
- 父母、子(養父母、養子を含む)
- 配偶者の父母
- 祖父母、孫
- 兄弟姉妹
これらの家族が「2週間以上にわたり常時介護を必要とする状態」にある場合に、介護休暇を取得する要件を満たします。同居しているかどうかは問われません。ただし、叔父や叔母、いとこなどは対象外となるため注意が必要です。
介護休暇の分割取得は3回まで可能
介護休暇の93日間は、一度にまとめて取得する必要はありません。要介護者1人につき、3回を上限として分割して取得することが認められています。この仕組みにより、介護の状況の変化に柔軟に対応することが可能です。
例えば、最初は入院の付き添いのために30日間取得し、一度職場に復帰した後、退院後の在宅介護のために再度40日間取得するといった使い方ができます。ただし、分割できるのは3回までで、合計日数は93日を超えることはできません。
介護休暇と介護時間の違いを解説
介護に関する制度には、「介護休業」の他に「介護短時間勤務」というものがあります。これらは目的や取得単位が異なるため、状況に応じて使い分けることが大切です。
| 項目 | 介護休業(長期) | 介護短時間勤務 |
|---|---|---|
| 主な目的 | 長期的な介護のためのまとまった休み | 日々の短時間介護との両立 |
| 取得可能日数 | 通算93日(1人につき、3回まで分割可能) | 介護が必要な期間中利用可能 |
| 取得単位 | 1日単位 | 1日2時間以内(30分単位など) |
| 利用シーン | 入院の付き添い、集中的な在宅介護 | デイサービスの送迎、通院の付き添い |
要するに、介護休業は「休む」制度であり、介護短時間勤務は「勤務時間を短縮する」制度です。どちらの制度が自身の状況に適しているか、よく検討しましょう。
会計年度任用職員が介護休暇(93日)を取得する際の注意点

- 介護休暇は無給が原則
- 無給を補う介護休業給付金の支給条件
- 申請方法と必要書類
- 任期満了が近い場合の取得条件
- 有給休暇は何日もらえる?
- 会計年度任用職員の介護休暇(93日)|制度と概要(まとめ)
介護休暇は無給が原則
会計年度任用職員の介護休暇について、最も注意すべき点は、休暇を取得している期間の給与は原則として「無給」となることです。これは、介護休暇が給与の支払い義務がない「特別休暇」として位置づけられているためです。
給与が支給されないため、介護休暇を長期間取得する際には、経済的な影響を十分に考慮する必要があります。生活費などを事前に計画しておかなければなりません。このため、後述する介護休業給付金の活用や、手持ちの年次有給休暇と組み合わせて使うなどの工夫が求められます。
無給を補う介護休業給付金の支給条件
前述の通り、介護休暇中は無給となりますが、一定の条件を満たすことで雇用保険から「介護休業給付金」を受け取ることができます。これは、介護のために休業する労働者の生活を支えるための制度です。
主な支給条件
支給を受けるためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 雇用保険の被保険者であること
- 介護休業を開始した日前2年間に、被保険者期間が12か月以上あること
- 介護休業期間中の各1か月において、休業日数が10日以下であること
- 休業中に支払われた賃金が、休業開始前の賃金の80%未満であること
特に、会計年度任用職員のような有期雇用労働者の場合、「介護休業開始予定日から93日を経過する日から6か月を経過する日までに、労働契約が満了することが明らかでないこと」という追加の要件があります。
申請方法と必要書類
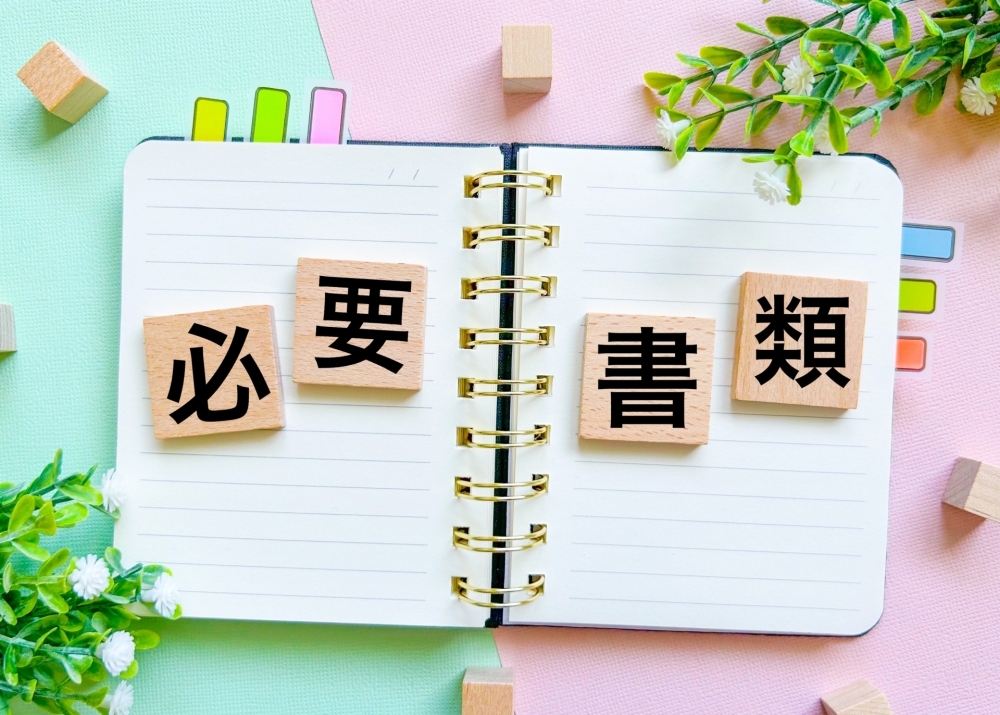
介護休暇を取得するためには、定められた手続きに従って申請を行う必要があります。急な申し出では業務の調整が難しくなるため、介護が必要になる可能性が出てきた段階で、早めに所属部署の上司や人事担当者に相談することが望ましいです。
具体的な手続きとしては、多くの自治体で「介護休暇承認請求書」などの所定の様式を提出することが求められます。その際、介護が必要な事実を証明するために、以下のような書類の添付を求められる場合があります。
- 医師の診断書
- 要介護認定の通知書の写し
- 介護対象家族との続柄がわかる住民票など
必要な書類は自治体によって異なるため、必ず事前に担当部署に確認してください。
任期満了が近い場合の取得条件
会計年度任用職員が介護休暇を取得する際、自身の任期がいつ満了するかは非常に重要な要素です。制度上、介護休暇の取得期間中に任期が満了し、かつその後の任期が更新されないことが明らかである場合には、介護休暇を取得することができません。
具体的には、「介護休暇の開始予定日から起算して93日を経過する日から6か月を経過する日までに任期が満了し、更新されないことが明らかである」場合には対象外となります。
これは、休業後の職場復帰を前提とした制度であるためです。休暇を申請する際には、自身の任期と更新の見通しについて、必ず所属部署に確認しておきましょう。
有給休暇は何日もらえる?
無給である介護休暇と上手く組み合わせて使いたいのが、給与が支払われる「年次有給休暇」です。会計年度任用職員に付与される年次有給休暇の日数は、週の所定勤務日数や勤続年数によって異なります。
| 週の勤務日数 | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 |
|---|---|---|---|---|
| 週5日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 |
※年度途中の採用の場合は、その年度の在職期間に応じて按分されます。 ※上記の表は一例です。詳細は各自治体の規定をご確認ください。
介護休暇を取得する際には、これらの有給休暇を計画的に利用することで、収入の減少をある程度補うことが考えられます。
会計年度任用職員の介護休暇(93日)|制度と概要(まとめ)
この記事で解説した、会計年度任用職員の介護休暇(93日)に関する重要なポイントを以下にまとめます。制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて適切に活用するための参考にしてください。
- 会計年度任用職員も家族の介護のために休暇を取得できる
- 長期の介護休暇は要介護者1人につき通算93日が上限
- 休暇は最大3回まで分割して取得することが可能
- 休暇を取得している間の給与は原則として無給
- 雇用保険の条件を満たせば介護休業給付金が支給される
- 短期的な介護には年間5日または10日の短期介護休暇も利用できる
- 日々の勤務時間を短縮する介護時間制度という選択肢もある
- 取得には週3日以上または年121日以上の勤務といった要件がある
- 任期満了が近く、契約更新の見込みがない場合は取得できないことがある
- 申請には所属部署への事前相談と所定の書類提出が必要
- 医師の診断書など介護の状況を証明する書類を求められる場合がある
- 対象となる家族は配偶者・父母・子・祖父母・兄弟姉妹など広い範囲
- 無給であるため年次有給休暇との計画的な使い分けが大切
- 制度の細かな運用は所属する自治体の規定によって異なる
- 不明な点や不安なことは必ず所属部署の人事担当者に確認する


-6.jpg)







