会計年度任用職員として働くことに、漠然とした不安や疑問を感じていませんか。会計年度任用職員はデメリットしかない、仕事は激務だといった声を聞く一方で、会計年度任用職員は誰でもなれるというイメージもあり、実際のところはどうなのか、情報が錯綜しているかもしれません。中には、職場で馬鹿にされるのではないかと、人間関係について心配している方もいるでしょう。
この記事では、そうした疑問や不安を解消するために、会計年度任用職員という働き方の実態を、客観的な情報に基づいて多角的に解説します。制度の成り立ちから、具体的な待遇、そして将来のキャリアパスまで、この記事を読めば、あなたが次のステップに進むための判断材料がきっと見つかります。
- 「会計年度任用職員がいらない」と言われる背景や理由
- 制度のメリット・デメリットと具体的な待遇
- やりがいや今後のキャリアを考えるための選択肢
- 後悔しないための賢い働き方や転職戦略
「会計年度任用職員はいらない」と言われる実態

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
- 会計年度任用職員は、そもそもなぜできたのか?
- 「デメリットしかない」と言われる待遇とは
- 会計年度任用職員は激務?馬鹿にされる?
- 正規職員との間に存在する不合理な格差
- 「誰でもなれる」のか?会計年度任用職員採用の実態
会計年度任用職員は、そもそもなぜできたのか?

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員制度が創設されたのは、地方公務員の非正規職員が抱えていた待遇格差を是正し、任用ルールを全国的に統一することが主な目的です。
2020年4月の地方公務員法改正以前は、臨時職員や非常勤職員といった非正規公務員の待遇や雇用条件は、各自治体の判断に委ねられていました。そのため、同じような仕事内容であっても、自治体によって賃金や手当に大きな差が生じるという不公平な状況が存在したのです。
このような問題を解決するため、国は法改正に踏み切り、従来の臨時・非常勤職員に代わる新しい統一的な身分として「会計年度任用職員」を設けました。
この制度によって、これまで曖昧だった任用プロセスや勤務条件を明確化し、公務員としての地位を保障することで、非正規職員がより安定して働ける環境を整えることを目指しています。
「デメリットしかない」と言われる待遇とは

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員の待遇面で最大のデメリットとして挙げられるのは、雇用の不安定さです。原則として任期が1年であり、毎年契約を更新する必要があります。
公務員というと安定したイメージがありますが、会計年度任用職員の場合は、年度末ごとに雇用の継続について面談が行われ、勤務態度などによっては契約が更新されない、いわゆる「雇い止め」のリスクが常につきまといます。
また、人件費が補助金で賄われている部署などでは、事業の終了と共に職を失う可能性も否定できません。長期的なキャリアを築きにくい点が、この制度の大きな課題となっています。
さらに、会計年度任用職員のうちフルタイム勤務の場合は副業が原則禁止されていますが、短時間勤務の場合は副業が原則として認められているため、収入面での制約は勤務形態によって異なります。安定した収入の増加が見込みにくい中で、副収入を得る道が限られている状況は、厳しい側面と言えます。
会計年度任用職員は激務?馬鹿にされる?
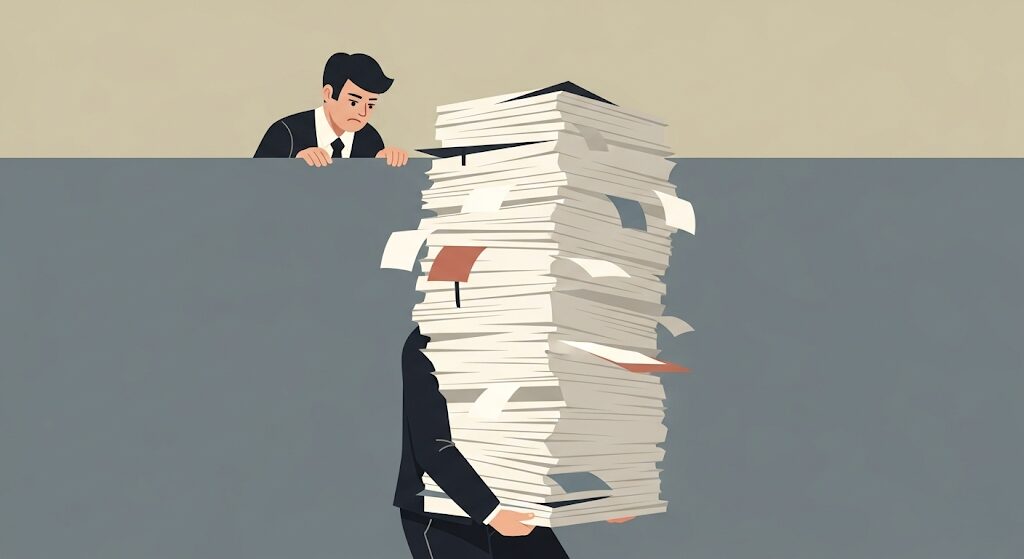
脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
「激務」であるかどうかは、配属される部署や担当する業務によって大きく異なります。しかし、一部の現場では人手不足が深刻で、正規職員の業務を補うために、想定以上の業務量をこなさなければならないケースも見受けられます。残業は少ない傾向にありますが、その分、勤務時間内に仕事を終わらせるプレッシャーが強いと感じる人もいます。
また、「馬鹿にされる」と感じる背景には、正規職員との立場上の格差やコミュニケーションの問題があります。本来は正規職員の補助が役割ですが、実際には同等の責任を負わされながら、重要な情報共有の輪からは外されたり、意思決定の過程に関与できなかったりすることが、疎外感や不満につながるのです。
このような待遇と責任の不均衡が、心理的な負担となり「割に合わない」「軽く扱われている」といった感情を抱かせる一因と考えられます。
正規職員との間に存在する不合理な格差

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員と正規職員との間には、同じ職場で同様の業務を行っていても、待遇面に様々な格差が存在します。これは「不合理な格差」として、制度の大きな問題点の一つに挙げられます。
具体的には、給与水準だけでなく、各種手当や福利厚生の面でも違いが見られます。以下の表は、一般的な待遇差をまとめたものです。
| 項目 | 会計年度任用職員 | 正規職員 |
|---|---|---|
| 給与水準 | 正規職員の6~7割程度の場合がある | 経験年数に応じ昇給 |
| 各種手当 | 通勤手当は支給されるが、住居手当や扶養手当は対象外が多い | 法律に基づき各種手当が支給される |
| 福利厚生 | 共済組合の利用範囲などが限定されることがある | 各種福利厚生制度を全て利用できる |
| 昇進・昇格 | 原則としてない | 勤務評価や経験に応じて行われる |
| 昇給 | 自治体や評価によっては昇給があるが、正規職員ほど自動的・体系的ではない | 経験年数に応じて行われる |
もちろん、これらの待遇は自治体によって異なりますが、全体的な傾向として、非正規という立場から生じる格差が存在することは否めません。こうした状況が、仕事へのモチベーション低下につながることもあります。
「誰でもなれる」のか?会計年度任用職員採用の実態

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員の募集は、特別な資格や経験を問わない事務補助などの職種も多く、門戸が広いことは事実です。そのため、「誰でもなれる」というイメージを持つ方もいるかもしれません。
しかし、実際には「誰でも無条件になれる」わけではありません。採用にあたっては、原則として公募が行われ、書類選考や面接といったプロセスを経る必要があります。特に面接では、志望動機やコミュニケーション能力、そして何よりその職務への適性が評価されます。
人気の職種や自治体では応募者が多く、倍率が高くなることも珍しくありません。未経験者でも応募可能な職種は多いですが、即戦力として業務をこなせる能力が期待されるため、これまでの社会人経験やスキルが採用の可否を左右することも十分考えられます。
応募のハードルは比較的低いものの、採用されるためにはしっかりとした準備が求められるのが実態です。
会計年度任用職員はいらないと感じた後のキャリア

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
- 会計年度任用職員が「楽しい」と感じるやりがい
- 会計年度任用職員は今後、減少していきますか?
- 「やめたい」と感じた後の転職戦略とは
- 正規職員や民間への転職を成功させる方法
- 制度の中で後悔せずに働くための視点
- 会計年度任用職員はいらないと結論付ける前に(まとめ)
会計年度任用職員が「楽しい」と感じるやりがい

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
これまで述べてきたように、会計年度任用職員には多くの課題がありますが、一方でこの働き方ならではのメリットや、やりがいを感じる人も少なくありません。
最も大きな魅力として挙げられるのが、地域社会への貢献を直接実感できる点です。役所の窓口業務や、福祉・教育の現場などで住民と接する中で、感謝の言葉をかけられたり、人の役に立っていると感じられたりする瞬間は、大きな喜びとなります。
また、ワークライフバランスを重視する人にとっては、理想的な働き方となる可能性があります。正規職員に比べて残業が少なく、定時で退勤できる職場が多いため、終業後の時間を趣味や家庭、自己啓発などに充てやすいのです。特にパートタイム勤務であれば、より柔軟な働き方が可能になります。
最終的な意思決定の責任は正規職員が負うため、過度なプレッシャーを感じることなく、与えられた職務に集中できる点を魅力に感じる人もいます。
会計年度任用職員は今後、減少していきますか?

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員という制度が、今後すぐに無くなる可能性は低いと考えられます。むしろ、その役割は見直されつつも、自治体運営にとって不可欠な存在として定着していくと予測されます。
その背景には、二つの側面があります。一つは、多くの自治体が抱える財政難と人手不足です。正規職員の採用を抑制する中で、多様化・複雑化する行政サービスを維持するためには、会計年度任用職員の柔軟な労働力が欠かせません。
もう一つの側面は、国による処遇改善の動きです。例えば、2025年からは再任用の上限回数が撤廃され、自治体の判断で継続的な任用が可能になるなど、雇用の安定性を高める法改正が進んでいます。
これらのことから、単純に数が減少するというよりは、専門性の高い業務や、柔軟な働き方が求められる分野で、その役割がより重要になっていくと言えるでしょう。
「やめたい」と感じた後の転職戦略とは

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
もしあなたが会計年度任用職員として働く中で、「やめたい」と感じたのであれば、転職は有力な選択肢となります。重要なのは、自身の状況を客観的に分析し、戦略的に次のステップを考えることです。
まず、なぜ「やめたい」と感じるのかを明確にしましょう。それが雇用の不安定さなのか、収入面への不満なのか、あるいはキャリアアップが見込めないことへの焦りなのかによって、目指すべき方向性は異なります。
例えば、より安定した環境を求めるのであれば、経験を活かして正規職員を目指す道が考えられます。一方で、自身のスキルを活かしてより高い収入やキャリアを求めるのであれば、民間企業への転職が視野に入ってくるでしょう。
いずれの道を選ぶにしても、会計年度任用職員として培った経験は決して無駄にはなりません。その経験をいかに次のキャリアに繋げるかを考え、早期に行動を開始することが、転職を成功させるための鍵となります。
正規職員や民間への転職を成功させる方法

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員からのキャリアチェンジを成功させるためには、公務員としての経験を「強み」として効果的にアピールする必要があります。
正規職員を目指す場合
多くの自治体では、会計年度任用職員などの職務経験者を対象とした、特別な採用選考枠を設けています。筆記試験が免除されたり、面接が重視されたりすることが多く、一般の採用試験よりも有利に進められる可能性があります。
対策としては、日々の業務でどのような実績を上げたか、どう課題解決に取り組んだかを具体的に説明できるように整理しておくことが大切です。
民間企業を目指す場合
民間企業へ転職する際は、「公務員経験で得たスキル」を企業の求める能力に結びつけて説明することが求められます。
例えば、窓口業務で培った丁寧な対人対応能力やクレーム処理能力、法令や規則に基づいて正確に事務を処理する能力などは、多くの企業で高く評価されるでしょう。
特に、公共性の高いインフラ企業や医療機関、あるいはコンサルティング会社などは、公務員経験が活かせる分野と考えられます。
制度の中で後悔せずに働くための視点

脱!地方公務員のつぶやき・イメージ
会計年度任用職員として働き続けることを選ぶ場合でも、後悔しないためにはいくつかの視点を持つことが大切です。
第一に、この制度のメリットとデメリットを正しく理解し、割り切ることも必要です。正規職員との待遇差などに不満を感じるのではなく、例えば「ワークライフバランスを重視できる」「過度な責任はない」といったメリットを最大限に活用するという考え方です。
第二に、受け身の姿勢でいるのではなく、主体的な行動が求められます。研修の機会があれば積極的に参加してスキルを磨いたり、業務改善の提案を行ったりと、職場での自身の価値を高められます。
そして、同じ立場で働く仲間とのネットワークを築くことも有効です。悩みを共有したり、有益な情報を交換したりすると、精神的な支えとなり、孤立を防ぐことにもつながります。自身のキャリアは自身で築くという意識を持つことが、後悔しない働き方の基本と言えるでしょう。
会計年度任用職員はいらないと結論付ける前に(まとめ)
この記事では、会計年度任用職員という働き方について、多角的な視点から解説してきました。最後に、あなたが今後のキャリアを判断する上で、改めて確認しておきたいポイントをまとめます。
- 制度は非正規職員の待遇格差是正を目的に創設された
- 1年ごとの契約更新という雇用の不安定さが最大のデメリット
- 定期昇給はほぼなくボーナスや退職金の支給も限定的
- 業務が激務になるかどうかは配属される部署によって大きく異なる
- 賃金や福利厚生において正規職員との間に明確な格差が存在する
- 応募しやすいが選考があり誰でも無条件になれるわけではない
- 地域社会への貢献や住民との関わりにやりがいを感じる人も多い
- プライベートと仕事を両立させやすい点は大きなメリット
- 制度がすぐに廃止される可能性は低く今後も存続すると考えられる
- 再任用制限の撤廃など処遇は少しずつ改善される傾向にある
- 現在の働き方に不満なら転職も有力な選択肢の一つ
- 公務員としての経験は正規登用や民間転職で強みになり得る
- 転職を成功させるには経験を言語化し戦略的に行動することが不可欠
- 制度のメリットとデメリットの両方を冷静に理解することが重要
- 自身のライフプランやキャリアの目標と照らし合わせて最終的に判断する










