会計年度任用職員として働いている方や、これから応募を考えている方の中には、「会計年度任用職員の5年ルール」と検索して、制度の仕組みや今後の働き方について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
とくに、3年ルールや更新の上限、再任用の回数制限など、自治体ごとに対応が異なるため、分かりにくい点が多いのが現状です。中には、契約が更新されなかった理由がわからず、次の就職先に悩む方もいます。
また、何歳まで働けるのか気になる高年齢の応募者も少なくありません。最近では、更新回数の上限撤廃に向けた動きも広がりを見せていますが、すべての自治体で実施されているわけではないため、しっかりと最新情報を把握しておく必要があります。
この記事では、会計年度任用職員に関する5年ルールの実態や更新制限、再任用との違い、年齢制限の考え方まで、初めての方にもわかりやすく丁寧に解説します。自分の働き方を見直すヒントとして、ぜひ参考にしてください。
- 会計年度任用職員に5年ルールが適用されない理由がわかる
- 自治体ごとに異なる更新回数の上限について理解できる
- 3年ルールや更新されなかった背景を知ることができる
- 年齢制限や再任用の実態について把握できる
会計年度任用職員に5年ルールは適用される?

- 会計年度任用職員とは?一般職との違いも解説
- 3年ルールとは何ですか?
- 5年ルールは適用される?
- 更新上限撤廃はどこまで進んでいるか?
会計年度任用職員とは?一般職との違いも解説
会計年度任用職員とは、地方自治体で1年ごとに契約される非常勤の公務員です。2020年から新しく制度化され、全国の市役所や県庁などで幅広く働いています。
この制度は、それまでバラバラだった臨時職員や非常勤職員の仕組みを整理して、統一されたルールのもとで任用されるようにするために作られました。名前の通り、4月から翌年3月までの「会計年度」を区切りにして、毎年契約されるのが特徴です。
一方、正規の一般職公務員は、採用試験に合格し、基本的に定年まで雇われる安定した働き方になります。給与や昇進の仕組みもきちんと整っていて、ボーナスや退職金もあります。
これに対して、会計年度任用職員はフルタイムでも昇進がなかったり、パートタイムだと退職金が出ないなど、待遇面で差があるのが現状です。
主な違いをまとめると以下のとおりです。
| 項目 | 会計年度任用職員 | 一般職公務員 |
|---|---|---|
| 採用方法 | 面接や書類選考が中心 | 公務員試験に合格 |
| 契約期間 | 原則1年ごとの更新 | 無期限(定年まで) |
| 昇進・昇給 | 限定的またはなし | 能力や年数に応じて昇進 |
| 手当や福利厚生 | 一部のみ | 充実している |
同じ自治体で働いていても、立場や待遇には大きな違いがあります。制度の仕組みを理解したうえで、どちらの働き方が自分に合っているかを考えるのが大切です。
3年ルールとは何ですか?
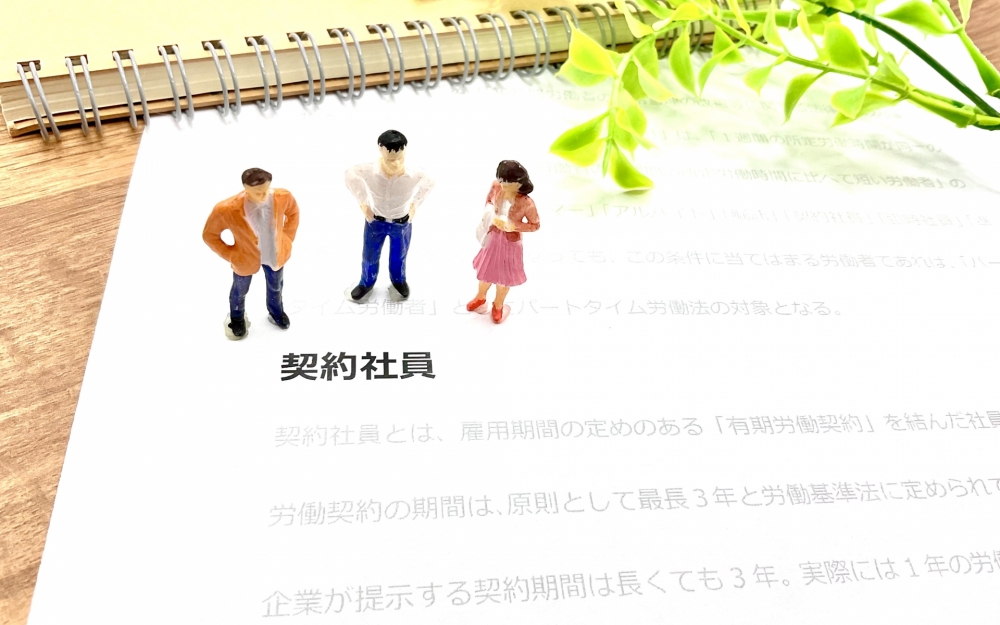
「会計年度任用職員には3年ルールがある」と聞いた人もいるかもしれません。しかし、これは正確に言うと法律ではなく、総務省のガイドラインに基づいた運用ルールです。つまり全国どこでも3年までと決まっているわけではなく、自治体ごとに判断が分かれています。
もともと、国の非常勤職員には「原則2回まで更新できる」という決まりがありました。これに合わせて、多くの自治体も「最大3年まで勤務」とする方針を取ってきたのです。ただしこのルールは、2024年に見直しが進みました。
今では次のような違いが出ています。
【主な運用のパターン】
- 更新は2回まで(計3年)
全国の約3割の自治体が採用 - 更新は最大4回(計5年)
東京都の一部などが該当 - 更新回数に制限なし
専門性が高い仕事では上限をなくす自治体もあり
会計年度任用職員に「必ず3年ルールがある」とは言えません。自分の自治体がどの運用をしているか、募集要項や人事課への問い合わせで確認しておくことが安心です。
特に「長く働きたい」と考えている人にとっては、更新の上限がキャリア設計に大きく影響します。早めに情報を集めて、備えておくとよいでしょう。
5年ルールは適用される?
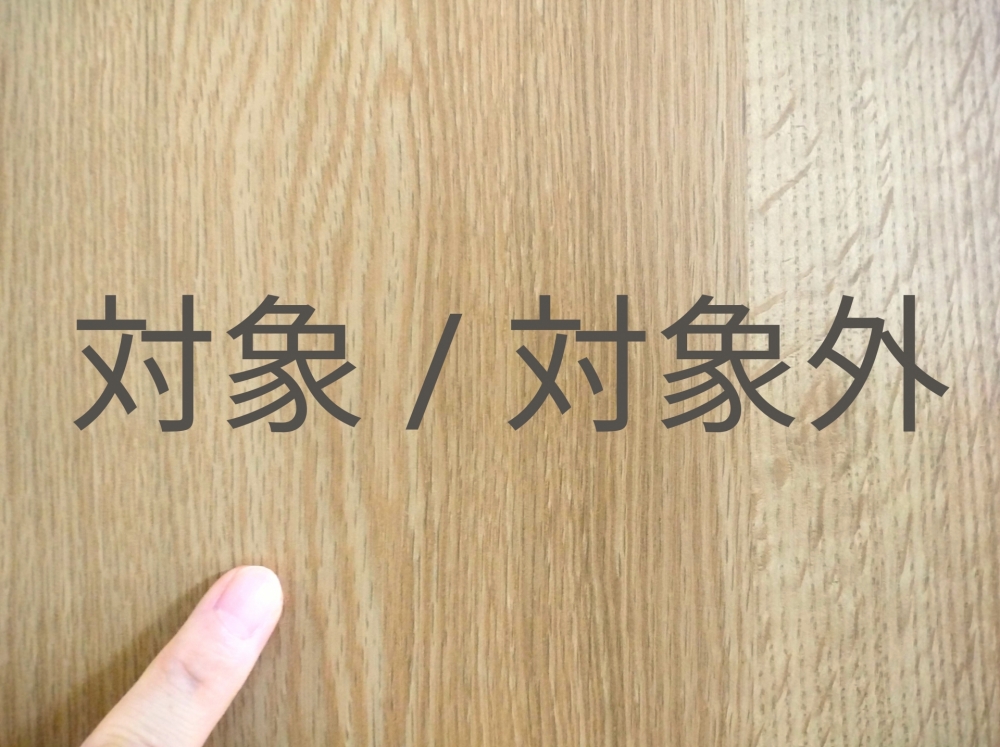
会計年度任用職員には、民間企業で適用される「5年ルール(無期転換ルール)」は適用されません。このルールは、同一の使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合、労働者の申し出により無期労働契約に転換できる制度です。しかし、会計年度任用職員は地方公務員法に基づく非常勤職員であり、労働契約法の適用外となるため、この制度の対象外です。
そのため、会計年度任用職員は毎年の契約更新が必要であり、長期的な雇用の安定性に欠けるという課題があります。一部の自治体では、独自に再任用の上限を設けており、例えば川崎市では5年目に再度の公募が必要とされています。
近年、国や自治体では再任用の上限撤廃の動きが進んでおり、2024年には人事院と総務省が再任用の上限回数を撤廃する通知を出しました。 これにより、自治体ごとの判断で再任用の上限を設けない運用が可能となりました。しかし、すべての自治体がこの方針を採用しているわけではなく、引き続き再任用の上限を設けている自治体も存在します。
会計年度任用職員には「5年ルール」は適用されず、雇用の継続性は自治体の運用方針に大きく左右されます。長期的な雇用を希望する場合は、勤務先の自治体の再任用方針を事前に確認することが重要です。
更新上限撤廃はどこまで進んでいるか?

会計年度任用職員の更新回数に関する制限は、近年見直しが進んでいます。これまで多くの自治体では、再任用の上限を2回までとし、3回目以降は公募による再採用が必要とされていました。しかし、2024年6月に国がこの制限を撤廃したことを受け、各自治体でも対応が進んでいます。
例えば、中央区では2025年4月1日から、公募によらない再任用の上限回数を撤廃する方針を決定しました。 また、自治労連の調査によれば、回答のあった401自治体のうち、「もともと上限なし」(25.9%)と「廃止済」(16.0%)を合わせると41.9%に達し、さらに「検討中」(19.7%)と「今後検討予定」(7.7%)を含めると、約7割の自治体が上限撤廃に向けた動きを見せています。
このような動きの背景には、優秀な人材の確保と雇用の安定化を図る目的があります。一方で、約23.7%の自治体は「見直す予定なし」と回答しており、採用の公平性や成績主義の観点から、上限の維持を選択しています。
今後、会計年度任用職員として働く方は、自身の勤務する自治体の方針を確認し、更新制度の変更に注意を払うことが重要です。また、雇用の安定性や再任用の可能性について、不明な点があれば早めに担当部署に相談することをおすすめします。
会計年度任用職員の5年ルールと雇止め・再就職のリアル

- 契約更新されなかったケースとその理由
- 会計年度任用職員は何歳まで働ける?
- 再度任用と更新はどう違うのか?
- 非正規でも責任重大?任用職員の仕事内容とは
- 任期満了後の選択肢と再就職
- 会計年度任用職員に5年ルールは適用される?(まとめ)
契約更新されなかったケースとその理由
会計年度任用職員は、原則として1年ごとの契約となっています。そのため、契約の更新が行われない場合もあります。更新されなかった主な理由としては、以下のようなものが挙げられます。
- 業務の縮小や廃止
担当していた業務自体が終了したり、外部委託に切り替えられたりする場合、契約が更新されない場合があります。 - 勤務評価や態度の問題:
過去の勤務成績や職場での態度が評価され、更新が見送られるケースもあります。 - 組織の方針変更や人員整理
自治体の方針転換や予算の都合により、人員の見直しが行われることがあります。 - 新しい人材の導入
新たな視点やスキルを持つ人材を採用するため、既存の職員の契約が更新されないこともあります。
これらの理由により、契約が更新されない場合があります。契約が更新されなかった際には、雇用保険の受給資格があるかどうかを確認し、必要に応じてハローワークで手続きを行うことが重要です。
また、次の職を探す際には、これまでの経験やスキルを活かせる職種を検討し、早めに行動を開始することが望ましいでしょう。
会計年度任用職員は何歳まで働ける?
会計年度任用職員の採用にあたって、法律上の年齢制限は設けられていません。多くの自治体では、年齢不問で募集を行っています。そのため、健康で業務に支障がなければ、高齢であっても任用される可能性があります。
ただし、一部の自治体では、任用の上限年齢を定めている場合があります。例えば、65歳に達する年度の末日を任用の限度とする規定があります。
実際には、60代や70代で採用されている例もあり、職種や業務内容によっては高齢者の経験や知識が重宝される場合です。例えば、図書館司書や学校のサポートスタッフなど、特定のスキルや経験を活かせる職種では、高齢者の採用が行われているケースがあります。
任用の可否は、自治体の方針や募集要項、業務内容によって異なります。応募を検討する際は、各自治体の募集要項を確認し、自身の経験やスキルが求められている職種かどうかを見極めることが重要です。また、健康状態や勤務時間など、自身の状況に合った職種を選ぶことで、長く働き続けることが可能となるでしょう。
再度任用と更新はどう違うのか?

再度任用と更新はよく似た言葉ですが、制度上ははっきりと違いがあります。区別しないまま話を進めてしまうと、誤解が生まれやすいため注意が必要です。
まず「更新」は、今の職場でそのまま仕事を続けられる形です。特別な選考を受けることはなく、過去の勤務が良ければそのまま次の年度に入れます。つまり、連続して同じ仕事を続けるイメージです。
一方「再度任用」は、新しく採用される扱いになります。同じ職場でも、また選考を受けなければなりません。前の勤務実績が参考となる場合はありますが、確実に採用されるとは限らない点がポイントです。
この2つの違いを表にまとめると以下のようになります。
| 比較項目 | 更新 | 再度任用 |
|---|---|---|
| 選考の必要 | なし(勤務成績で判断) | あり(再び面接などを実施) |
| 勤務のつながり | 連続して勤務が続く | 一度退職してから再採用 |
| 安定性 | 比較的高い | 再び応募が必要で不安定 |
仕組みが大きく異なりますので、自治体の説明や契約書をよく確認しておきましょう。再度任用が必要なタイミングでは、早めの準備と情報収集が大切です。
非正規でも責任重大?任用職員の仕事内容とは

会計年度任用職員は「非正規」という名前がついていますが、実際には多くの重要な仕事を任されています。責任も決して軽くありません。
仕事内容はさまざまですが、主に以下の6つの分野に分けられます。
- 事務系
市役所などで書類の受付やデータ入力などを行います。 - 福祉系
保育士や高齢者施設のスタッフなど、人と関わる仕事が多いです。 - 技術系
土木や建築のサポートを担当します。 - 医療系
保健センターで働く看護師や栄養士などが該当します。 - 技能系
給食調理や清掃など、専門的な作業もあります。 - その他
ALT(英語の先生)やカウンセラーも任用職員です。
例えば、保育士や図書館司書などは、正職員とほぼ同じ内容の仕事をしています。それにも関わらず、給料や待遇には差があるケースが多いです。
また、緊急時や忙しい時期には、正職員と一緒に仕事を進めなければならず、責任も大きくなります。非正規だからといって軽い役割ではないのが現状です。
仕事内容をよく知っておくと、自分の希望に合う職種の選択や応募の準備もしやすくなります。採用情報には仕事内容の詳しい説明が載っているので、しっかり確認するようにしましょう。
任期満了後の選択肢と再就職

会計年度任用職員の任期は1年間です。たとえ勤務成績が良くても、翌年度に必ず更新されるわけではありません。更新されないと仕事がなくなるため、早めに次の働き方を考えておくことが大切です。任期満了後には、主に4つの進路があります。
1. 同じ自治体で別の仕事に応募する
自治体によっては、別の部署や職種で募集を出していることがあります。同じ場所で働けるので環境に慣れている人には選びやすい道です。
2. 他の自治体の任用職員になる
市や町を変えれば、また同じように働ける可能性があります。自治体ごとにルールが違うため、求人ページや公報をしっかりチェックしておきましょう。
3. 民間企業に転職する
役所での経験を生かして、事務職や福祉関係の仕事に就く人もいます。特に「公共の仕事を理解している人」として評価されやすいです。
4. 資格取得などでスキルアップ
行政書士や社会福祉士など、これまでの経験と関わりがある資格を取ると就職の幅が広がります。自治体の職業訓練を使えば、お金の負担を減らせることもあります。
任期が終わった後の道は一つではありません。次の仕事を急いで決めるのではなく、自分にとって合っている働き方をじっくり考えることが大切です。再就職のためには、任期が終わる半年ほど前から動き出すのが安心です。
会計年度任用職員に5年ルールは適用される?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員は1年ごとに契約される非常勤の地方公務員
- 正規の一般職公務員とは待遇や安定性に大きな差がある
- 契約期間は原則4月から翌年3月までの1年間
- 昇進や退職金の支給は原則としてない、または限定的
- 採用方法は公務員試験ではなく書類選考や面接が中心
- 「3年ルール」は法律ではなく総務省のガイドラインに基づく運用
- 実際には自治体によって更新回数の上限が異なる
- 一部自治体では「5年まで勤務」など独自ルールを設けている
- 労働契約法の「無期転換ルール」は公務員には適用されない
- 2024年からは国の通知により更新上限の撤廃が可能となった
- 自治体の約7割が更新上限撤廃または検討を進めている
- 雇止めの理由には業務縮小、人員整理、勤務態度などがある
- 採用年齢に法的制限はないが、上限を設ける自治体も存在
- 「更新」は選考不要だが「再度任用」は改めて選考が必要
- 非正規でも仕事内容は正規と同等で責任も重いことが多い










