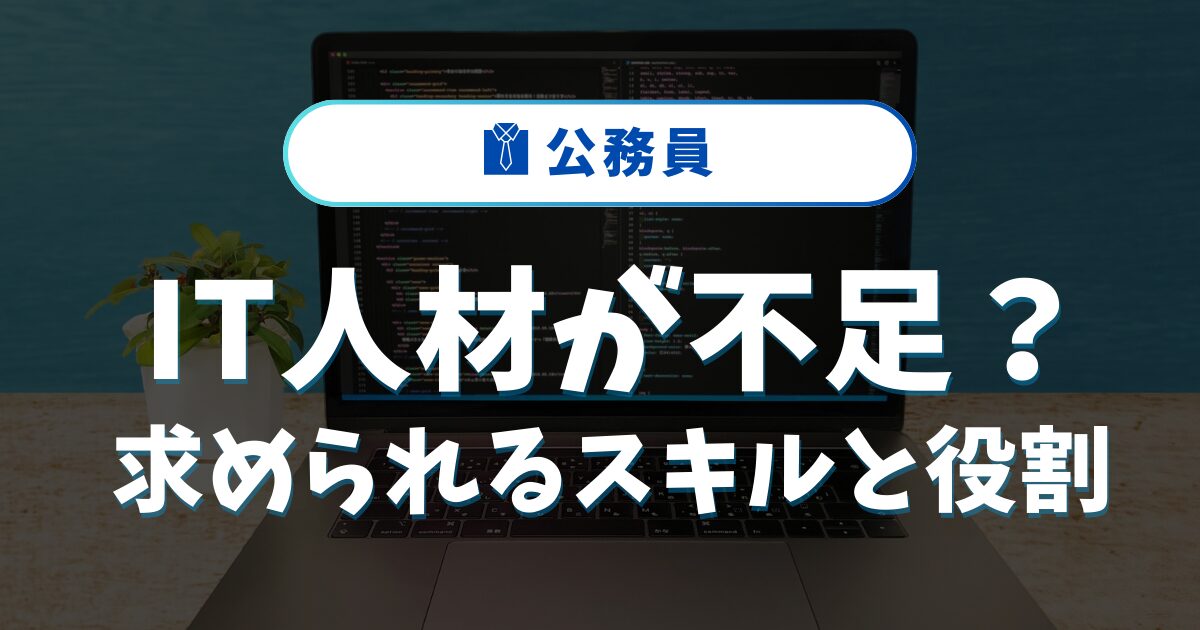近年、行政のデジタル化が進み、公務員の情報系職種におけるIT人材の需要が急速に高まっています。自治体の業務システムを管理・運用するシステムエンジニアや、ネットワーク・セキュリティを担当する専門職など、さまざまな分野でITスキルを持つ公務員が求められています。
しかし、民間のITエンジニアとは異なる働き方や役割があり、「自分にはどっちが向いているのか?」と悩む人も多いでしょう。本記事では、公務員IT人材の仕事内容やキャリアパス、必要なスキルについて詳しく解説します。安定した職場で社会貢献しながらITスキルを活かしたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
- 公務員のIT人材の需要が高まっている理由と現状
- 公務員の情報系職種の種類と仕事内容
- 公務員のシステムエンジニアの役割と求められるスキル
- IT人材が公務員として働くメリットと民間との違い
公務員におけるIT人材の需要とキャリアパス

- 地方公務員のIT人材の需要と現状
- 公務員の情報系職種とは?仕事内容を解説
- IT人材が公務員として活躍するメリット
- IT職の給与とキャリアパスは?
地方公務員のIT人材の需要と現状
近年、地方自治体ではIT人材の需要が高まっています。その背景には、行政サービスのデジタル化や業務の効率化が求められていることがあります。これにより、情報技術を活用できる公務員が必要とされています。
現在、地方公務員のIT人材は以下のような業務に関わっています。
- 行政システムの管理・運用
住民票や税務システムなど、自治体が運営するシステムの維持管理 - セキュリティ対策
サイバー攻撃から住民の個人情報を守る業務 - 業務のデジタル化推進
紙の書類を電子化し、手続きをオンライン化するプロジェクト - データ分析・活用
住民サービス向上のためのデータ活用
しかし、多くの自治体ではIT人材が不足しているのが現状です。その理由として、以下の点が挙げられます。
- 専門職の公務員枠が少ない
- 給与が民間企業に比べて低め
- 最新技術を活用する機会が限られる
この課題を解決するため、政府は2021年9月に「デジタル庁」を設立し、地方自治体のデジタル化推進を支援しています。また、自治体によっては、民間企業と協力してデジタル化を進める例も増えています。
今後、地方自治体におけるIT人材の重要性はさらに高まるでしょう。行政のデジタル化を支える役割として、ITの知識を持つ公務員の需要は拡大していくと考えられます。
公務員の情報系職種とは?仕事内容を解説

公務員の中には、IT関連の仕事を専門とする「情報系職種」があります。これらの職種は、行政サービスのデジタル化やシステム運用を担当し、自治体や国の業務を支えています。
主な情報系職種とその仕事内容を紹介します。
| 職種名 | 主な業務内容 |
|---|---|
| システムエンジニア(SE) | 自治体の業務システムの開発・運用・保守 |
| ネットワーク管理者 | 行政ネットワークの設計・監視・管理 |
| 情報セキュリティ担当 | サイバー攻撃対策や個人情報の保護 |
| データアナリスト | 行政データを活用した政策立案やサービス改善 |
これらの職種では、主に次のようなスキルが求められます。
- プログラミングやデータベースの知識(Python、SQL など)
- ネットワークやクラウド技術の理解(AWS、Cisco など)
- 情報セキュリティの知識(個人情報保護、サイバーセキュリティ)
- プロジェクト管理能力(自治体のITプロジェクトの進行管理)
しかし、公務員の情報系職種には課題もあります。例えば、予算の関係で最新技術の導入が遅れやすいことや、IT専門職が少なく負担が大きいことが挙げられます。そのため、民間企業と連携したり、専門研修を受けたりして、スキルを磨くことが重要になります。
行政のデジタル化が進む中で、情報系公務員の役割はますます重要になっています。今後、より多くのIT専門人材が求められるでしょう。
IT人材が公務員として活躍するメリット

IT業界で働く人が公務員に転職すると、さまざまなメリットがあります。安定した環境でスキルを活かしながら、行政のデジタル化に貢献できる点が魅力です。
IT人材が公務員になるメリット
- 雇用の安定
景気の影響を受けにくく、長期的に働きやすい - ワークライフバランスの向上
残業が少なく、休暇も取りやすい - 社会貢献ができる
市民の生活を便利にするシステムを作れる
また、公務員には研修制度があり、ITスキルを学び続けられる環境があります。最新技術の導入が遅れることはありますが、長期的にシステムを改善できるため、大規模なプロジェクトに関わることも可能です。
IT人材にとってのデメリットも理解しよう
- 給与が民間より低め
特に若手のうちは収入が伸びにくい - 技術革新のスピードが遅い
最新技術をすぐに導入するのが難しい - ルールが多い
行政の決まりごとに沿って業務を進める必要がある
これらの点を考慮しながら、自分のキャリアプランに合うかを検討することが大切です。安定した環境で社会に貢献したいIT人材には、公務員という選択肢は魅力的なものになるでしょう。
IT職の給与とキャリアパスは?

IT職の給与やキャリアパスは、安定した収入と働きやすさが魅力ですが、民間企業と比べると昇給のスピードや給与水準には差があります。公務員として長く働くことを前提に、どのような成長ができるのかを理解しておくことが大切です。
公務員IT職の給与の目安
公務員の給与は年齢や経験によって変わりますが、一般的な目安は以下の通りです。
| キャリア | 年収の目安 |
|---|---|
| 新卒(1~3年目) | 約350万~450万円 |
| 中堅(4~10年目) | 約450万~600万円 |
| 管理職(10年以上) | 約600万~800万円 |
給与は安定しており、ボーナス(期末・勤勉手当)も年2回支給されます。ただし、民間のIT企業と比べるとスタート時の給与は低めです。
公務員IT職のキャリアパス
公務員IT職には以下のようなキャリアの流れがあります。
- 新人期(1~3年目)
- 行政システムの運用や簡単な業務支援を担当
- 公務員としての基礎を学ぶ
- 中堅期(4~10年目)
- システム開発やITプロジェクトの管理に関わる
- 新しい技術の導入を検討する立場になる
- 管理職(10年以上)
- IT戦略の立案や全体の統括を担当
- 他部署と連携し、行政のDX(デジタル化)を推進する
IT職は、短期間で高収入を得る職業ではありませんが、長期的に安定した収入と働きやすさを求める人には適しています。特に、社会貢献を重視するIT人材にとっては魅力的なキャリアパスといえるでしょう。
公務員のIT人材として働くためのポイント

- システムエンジニアと公務員、どっちが向いている?
- ITエンジニアが公務員試験に合格するポイント
- IT人材の展望と求められるスキル
- 公務員のIT人材として働くためのポイント(まとめ)
システムエンジニアと公務員、どっちが向いている?
ITエンジニアと公務員には、それぞれ異なる働き方や求められるスキルがあります。どちらが向いているのかを判断するには、自分の価値観やキャリアの優先順位を整理することが大切です。
エンジニアに向いている人
エンジニアは、技術力を活かしてシステム開発やデータ分析を行う職種です。向いているのは以下のような人です。
- 最新技術を学び続けるのが好き
- スピード感のある仕事がしたい
- 高収入を目指したい
- 自分のアイデアを形にするのが得意
民間のIT企業では、能力次第で給与が大きく上がる可能性があります。しかし、納期のプレッシャーが強く、残業が多くなりやすい傾向もあります。
公務員に向いている人
公務員は、安定した環境で長く働くことができる職業です。以下のような人に向いています。
- 安定した仕事を求めている
- 社会貢献に関心がある
- チームワークを重視する
- 規則に沿って働くのが得意
公務員のIT職は、新しい技術を導入するよりも、運用やセキュリティ管理が中心となることが多いです。また、給与は民間企業より低めですが、福利厚生が充実しています。
どちらを選ぶべきか?
どちらが向いているかは、自分の働き方の希望によります。技術を磨きながらキャリアアップを目指したいならエンジニア、安定した環境で社会貢献をしたいなら公務員が向いているでしょう。自分の価値観と照らし合わせて、最適な選択をしましょう。
ITエンジニアが公務員試験に合格するポイント
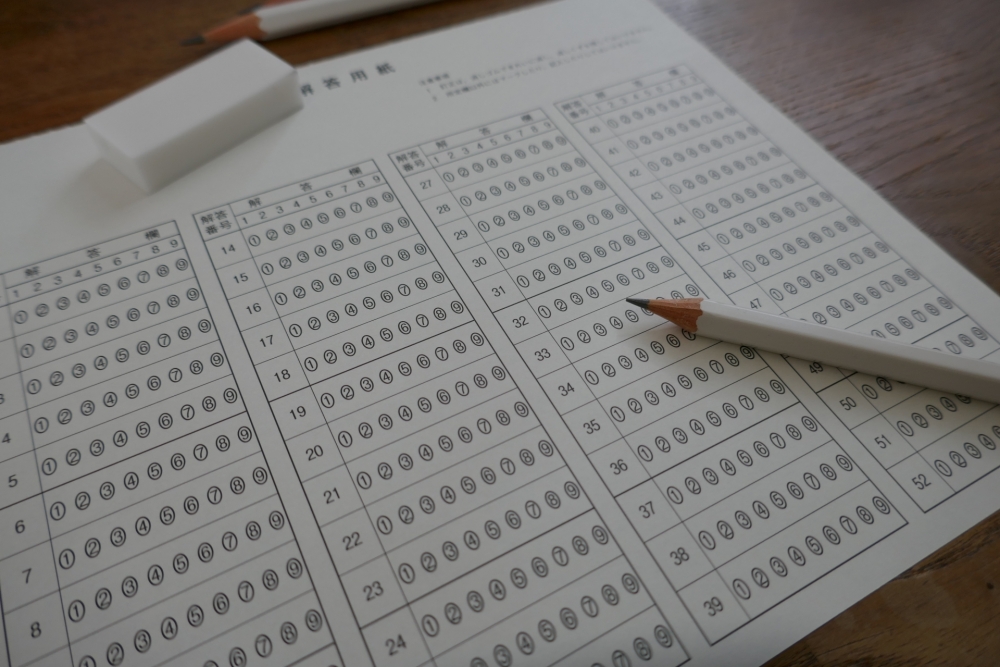
ITエンジニアが公務員試験に合格するためには、計画的な勉強と面接対策が欠かせません。民間企業とは異なる視点での準備が必要となるため、早めに対策を始めることが大切です。
試験対策のポイント
公務員試験は筆記試験と面接試験があり、ITエンジニア向けの採用試験でも一般教養が問われます。以下の勉強方法が有効です。
- 専門試験の対策
情報処理技術者試験の知識が活かせるため、基本情報技術者や応用情報技術者の内容を復習する - 教養試験の学習
数学・国語・時事問題など、広範囲の知識をカバーする - 論文対策
行政のデジタル化や情報セキュリティについて論理的に書けるようにする
特に、情報系の公務員試験ではIT技術と行政の関わりを理解しているかが重要になります。
面接対策のポイント
公務員試験の面接では、ITスキルを行政でどう活かせるかを明確に伝えることが大切です。以下の点を意識しましょう。
- 行政の課題とITの役割について意見を持つ
- チームでの業務経験をアピールする
- 長く働く意志を伝える
特に、「なぜ民間ではなく公務員を選んだのか?」という質問はとても多いです。社会貢献や安定性を重視した理由を整理しておきましょう。
効率的な学習方法
公務員試験は範囲が広いため、計画的に勉強することが重要です。
- オンライン講座や参考書を活用
- 過去問を解いて出題傾向をつかむ
- スケジュールを立てて毎日少しずつ勉強する
特に論文試験や面接は、独学では難しいため、模擬試験や講座を利用するとよいでしょう。
IT人材の展望と求められるスキル

行政のデジタル化が進む中で、IT人材の役割はますます重要になっています。ITを活用して行政サービスの向上を図るため、多様なスキルが求められています。
今後のIT人材の展望
公務員のIT職は、以下のような分野での活躍が期待されています。
- 行政のデジタル化
オンライン申請や電子決済の導入を進める - データ活用
住民データを分析し、より良い行政サービスを提供 - セキュリティ強化
サイバー攻撃対策や個人情報の管理を徹底 - AI・クラウドの活用
最新技術を行政システムに取り入れる
これらの施策によって、行政の効率化や住民の利便性向上が期待されています。
求められるスキル
IT人材には、以下のようなスキルが必要とされます。
- IT基礎知識
システム設計やデータベース管理の理解 - プロジェクト管理
外部業者と協力し、システム導入を進める能力 - セキュリティ知識
行政機関の情報を守るための専門知識 - データ分析力
ビッグデータを活用し、行政の課題を解決
今後は、より高度な技術を活用しながら、行政のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進できる人材が求められます。技術の進化に対応できるよう、学び続ける姿勢も重要です。
公務員のIT人材として働くためのポイント(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 地方自治体ではIT人材の需要が高まっている
- 行政サービスのデジタル化が進んでいる
- IT人材はシステム運用やセキュリティ管理を担当する
- データ分析を活用し、住民サービスの向上を図る
- 公務員のIT職は専門職の枠が少なく、競争率が高い
- 民間企業に比べて給与は低めだが、安定した雇用がある
- 最新技術の導入が遅れる課題がある
- 政府は「デジタル庁」を設立し、自治体のIT化を支援している
- 公務員の情報系職種にはシステムエンジニアやデータアナリストが含まれる
- IT人材にはプログラミングやセキュリティの知識が求められる
- 予算の制約で最新技術の活用が難しい場合がある
- 公務員はワークライフバランスが取りやすい
- 社会貢献を重視する人にとって魅力的なキャリアパスがある
- 公務員のIT職は給与の昇給スピードが遅い
- デジタル化が進むにつれ、IT人材の役割はさらに重要になる