公務員として働く中で、体調をくずして病気休暇を取らなければならない場面もあります。その際に気になるのが、病気休暇中の過ごし方や注意点ではないでしょうか。
特に、休暇中に旅行をしてもよいのか、どこまでの行動が許されるのかを知っておくことは大切です。また、必要に応じて提出する診断書の書き方やタイミングについても、あらかじめ理解しておくと安心できます。
一方で、制度の正しい使い方を知らないまま行動すると、不正と受け取られてしまうリスクもあります。過ごし方を誤れば、思わぬデメリットが生じることもあるため、注意が必要です。
この記事では、公務員が病気休暇中にどう過ごせばよいかをわかりやすく解説します。信頼を失わず、心と体をしっかり回復させるためのポイントを紹介していきます。
- 病気休暇中に自宅で快適に過ごすための工夫がわかる
- 許可なく旅行や外出をするリスクが理解できる
- 不正と疑われないための報告や証拠の重要性がわかる
- 診断書の書き方と提出のタイミングが理解できる
公務員の病気休暇中の過ごし方と基礎知識
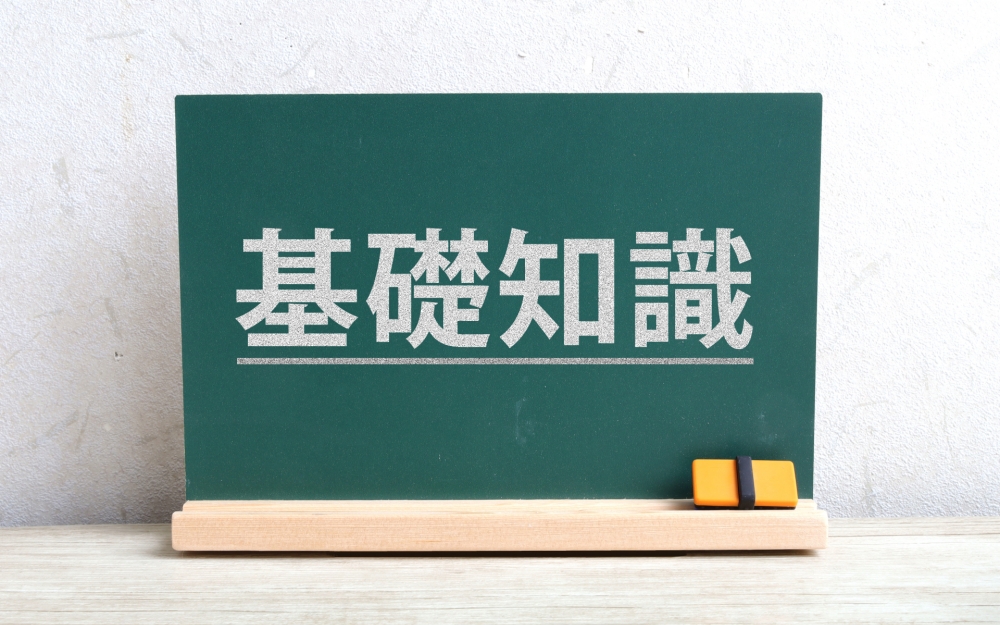
- 病気休暇の給料は何割ですか?
- 診断書の書き方と注意点
- 1週間の病気休暇|正しい取得手順
- 病気休暇中にしてはいけないことは?
病気休暇の給料は何割ですか?
病気休暇を取ると、給料はどうなるのか気になる人も多いでしょう。結論から言えば、病気休暇のあいだは、給料が全額もらえるしくみになっています。これは90日までの期間が対象で、そのあいだの生活費が保障されている制度です。
たとえば、月に30万円もらっている人が病気休暇を使っても、そのままの金額が支払われます。ただし、これには上限があり、90日をこえると「病気休職」という別の制度に変わり、給料は8割に下がります。
また、ボーナスについても注意が必要です。期末手当は減らされませんが、勤勉手当は30日以上休むと減額されます。具体的には、60日休んだ場合、手当が30%ほど減るケースもあります。
さらに、通勤手当や住居手当なども、1か月丸ごと出勤しないと支給されない可能性があります。病気休暇中も経済的には守られていますが、一定の条件を超えると変化が出てくるため、事前に職場の人事担当に確認することが大切です。
診断書の書き方と注意点

病気休暇を8日以上連続で取る場合、職場に提出する診断書が必要になるケースが多いです。これは、療養の必要性を職場に伝えるための書類で、病名や休養期間などが明記されます。
まず病院で診察を受けた際に、「公務員の病気休暇に使う診断書が必要です」と医師にはっきり伝えることが大切です。職場で指定された書き方や用紙があるときは、それを持参するとスムーズに依頼できます。
診断書には、氏名・病名・診察日・休養の必要な期間・医療機関名・医師の名前と印がしっかり書かれている必要があります。たとえば「○○のため、〇月〇日から〇月〇日まで療養を要する」といった表現が一般的です。
また、提出のタイミングも重要です。特に長期間の休みになると、事前の申請や報告が求められます。診断書の発行には数日かかる場合もあるため、早めに申請すると安心です。書類が不備なく整っていれば、職場とのやりとりもスムーズに進むでしょう。
1週間の病気休暇|正しい取得手順

公務員が病気やけがで1週間ほど仕事を休む場合、正しい手順で病気休暇を申請することが求められます。まず、体調に異変を感じたら早めに職場の上司に連絡し、「病気休暇を取りたい」と伝えましょう。
1週間以内の休暇であれば、診断書がなくても大丈夫な場合が多く、病院の領収書やお薬手帳のコピーなどで代用できます。ただし、地方公務員は、条例によって日数が違いますので、人事担当者に確認しましょう。
病気休暇申請書は、休みが終わったあとに提出することも可能です。ただ、申請が遅れると手続きが複雑になる場合があるため、早めの提出をおすすめします。休みの間も体調の変化があれば、職場に簡単な報告をしておくと安心です。
また、1週間の中に土日が入っている場合でも、病気休暇はカウントされます。たとえば火曜日から月曜までの7日間休んだ場合、土日も含めて1週間とされます。正しい書類とスケジュール管理で、安心して療養できるようにしましょう。
病気休暇中にしてはいけないことは?

病気休暇は、公務員が体調を回復するために使える大切な制度です。ただし、休んでいる間にしてはいけない行動もあります。これを守らないと、信用を失ったり、処分を受けたりする場合があります。
まず絶対にやってはいけないのが、副業やアルバイトです。休んでいるのに働くのは、公務員のルール違反です。また、旅行や遊びに行くなど、体を休めていないと見なされる行動も問題になります。たとえ気分転換のつもりでも、状況によっては不適切と判断されます。
SNSへの投稿にも注意が必要です。休暇中に楽しそうな写真や動画を投稿すると、「本当に具合が悪いのか?」と疑われるおそれがあります。発覚のきっかけになるのは、同僚や知人の通報、またはネット上での情報発信が多いです。
不適切な行動が見つかると、減給や停職などの処分を受ける可能性もあります。休んでいるあいだは、無理をせず医師の指示に従い、体調回復を最優先にした生活を送りましょう。
公務員の病気休暇中の過ごし方と注意点

- 病気休暇中に旅行はOK?
- 病気休暇の過ごし方
- 病気休暇を取得するデメリットと対策
- 不正を避ける心得
病気休暇中に旅行はOK?
病気休暇中に旅行へ行けるかは、病気の内容や医師の指示によって変わります。すべての旅行がダメなわけではありませんが、何でも自由にしてよいわけでもないので注意が必要です。
たとえば、うつ病など精神的な不調で気分転換が必要な場合には、近くへの外出や短い旅行が治療の一部になる場合もあります。ただし、医師から「外出してもよい」という言葉をもらっているかが大切です。自己判断だけで出かけるのは危険です。
また、職場へ旅行の予定を伝えておくことも大事なポイントです。許可を取らずに外出すると、後でトラブルになるかもしれません。とくに宿泊をともなう旅行は、体への負担もあるため、慎重に判断する必要があります。
病気休暇の過ごし方|5つのコツ

病気休暇を使ってしっかり体を休めるためには、家での過ごし方がとても大切です。うまく療養できれば、回復も早くなり、職場復帰もスムーズに進みます。ここでは、病気休暇中におすすめしたい5つの工夫を紹介します。
まず1つ目は「生活リズムを整える」ことです。朝は決まった時間に起きて、夜も同じ時間に寝るようにすると、心と体が落ち着きやすくなります。
2つ目は「体に合った軽い運動」です。散歩やストレッチなどを少しずつ取り入れると、気分もリフレッシュできます。
3つ目は「栄養のある食事」をとることです。インスタント食品ばかりに頼らず、できるだけ野菜やたんぱく質をとるようにしましょう。
4つ目は「趣味の時間を持つ」ことです。読書や音楽など、自分が楽しめることに触れると気持ちが明るくなります。
最後の5つ目は「医師との連絡をしっかり続ける」ことです。回復の様子や不安があれば、早めに相談すると安心です。無理せず、心と体をいたわる時間にしましょう。
病気休暇を取得するデメリットと対策

病気休暇は大切な制度ですが、長く使うと仕事への影響も出てきます。特に心配されるのが、昇進や人事評価への影響です。ここではそのリスクと、あらかじめできる対策を紹介します。
まず気をつけたいのは、長期での休暇が続いた場合です。職場によっては、昇格の時期がずれる場合があります。「また休むのでは?」と考えられてしまい、大きな仕事を任されにくくなるケースもあります。
これを防ぐには、体調が悪くなったときに早めに休むことが重要です。短い休みであれば、評価への影響も少なくなります。そして、病状や復帰の目安を職場にきちんと伝えることも信頼を守るポイントです。
さらに、復職したあとにできるだけ早く仕事に慣れる努力を見せましょう。少しずつでも実績を積み上げることで、信頼は回復しやすくなります。必要があれば、医師と相談して短時間勤務から始めるのもひとつの方法です。
不正を避ける心得

病気休暇は体を休める大切な制度ですが、使い方を間違えると「不正ではないか」と思われるおそれがあります。疑われないためには、きちんとした証明と報告を意識する必要があります。
まず意識すべきは、診断書や病院の領収書をしっかりと保管することです。提出が終わっても、コピーなどを自分で取っておくと安心です。とくに8日以上の休みや、1か月に5日以上休むときは証明書が必ず必要になります。
次に大切なのは、職場への報告です。病状や今の体の様子、復帰の見通しなどを、できるだけ分かりやすく伝えましょう。書面やメールを使えば、あとで「言った・言わない」のトラブルも防げます。
また、療養中の行動にも注意がいります。たとえ回復していても、遊びに出かけた様子をSNSなどに投稿すると誤解を生みやすくなります。あとから「本当に病気だったのか」と疑われるきっかけにもなりかねません。
安心して休むためには、ルールを守り、証拠と報告をそろえることが大切です。信頼を守る行動が、自分の働きやすさにもつながっていきます。
公務員の病気休暇中の過ごし方(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 病気休暇は最長90日まで全額給料が支給される
- 90日を超えると病気休職となり給料は8割に下がる
- 勤勉手当は30日以上の休暇で減額の可能性がある
- 通勤手当や住居手当は出勤実績がないと支給されにくい
- 病気休暇中でも医師の許可があれば外出や短期間の旅行は可能
- 外出や旅行前には職場に報告・相談することが望ましい
- SNSへの投稿は誤解を招くため控えるべき
- 軽い運動や散歩を取り入れると気分転換になり回復に役立つ
- 決まった時間に起きて寝る生活リズムを保つことが大切
- 栄養バランスのとれた食事を心がけることが必要
- 自分が楽しめる趣味に時間を使うと精神的な回復が早まる
- 医師との連絡は継続し、体調変化を共有するようにする
- 体調が悪化する前に短期で休むことで評価への影響を減らせる
- 診断書や病院の証明書は必ず保存しておくべき
- 職場への報告は文書やメールで記録に残すことが望ましい










