近年のAI技術の進化により、多くの仕事が自動化される中で、公務員の仕事もAIに取って代わられるのではと不安に感じている人もいるでしょう。
特に、事務処理やデータ入力などの業務は、AIが得意とする分野であり、実際に一部ではすでに代替が進んでいます。この流れの中で、給料が下がるのではないか、リストラの可能性はあるのかと心配する声も聞かれます。
一方で、公務員のすべての仕事がなくなるわけではありません。住民対応や制度づくりのような、AIではできない業務も多く残っています。つまり、今後は「AIに代われる業務」と「人にしかできない業務」に分かれていく時代が到来しています。
この記事では、AI導入による変化、公務員の仕事の今後、そして生き残るために必要なスキルについてわかりやすく解説します。
- AIにより公務員の一部業務がなくなる理由と背景
- 公務員の仕事でもAIではできない業務があること
- 将来的に公務員の給料が下がる可能性があること
- 公務員がリストラされるリスクや今後求められるスキル
AIで公務員の業務がなくなる時代に突入するのか?

AIが進むとなくなる職業は?
AIの進化により、今後なくなると言われている職業が増えています。中でも、同じ作業をくり返す仕事や、手順が決まっている仕事は特に代わりやすいです。
理由は、AIやロボットが「速く」「正確に」作業をこなせるからです。人間よりもミスが少なく、休まずに働けるため、企業もAIを使いたくなります。
例えば以下のような仕事が挙げられます。
- データ入力や事務作業
- 銀行や役所の窓口対応
- 工場での組み立てや検品
- レジ打ちや切符の販売
これらはすでにAIやロボットが一部を担当しており、今後さらに広がると考えられています。
ただし、すべての仕事がすぐに消えるわけではありません。人との会話や判断が必要な職業は、AIでは対応しきれないこともあります。
AIの登場でなくなる職業もあれば、逆にAIを使いこなす新しい仕事も生まれています。変化に合わせてスキルを学ぶことが、これからはより大切になるでしょう。
公務員の将来は仕事がなくなるのか?

公務員という職業が、将来すべてなくなる可能性は低いです。しかし、一部の業務はAIによって変わっていくと考えられています。
たしかに、データの入力や書類のチェックなど、同じ作業をくり返す仕事はAIが得意とする分野です。これらの仕事はすでにAIで自動化されつつあり、職員の数が少なくても回るようになるかもしれません。
一方で、すべての公務員がいなくなるわけではありません。理由としては、住民の相談にのったり、災害時に現場で指示を出したりするなど、人間にしかできない仕事も多くあるからです。
また、国や地域のルールをつくる業務や、複雑な課題に対応するには、人の判断が必要です。AIにはまだ感情や柔軟な対応ができません。
つまり、公務員の仕事が全部なくなるというよりは、「なくなる業務」と「残る業務」に分かれていくという流れです。将来も公務員が必要とされる場面はあるでしょう。
何の業務がAIに代替される?

現在、公務員の仕事の一部がAIに代わられはじめています。すべてではありませんが、くり返しの多い作業や、決まったルールで進める仕事はAIに任せやすいです。
AIによって代替されやすい主な業務は以下のとおりです。
- 書類のチェックやデータ入力
- 住民からのよくある問い合わせへの対応(チャットボット)
- 申請内容の分類や処理
- 会議の議事録作成や文書整理
例えば、以前は人が30分かけて処理していた申請書も、AIなら数秒で終わる場合があります。これにより、時間の節約だけでなく、ミスも少なくなります。
ただし、すべての業務が代わるわけではありません。住民対応など、人とのやりとりが必要な業務は、今のところ人間にしかできません。
公務員の仕事はAIと役割を分け合う時代になってきています。AIに代われる仕事は今後も増えると見られており、職員はより人間らしい仕事に力を入れる必要があるでしょう。
AI導入よるメリットとデメリット

AIを公務員の業務に取り入れると、良い点もあれば注意が必要な点も出てきます。便利になる一方で、新たな負担や問題も出てくるのです。
まず、AI導入のメリットは以下のとおりです。
- 単純作業をAIが代行することで、業務の効率アップ
- ミスの減少とスピードの向上
- 時間に余裕ができ、住民対応や企画などに集中できる
しかし、デメリットも存在します。
- 残った職員の業務がかえって重くなる場合がある
- AIシステムを使いこなすためのスキル習得が必要
- 人との関わりが減り、やりがいを感じにくくなることもある
例えば、AIに任せる部分が増えると、職員一人に対する責任が重くなるケースがあります。また、操作ミスやシステムトラブルが起きたときの対応も必要です。
AI導入にはメリットとデメリットの両面があります。うまく使い分けていくためには、職員自身がAIの特性を理解し、使いこなす準備が必要でしょう。
将来の給料が下がる可能性はある?
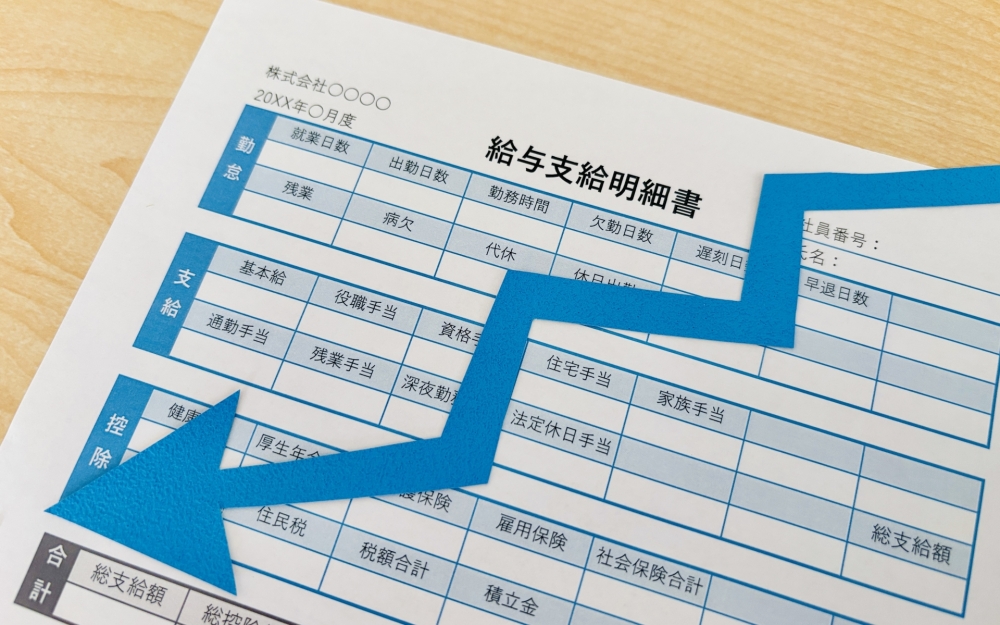
将来、公務員の給料が下がるおそれがあります。特に、AIの導入や業務の見直しによって、人数を減らしたり、働き方を変えたりする動きが進んでいるからです。
公務員の給料が下がるリスクには、次のような背景があります。
- 少子高齢化で税金が減る
- 国や市の財政がきびしくなる
- 人を減らして、仕事をAIに任せる流れが強まっている
たとえば、ボーナスを数%カットして財源を確保する自治体も見られます。また、仕事量が増えるのに給料は上がらない、という不満も出てきています。
一方で、働き方を見直して、効率よく仕事をこなせば評価される制度に変わる可能性もあります。ただし、そのためにはスキルアップや新しい働き方に慣れる必要があります。
今後の公務員には「安定しているから安心」とは言えない時代が来るかもしれません。今のうちに変化に備える準備が大切です。
AIで公務員の業務がなくなる時代でも求められる人材とは

AI導入で公務員に求められる新スキル
AIの導入が進む中で、公務員にも新しいスキルが求められるようになっています。今までのように、同じ仕事を同じやり方でこなすだけでは通用しなくなる時代が近づいています。
具体的に求められるスキルには以下のようなものがあります。
- デジタル機器やAIツールを使いこなすスキル
- データの読み取りや分析力
- システムや作業の流れを改善する考え方
- 自分の考えを分かりやすく伝える力
これらを身につければ、AIと協力しながら質の高い仕事ができるようになります。逆に、これらがないと「効率が悪い人」とみなされてしまい、仕事を続けにくくなるおそれもあります。
さらに、給与の決め方も成果やスキル重視に変わっていく可能性があります。ただ「がんばった」だけでは評価されない時代に備えるためにも、今から学び始めるのがおすすめです。
AI導入によってリストラの可能性はある?

公務員がAIによってリストラされるのではと心配する声もあります。ただし、すぐに大量の人が職を失うわけではありません。法律で公務員の身分は守られており、急な解雇は起きにくいからです。
しかし、これから先の働き方は確実に変わっていくでしょう。AIが得意な仕事をどんどん自動化し、人がやる業務は変わっていきます。そこで大切になるのが「ITスキル」や「デジタルリテラシー」です。
具体的には
- Excelやクラウドツールを使いこなす力
- Zoomなどのオンライン会議ツールの操作
- セキュリティや情報の扱いに関する知識
- 基本的なプログラミング(RPAやVBAなど)
これらを身につけていれば、AIと一緒に働ける「必要な人材」として評価されやすくなります。今後は、学ぶ姿勢そのものが生き残るためのカギになります。
AIではできない自治体の業務

公務員の中には、AIではまだ対応が難しい業務が多くあります。特に、「制度づくり」や「住民への対応」は、専門知識と柔軟な考え方が必要なため、人の手で行う必要があります。
たとえば、以下のような業務です。
- 新しい法律やルールを考える制度設計
- 地域ごとの課題に合わせた政策の立案
- 一人ひとりの事情にあわせた住民サポート
- 緊急時の判断と連携(災害対応など)
これらの仕事には、細かな状況を読み取ったり、多くの関係者と話し合ったりする力が求められます。また、社会の動きに合わせて柔軟に考え直す必要もあるため、単純な計算や作業では済みません。
AIはあくまで「道具」であり、人が考えたルールの中でしか動けません。そのため、今のところこうした業務は人間の公務員が中心となって進めていく必要があります。
AIが絶対にできない仕事は何ですか?

AIにはできない仕事も多くあります。その多くに共通しているのは、「人の気持ちを感じ取る力」や「新しい考えを生み出す力」が必要な仕事です。AIはルールにしたがって動くため、思いやりや創造力を使う仕事には向いていません。
具体的には以下のような仕事があります。
- カウンセラー
相手の感情をくみ取って助ける - 教師
子どもの成長に合わせて教え方を変える - アーティスト
自分だけの表現で作品を作る - 医師
言葉にできない症状や気持ちを読み取る - 起業家
誰も思いつかないアイデアを形にする
これらの仕事には、人と人との深い関わりや、その場の空気を読む力が求められます。AIでは、そのような判断や対応はまだ難しいのが現実です。
今後も、人ならではの力が必要な仕事はなくならないでしょう。AIと上手に役割を分けることが大切になります。
AIで公務員の業務がなくなる時代に突入するのか?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 単純作業や決まった手順の業務はAIに代替されやすい
- 公務員の事務作業やデータ入力はAI導入が進んでいる
- 窓口対応や書類チェックもAIが一部を担いはじめている
- AIの導入で業務効率が上がり、時間やコストの削減が可能
- 職員数が減っても仕事が回る体制が整いつつある
- 一方で、住民対応や災害時の現場判断は人間にしかできない
- 制度づくりや政策立案はAIには困難である
- AIでは柔軟な対応や感情をくんだ判断が難しい
- 公務員の仕事は「AIに代わる業務」と「残る業務」に分かれていく
- AI導入により、公務員にも新しいスキルが求められる
- デジタル機器やデータ分析に強い人材が重宝される
- ITスキルがなければ仕事の継続が難しくなる場合もある
- 給料やボーナスが見直される自治体も出てきている
- 職員の仕事量が逆に増えるリスクもある
- AIができない業務に特化することが今後の生き残り策となる


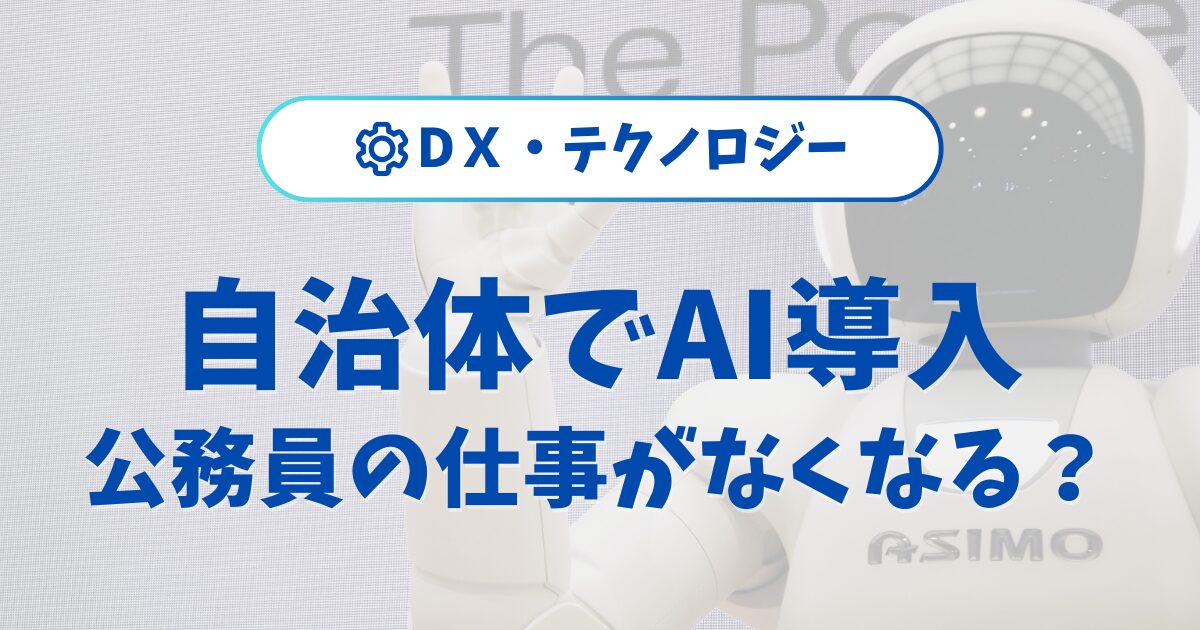
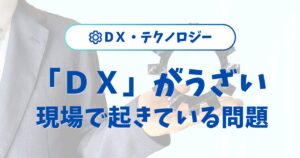
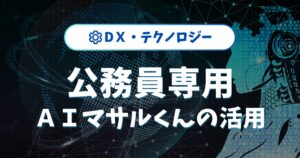
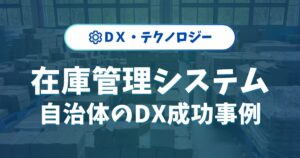

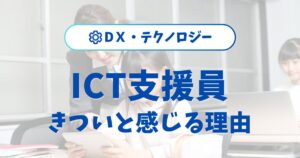
-300x158.jpg)