会計年度任用職員として働いていると、病気や家庭の事情で「休職したいけれど、そもそも制度はあるのだろうか」と不安に思うことがあるかもしれません。
会計年度任用職員は休職できますか?という基本的な疑問から、休職期間や無給になるのかといった経済的な心配、さらには欠勤が多い場合の処分や契約更新への影響まで、悩みは尽きないものです。
この記事では、そうした不安や疑問を解消するため、会計年度任用職員の休職制度について、その利用条件から手続き、そして知っておくべきリスクまで、網羅的に解説します。
- 会計年度任用職員の休職制度の有無と利用条件がわかる
- 休職中の給与や傷病手当金の仕組みを理解できる
- 欠勤や休職が人事評価や契約更新に与える影響を把握できる
- 休職から復職までの具体的な流れを知ることができる
会計年度任用職員の休職制度|利用条件から手続きまで

- 会計年度任用職員は休職できますか?制度の有無と条件
- 常勤職員との休職制度の違いを比較
- 会計年度任用職員の病気休暇の期間は?取得の流れも解説
- 会計年度任用職員の休職期間と手続き【申請方法まとめ】
- 休職からの復職に必要な手続きとは
- 会計年度任用職員の休職中は無給?傷病手当金はもらえる?
会計年度任用職員は休職できますか?制度の有無と条件

結論として、会計年度任用職員にも休職制度は存在します。地方公務員法が適用されるため、正規職員と同様に、病気や育児、介護などを理由とした休職が認められる場合があります。
ただし、その適用には一定の条件が伴います。最も大きな原則は、休職が「任期内」に限られるという点です。会計年度任用職員の任期は多くの場合1年単位であるため、休職期間も最長でその年度の末日までとなります。
加えて、自治体によっては「6か月以上の任用期間があること」といった、休職制度を利用するための独自の条件を設けている場合があります。このため、ご自身の勤務先の条例や規則を事前に確認することが非常に大切になります。
常勤職員との休職制度の違いを比較
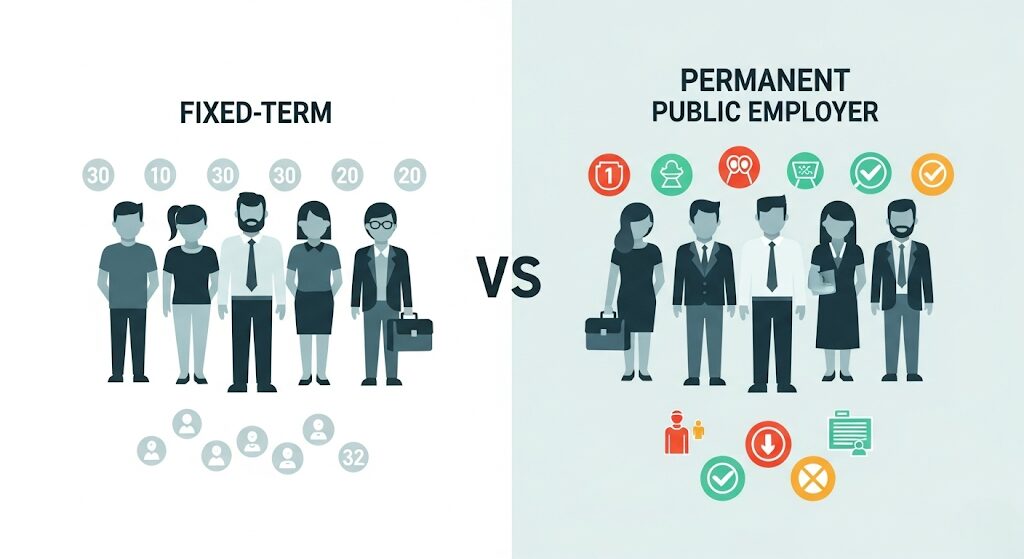
会計年度任用職員の休職制度は、常勤職員(正規職員)の制度と比較していくつかの重要な違いがあります。最も大きな相違点は「任期」と「休職期間の上限」です。
以下の表で主な違いをまとめました。
| 項目 | 会計年度任用職員 | 常勤職員(正規職員) |
| 任期 | 原則1年(年度ごと) | 定年まで継続 |
| 休職期間の上限 | 任期内(原則年度末まで) | 数年単位での長期休職も可能 |
| 休職中の給与 | 原則無給(例外あり) | 条例に基づき一部支給される場合がある |
| 復職の前提 | 任期内での復職が原則 | 長期療養後も復職可能 |
会計年度任用職員の休職は、年度ごとの契約という雇用形態に大きく影響されます。常勤職員のように数年にわたる休職は想定されておらず、あくまで現在の任期内での対応が基本となる点を理解しておく必要があります。
会計年度任用職員の病気休暇の期間は?

休職を考える前に、まずは「病気休暇」制度の利用を検討するのが一般的です。病気休暇は、比較的短期間の療養を目的とした休暇で、年次有給休暇とは別に付与されます。
近年、処遇改善が進み、多くの自治体で年間10日程度の「有給」の病気休暇が設けられるようになりました。ただし、この日数は自治体によって異なり、また、付与されるためには「6か月以上の任期がある」といった条件が定められている場合があります。
病気休暇取得の流れ
- 上司への連絡
体調不良を感じたら、速やかに上司に連絡し、状況を報告します。 - 医療機関の受診:
7日を超える休暇を取得する場合は、原則として医師の診断書が必要となります。7日以内であれば、受診した際の領収書などで認められることもあります。 - 申請書の提出
自治体所定の申請書に必要事項を記入し、診断書などの証明書類を添えて提出します。
有給の病気休暇を使い切っても療養が必要な場合は、無給の病気休暇や年次有給休暇を利用するか、長期にわたる場合は後述の休職制度へ移行することになります。
休職期間と手続き

有給の病気休暇などを使い切っても、なお長期の療養が必要な場合に利用するのが「休職」制度です。
休職が認められる期間は、前述の通り、任期の範囲内というのが大原則です。自治体によっては「任期内かつ最大90日まで」といった具体的な上限を設けているケースもありますが、実質的には任期満了日(多くは3月31日)が上限となります。
休職申請の具体的な手続き
休職を申請する際の手続きは、一般的に以下の流れで進みます。
- 上司・人事担当への相談
医師から長期療養の必要性を告げられた時点で、まずは上司や人事課に相談します。 - 必要書類の準備
休職の申請には、医師の診断書が不可欠です。それに加え、自治体が定める「休職願」や「承諾書」などの書類を作成する必要があります。 - 書類の提出と審査
全ての書類を揃えて人事担当部署に提出します。提出された診断書などに基づき、任命権者(市長や教育長など)が休職の可否と期間を最終的に決定します。 - 発令
休職が承認されると、「休職を命ずる」という内容の辞令が交付され、正式に休職期間が開始されます。
これらの手続きには時間がかかる場合があるため、長期療養が必要だと判断されたら、できるだけ早く準備を始めることが望ましいです。
休職からの復職に必要な手続きとは

休職期間が満了し、職場に復帰する際には、再び職務を遂行できる状態に回復していることを証明する必要があります。
最も重要なのが、医師による「復職可能」である旨を記した診断書の提出です。休職を開始した時と同様に、医師の客観的な判断が求められます。この診断書を人事担当部署に提出し、内容が確認された上で、任命権者が復職を決定します。
自治体によっては、産業医との面談が設定される場合もあります。これは、本人の健康状態をより詳しく把握し、復帰後の業務に支障がないか、また、どのような配慮が必要かを確認するために行われます。スムーズな職場復帰のためにも、これらの手続きは誠実に対応することが大切です。
休職中は無給?傷病手当金はもらえる?

休職する上で最も気になるのが、経済的な問題ではないでしょうか。会計年度任用職員が病気やケガで休職する場合、その期間中の給与は原則として「無給」となります。
これは「ノーワーク・ノーペイの原則」に基づくもので、勤務していない期間の給与は支払われないのが基本です。ただし、この経済的な負担を支えるためのセーフティネットが存在します。
それが、健康保険から支給される「傷病手当金」です。傷病手当金は、以下の4つの条件をすべて満たした場合に受給できます。
- 業務外の病気やケガによる療養のための休業であること
- 働くことができない状態であると医師が証明していること
- 連続する3日間を含み、4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
支給額は、おおよその給与の3分の2に相当する額で、最長で1年6か月にわたって受給が可能です。休職中の生活を支える非常に重要な制度ですので、申請方法や必要書類については、勤務先の人事担当や加入している健康保険組合に必ず確認しましょう。
会計年度任用職員の休職・欠勤のリスク|処分と契約更新

- 会計年度任用職員で欠勤が多いと評価や更新にどう響く?
- 会計年度任用職員の欠勤でどんな処分がある?具体例解説
- 会計年度任用職員がクビになる理由は何?分限免職とは
- 休職や欠勤に関するよくある質問
欠勤が多いと評価や更新にどう響く?

やむを得ない理由があるとはいえ、欠勤が多い状況は、人事評価や次年度の契約更新に影響を与える可能性があります。
会計年度任用職員にも、常勤職員と同様に人事評価制度が適用されます。この評価は、勤勉手当(ボーナス)の支給額や、次年度も再度任用されるかどうかの判断材料となります。
勤務態度は評価の重要な項目の一つであり、正当な理由のない欠勤や頻繁な遅刻・早退は、「勤務実績が良好でない」と判断される一因になり得ます。
特に、無断欠勤を繰り返すことは、職場からの信頼を著しく損なう行為です。たとえ有給休暇や病気休暇の範囲内であっても、その頻度や業務への影響度合いによっては、契約更新の際に慎重な判断が下される可能性があることは否定できません。
会計年度任用職員の欠勤でどんな処分がある?具体例解説

欠勤が服務規律上の問題と見なされた場合、懲戒処分が下されることがあります。地方公務員法に基づく懲戒処分には、重い順に「免職」「停職」「減給」「戒告」の4種類があります。
人事院が示す指針によれば、正当な理由のない欠勤に対しては、以下のような処分が標準例とされています。
- 10日以内の欠勤: 減給または戒告
- 11日以上20日以内の欠勤: 停職または減給
- 21日以上の欠勤: 免職または停職
これは国家公務員の基準ですが、地方公務員である会計年度任用職員にも同様の考え方が適用されるのが一般的です。
例えば、無断欠勤を繰り返した職員に対し、1か月間の給与を10%減額する「減給」処分が下された事例もあります。処分の判断は、欠勤の理由や常習性、職務への影響などを総合的に考慮して行われます。
会計年度任用職員がクビになる理由は何?分限免職とは

最も重い処分である「クビ」は、法的には「分限免職」と呼ばれます。これは、職員の勤務実績や適格性に問題がある場合に、本人の意に反して職を解く措置です。
分限免職に至る主な理由としては、「勤務実績が著しく不良である場合」や「心身の故障により、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合」などが地方公務員法で定められています。
具体的には、以下のようなケースが考えられます。
- 再三の指導にもかかわらず、業務上のミスや事故を頻発させる
- 正当な理由なく、長期にわたり欠勤を続ける
- 医師の診断により、回復の見込みがなく、職務への復帰が困難と判断される
分限免職は、職員の身分に重大な影響を与えるため、その判断は客観的な事実に基づき、慎重に行われます。懲戒処分としての免職とは異なり、制裁的な意味合いだけでなく、公務の能率的な運営を確保するという目的も持っています。
休職や欠勤に関するよくある質問
ここでは、会計年度任用職員の休職や欠勤について、特によく寄せられる質問にお答えします。
Q1. 病気休暇を使い切ったら、すぐに休職しないといけませんか?
A. 必ずしもそうではありません。まずは残っている年次有給休暇を利用して療養を続ける選択肢があります。年次有給休暇は有給ですので、経済的な負担を軽減できます。それでも療養期間が不足する場合に、休職を検討することになります。
Q2. 休職したことが、次年度の契約更新で不利になりますか?
A. 制度に則った正当な理由での休職が、直ちに不利になることはありません。ただし、前述の通り、休職に至るまでの勤務状況や、復職後の勤務への期待度などが総合的に評価されるため、間接的な影響が全くないとは言い切れません。大切なのは、休職前から誠実に勤務し、職場と良好な関係を築いておくことです。
Q3. 休職中に任期が満了した場合はどうなりますか?
A. 任期満了とともに、休職も終了し、雇用契約も一旦終了となります。翌年度も継続して療養が必要な場合は、再度任用されることが前提となりますが、健康状態によっては再度の任用が見送られる可能性もあります。
会計年度任用職員の休職は制度理解と事前相談が重要
記事のポイントをまとめます。
- 会計年度任用職員にも休職制度は存在する
- 休職期間は任期内(原則として年度末まで)に限られる
- 常勤職員と比べて休職期間や給与の面で違いがある
- 休職の前に、まずは病気休暇や年次有給休暇の利用を検討する
- 病気休暇は年間10日程度の有給休暇が設けられている場合が多い
- 7日を超える病気休暇の取得には医師の診断書が必要
- 長期療養には休職制度を利用する
- 休職申請には診断書や休職願などの提出が求められる
- 休職期間中の給与は原則として無給となる
- 無給期間中は健康保険の傷病手当金を受給できる可能性がある
- 傷病手当金は給与の約3分の2が最長1年6か月支給される
- 復職する際にも医師の診断書が必要
- 正当な理由のない欠勤は人事評価や契約更新に影響する
- 欠勤が続くと戒告や減給などの懲戒処分を受けることがある
- 勤務実績不良や長期の欠勤は分限免職の理由にもなり得る
- 制度の詳細は自治体ごとに異なるため、必ず勤務先の規則を確認する
- 休職を検討する際は、早めに上司や人事担当に相談することが鍵となる










