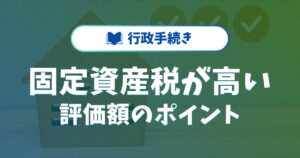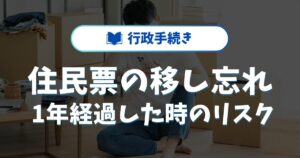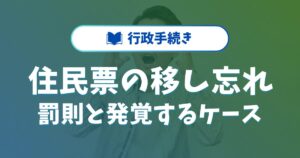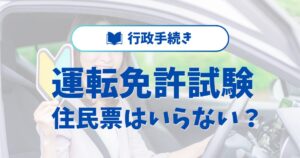生活保護を受けながら入院が決まった際、「パジャマ代はどうなるのだろう?」と不安に思う方は少なくありません。入院中は何かと物入りになりますが、生活保護の制度は複雑で、何が支給対象で何が自己負担なのか分かりにくいものです。
例えば、生活保護受給中の入院で気になる差額ベッド代や、娯楽のためのテレビ代はどう扱われるのでしょうか。また、入院が月またぎになった場合の生活保護費の計算方法や、1ヶ月以上の長期入院で留守宅の家賃がどうなるかという心配もあるでしょう。さらに、病院から求められることがある入院保証金についても、どう対応すればよいか戸惑うかもしれません。
この記事では、生活保護受給者の入院時にかかる費用、特にパジャマ代をはじめとする日用品費の扱いや、自己負担となる費用の範囲、そして必要な手続きについて、制度の基本から分かりやすく解説します。この記事を読めば、入院に関するお金の不安を解消し、安心して治療に専念するための知識を得られます。
- 生活保護での入院時にパジャマ代が支給されるかどうかがわかる
- パジャマ代以外に自己負担となる費用の種類が明確になる
- 入院期間に応じた生活保護費や家賃の扱いを理解できる
- 入院が決まった際に必要な手続きの流れを把握できる
生活保護での入院、パジャマ代など自己負担の範囲は?

- 入院日用品費でパジャマ代は支給される?
- 入院患者日用品費で賄うものと優先順位
- 入院中のテレビ代は対象外?娯楽費の範囲を解説
- 要注意!差額ベッド代は原則自己負担
- 差額ベッド代が自己負担にならない例外とは?
- 病院に支払う入院保証金、立て替えは可能?
入院日用品費でパジャマ代は支給される?
生活保護受給者が1ヶ月以上入院する場合、「入院患者日用品費」という名目でお金が支給されます。しかし、結論から言うと、この費用でパジャマ代が必ずしも賄えるとは限りません。
その理由は、病院によっては感染症対策などの理由から、持ち込みのパジャマではなく、病院が指定する病衣のレンタルを義務付けている場合があるからです。
このレンタル費用は、生活保護制度上「個人的な選択による出費」と見なされることが多く、入院患者日用品費の支給対象外、つまり自己負担となるのが原則です。
もし、ご自身のパジャマの持ち込みが許可されているのであれば、入院患者日用品費から購入費用を捻出することは可能です。ただし、この日用品費には他にも使い道があるため、計画的な利用が求められます。
入院患者日用品費で賄うものと優先順位

入院が1ヶ月以上続くと、食費や光熱費などを対象とする「生活扶助」が停止され、代わりに「入院患者日用品費」として月額23,110円(2025年現在)が支給されます。この費用は、入院生活で必要となる身の回り品の購入に充てるためのものです。
この日用品費には、使い道の優先順位を考える必要があります。まず最優先されるべきは、歯ブラシ、タオル、ティッシュペーパー、下着といった、療養生活に最低限不可欠な物品です。自治体によっては、おむつ代もこの費用から支出することになります。
これらの必需品を確保した上で、もし費用に余裕があれば、雑誌の購入や、前述の通り持ち込みが許可された場合のパジャマ代などに充てることが可能です。しかし、限られた金額であるため、無計画に使うと必需品が購入できなくなる恐れがあり、注意が欠かせません。
入院中のテレビ代は対象外?娯楽費の範囲を解説
入院中の気晴らしとしてテレビを見たいと考える方は多いですが、テレビカード代や病室でのWi-Fi利用料といった費用は、生活保護の支給対象外となります。これらは原則として自己負担です。
なぜなら、生活保護制度は憲法が定める「健康で文化的な最低限度の生活」を保障することを目的としており、支給される費用は生命維持や治療に直接必要なものに限定されるからです。
テレビやインターネットは、生活を豊かにするものではありますが、「治療に不可欠なもの」とは見なされず、娯楽や嗜好品の範疇に入ると判断されます。
このため、これらの費用は入院患者日用品費から自分でやりくりして支払うことになります。ただし、日用品費は生活必需品の購入が優先されるため、娯楽に充てられる金額は非常に限られているのが実情です。
要注意!差額ベッド代は原則自己負担

入院費用の中でも特に高額になりがちなのが、個室や少人数の病室を利用した際に発生する「差額ベッド代」です。この差額ベッド代は、生活保護の医療扶助の対象外であり、原則として全額が自己負担となります。
生活保護制度が保障するのは、あくまで標準的な療養環境、つまり相部屋(大部屋)での入院です。患者自身の希望で「より快適な環境で過ごしたい」「プライバシーを確保したい」といった理由から個室などを選んだ場合、その追加費用は最低限度の生活の範囲を超える贅沢と見なされます。
病院側から差額ベッド代が発生する病室を勧められた際には、安易に同意書へサインしないことが肝心です。一度同意してしまうと、支払い義務が生じてしまうため、慎重な判断が求められます。
差額ベッド代が自己負担にならない例外とは?

前述の通り、差額ベッド代は原則自己負担ですが、支払い義務が発生しない例外的なケースも存在します。主に「治療上の必要性」と「病院側の都合」の2つのパターンが考えられます。
治療上の必要性がある場合
例えば、免疫力が著しく低下しており感染症のリスクが高い、術後で絶対安静が必要、または終末期で精神的な苦痛の緩和が求められるなど、医師が治療のために個室での管理が不可欠と判断した場合は、差額ベッド代は請求されません。
病院側の都合による場合
また、大部屋が満床でやむを得ず個室に入院した場合や、院内感染の防止対策として病院側の判断で隔離された場合など、患者の希望に基づかないケースでも支払い義務は生じない決まりです。
もし、これらの状況に該当するにもかかわらず請求された場合は、同意書へのサインを保留し、まずは担当のケースワーカーや病院の相談窓口(医療ソーシャルワーカー)に相談することが大切です。
病院に支払う入院保証金、立て替えは可能?
入院する際に、病院から「入院保証金」の支払いを求められることがあります。これは、入院費用の支払いを担保するためのお金で、相場は5万円から10万円程度です。しかし、生活保護を受給している場合、この保証金の扱いはどうなるのでしょうか。
生活保護受給者の医療費は「医療扶助」によって現物支給(窓口負担なし)されるため、多くの病院では入院保証金の支払いが免除されます。入院が決まったら、まず福祉事務所が発行する「医療券」を病院に提示し、保証金が不要かどうかを確認しましょう。
万が一、病院の方針で保証金が必要と言われた場合でも、すぐに支払えないからといって入院を諦める必要はありません。担当のケースワーカーに事情を説明し、相談してください。福祉事務所が病院と調整してくれる場合や、公的な貸付制度を利用できる可能性があります。
生活保護の入院でパジャマ代以外の手続きと注意点

- 入院が決まったら?ケースワーカーへの報告と手続き
- 入院が月またぎになった場合の生活保護費の計算方法
- 入院が1ヶ月以上の場合、家賃(住宅扶助)は出る?
- 住宅扶助が打ち切りになる入院期間の目安
- 生活保護の入院とパジャマ代の疑問を解決(まとめ)
入院が決まったら?ケースワーカーへの報告と手続き

入院が決まった際に、まず最初に行うべき最も大切なことは、担当のケースワーカーへ速やかに連絡することです。これは、入院に伴う医療扶助の手続きや、生活保護費の算定変更に不可欠なため、法律上の義務にもなっています。
連絡する際には、入院する病院名、入院予定日、おおよその入院期間、そして病状について伝えます。ケースワーカーはこれらの情報をもとに、「医療券」の発行手続きなど、必要な準備を進めてくれます。
もし緊急入院で事前の連絡ができなかった場合でも、入院後できるだけ早く、本人または家族から必ず報告を入れるようにしましょう。報告を怠ると、医療費の支払いがスムーズに進まなかったり、保護費の過払いが発生して後日返還を求められたりする可能性があるため、注意が必要です。
入院が月またぎになった場合の生活保護費の計算方法

入院が月をまたぐ場合、生活保護費の計算方法が少し複雑になります。特に、入院期間が1ヶ月を超えるかどうかが大きなポイントです。
1ヶ月未満の短期入院の場合
月の途中で入院し、その月のうちに退院するような短期入院であれば、生活保護費(生活扶助)は通常通り満額支給されます。
1ヶ月以上の長期入院の場合
一方、入院が1ヶ月以上続くと見込まれる場合は、入院した月の翌月1日から、生活扶助が「入院患者日用品費」に切り替わります。例えば、3月20日に入院した場合、3月分の生活扶助は満額支給されますが、4月1日からは入院患者日用品費(月額23,110円)が支給される仕組みです。
退院した際は、退院日の翌日から生活扶助が日割りで再計算されます。このように、入院と退院のタイミングによって支給額が変わるため、不明な点があればケースワーカーに確認することをお勧めします。
入院が1ヶ月以上の場合、家賃(住宅扶助)は出る?
は出る?.jpg)
長期入院で最も気がかりなことの一つが、留守にしている自宅の家賃ではないでしょうか。生活保護制度では、この点についても配慮がなされています。
結論として、入院期間が1ヶ月以上になったとしても、家賃を補助する「住宅扶助」は原則として継続して支給されます。これは、退院後に帰る家を失い、生活基盤がなくなってしまうことを防ぐための措置です。
ただし、この住宅扶助の支給には条件があり、無期限に続くわけではありません。入院が長期化し、退院の見込みが立たなくなった場合には、支給が停止される可能性があります。そのため、入院が長引きそうな場合は、今後の見通しについてケースワーカーと密に連携を取ることが不可欠です。
住宅扶助が打ち切りになる入院期間の目安

前述の通り、長期入院中でも住宅扶助は継続されますが、その期間には目安があります。一般的に、以下の基準で判断されることが多いです。
| 入院期間 | 住宅扶助の扱い |
|---|---|
| 6ヶ月以内 | 原則として継続支給される |
| 6ヶ月を超えた場合 | 3ヶ月以内に退院の見込みがあれば継続される |
| 9ヶ月を超えた場合 | 原則として支給が停止(打ち切り)される |
つまり、入院が9ヶ月を超えて退院の見込みが立たない場合、住宅扶助は打ち切りとなり、住んでいる家を引き払う必要が出てくる可能性があります。もし退去せざるを得なくなった場合でも、家財の処分費用などが「一時扶助」として支給される制度があります。
いずれにしても、自身の病状や退院の見通しについては、医師の診断を踏まえて正確にケースワーカーへ伝えることが、住まいを守る上で非常に大切になります。
生活保護の入院とパジャマ代の疑問を解決(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- 生活保護受給者の入院時、パジャマ代は原則自己負担
- 病院指定の病衣レンタル費用は入院患者日用品費の対象外
- パジャマ持ち込み可なら日用品費から購入費用を捻出できる
- 入院が1ヶ月以上の場合、月額23,110円の入院患者日用品費が支給される
- 日用品費は歯ブラシやタオルなど生活必需品の購入が最優先
- テレビカード代やWi-Fi代などの娯楽費は自己負担
- 娯楽費は治療に不可欠ではないため扶助の対象外
- 差額ベッド代も原則自己負担であり医療扶助ではカバーされない
- 治療上の必要性や病院都合の場合は差額ベッド代の支払い義務はない
- 入院保証金は医療扶助があるため免除されることが多い
- 保証金を求められたらまずケースワーカーに相談する
- 入院が決まったら速やかにケースワーカーへの報告が義務
- 入院が月をまたぐと生活保護費の計算方法が変わる
- 1ヶ月以上の入院では住宅扶助(家賃)が継続支給される
- ただし入院が9ヶ月を超えると住宅扶助は原則打ち切りになる