会計年度任用職員として働く上で、多くの方が悩むのが人事評価の目標設定ではないでしょうか。どのように書けば良い評価につながるのか、具体的な書き方が分からず、会計年度任用職員の人事評価シートを前に手が止まってしまうこともあるかもしれません。
会計年度任用職員の人事評価の目的は、能力や実績に基づいた公正な処遇を実現し、職員の成長を促すことにあります。そして、その評価結果は会計年度任用職員の人事評価における勤勉手当にも影響するため、適切な目標設定が不可欠です。
この記事では、会計年度任用職員の自己評価の記入例も交えながら、評価される目標設定の具体的な方法を解説します。この記事を最後まで読めば、人事評価における目標設定で失敗や後悔をすることなく、自信を持って評価に臨めるようになるはずです。
- 人事評価における目標設定の基本原則と評価全体の流れ
- 評価で差がつき、勤勉手当にも影響する目標設定の書き方
- 職種別の例文や自己評価で目標達成をアピールする方法
- 避けるべき悪い目標設定の例とその具体的な改善策
会計年度任用職員の人事評価における目標設定の基本

このセクションでは、会計年度任用職員の人事評価と目標設定に関する基本的な知識を解説します。評価の全体像を理解するための土台となる内容です。
- 人事評価の目標設定における重要性と基本原則
- 人事評価の5原則と効果的な目標設定との関連性
- 人事評価を構成する能力評価と業績評価
- 人事評価シートにおける目標設定から評価までの流れ
- 勤勉手当と連動する人事評価の目標設定ポイント
- 目標設定で役立つSMARTの法則とは?
人事評価の目標設定における重要性と基本原則
会計年度任用職員の人事評価において、目標設定は評価の出発点であり、根幹をなすプロセスです。適切な目標があることで、職員は自身の業務の方向性を明確にでき、評価者は客観的で公平な評価を下すことが可能になります。
目標設定が果たす主な役割は、職員自身の役割認識を深め、主体的な業務遂行を促すことにあります。加えて、組織内で目標を共有することで、チーム全体の連携強化にもつながります。
目標を設定する際は、いくつかの基本原則を守ることが求められます。第一に、職員の職務や責任に応じて「公平・公正」であることです。評価者の主観が入らないよう、具体的な行動指標や数値を用いることが望まれます。
第二に、個人目標が所属部署や組織全体の目標と連動していることです。これにより、一人ひとりの働きが組織の成果に結びつくようになります。業務環境の変化に応じて、評価者と被評価者の合意のもとで目標を柔軟に見直す姿勢も大切です。
人事評価の5原則と効果的な目標設定との関連性

人事評価制度を適切に運用するためには、「人事評価の5原則」と呼ばれる考え方を理解しておくことが役立ちます。これは、評価の公正性や納得性を確保し、職員の成長を促すための基盤となるものです。
人事評価の5原則
- 公正な評価
特定の人に有利・不利になることなく、全職員に公平に運用されること。 - 評価基準の明確化
誰が見ても分かるように、評価の基準や尺度が具体的に示されていること。 - 評価基準の理解
評価者と被評価者の双方が、評価基準を十分に理解し、共通の認識を持っていること。 - 評価基準の遵守
評価者は、定められた基準に則って評価を行い、恣意的な判断をしないこと。 - 評価責任の自覚
評価者は、自身の評価が相手に大きな影響を与えることを自覚し、責任を持って行うこと。
これらの原則と目標設定は密接に関連しています。例えば、効果的な目標設定を行うことは「評価基準の明確化」に直結します。目標が具体的であればあるほど、評価の客観性が高まり、「公正な評価」が実現しやすくなります。
そして、目標設定の段階で評価者と被評価者がすり合わせを行うことで、「評価基準の理解」が深まり、評価結果に対する納得感の醸成につながるのです。
人事評価を構成する能力評価と業績評価
会計年度任用職員の人事評価は、一般的に「能力評価」と「業績評価」という2つの柱で構成されています。この2つの評価の違いを理解することは、目標設定や自己評価を行う上で非常に大切です。
能力評価は、業務を遂行するために必要とされる知識、技能、規律性、協調性といった、個人の能力や勤務態度を評価するものです。職務に必要な能力をどの程度発揮しているか、というプロセスや姿勢が評価の対象になります。
一方、業績評価は、期初に設定した目標の達成度や、業務を通じて生み出された成果を評価します。こちらは「何をどれだけ達成したか」という結果に焦点を当てた評価です。目標設定は、主にこの業績評価の基準を明確にするために行われます。
日々の業務に取り組む姿勢(能力評価)と、目標に向かって成果を出すこと(業績評価)の両面から評価される仕組みになっています。双方のバランスを意識して業務に取り組むことが、良い評価を得るための鍵となります。
人事評価シートにおける目標設定から評価までの流れ
会計年度任用職員の人事評価は、年間を通じて決められたサイクルで進められます。ここでは、目標設定から評価結果の通知までの一般的な流れを解説します。
1. 期首の目標設定と面談
年度の初めに、評価者(所属長など)と職員が面談を行い、その年度の業務目標を設定します。この段階で、組織の目標と個人の役割を結びつけ、具体的で達成可能な目標について合意形成を図ります。合意した目標は、人事評価シートに記録されます。
2. 期間中の進捗確認
評価期間の途中では、目標の進捗状況を確認するための面談が実施される場合があります。業務内容の変更や予期せぬ課題が発生した場合には、このタイミングで目標の修正を行うことも可能です。
3. 期末の自己評価
評価期間の終わりには、職員自身が人事評価シートに自己評価を記入します。設定した目標に対する達成度や、期間中の取り組み、成果、そして今後の課題などを客観的に振り返り、記述するプロセスです。
4. 評価の実施とフィードバック
自己評価が記入された人事評価シートをもとに、評価者が最終的な評価を行います。その後、評価結果を職員に通知し、フィードバック面談が実施されます。この面談は、評価の根拠を伝え、職員の成長を促すための重要な機会となります。
以上の流れを理解しておくことで、計画的に業務を進め、適切なタイミングで自分の成果をアピールできるようになります。
勤勉手当と連動する人事評価の目標設定ポイント

会計年度任用職員の勤勉手当は、勤務成績に応じて支給額が変動する仕組みであり、人事評価の結果、特に業績評価が直接的に反映されます。このため、目標設定は待遇にも影響を与える重要な要素です。
勤勉手当の支給額は、多くの場合「基礎額 × 在職期間別割合 × 成績率」という式で算出されます。この中の「成績率」が、人事評価の結果によって決定される部分です。評価結果が良いほど成績率は高くなり、逆に評価が低いと成績率は標準よりも低くなる可能性があります。
したがって、目標設定を行う際には、単に業務をこなすだけでなく、評価基準を意識した内容にすることが求められます。例えば、評価区分が「良好」「良好でない」の2段階や、A~Cの3段階などで運用されている場合、標準以上の評価(「良好」やA評価など)を得られるような、具体的で測定可能な目標を立てることがポイントです。
目標が曖昧だと、成果を客観的に示すことが難しくなり、正当な評価を受けにくくなる恐れがあります。自分の頑張りが勤勉手当という形で適切に報われるためにも、評価者と十分にすり合わせを行い、納得感のある目標を設定しましょう。
目標設定で役立つSMARTの法則とは?
目標設定を行う際に、具体的で達成可能な目標を立てるためのフレームワークとして「SMARTの法則」が広く知られています。この法則を活用することで、誰が見ても分かりやすく、評価しやすい目標を作成できます。
SMARTは、以下の5つの英単語の頭文字を取ったものです。
| 要素 | 英語 | 意味 | 具体的なポイント |
|---|---|---|---|
| S | Specific | 具体的 | 誰が読んでも同じように解釈できる、曖昧さのない内容にする |
| M | Measurable | 測定可能 | 「いつまでに」「どれくらい」など、達成度を数値で測れる指標を入れる |
| A | Achievable | 達成可能 | 現実的に達成できる、少し挑戦的なレベルの水準に設定する |
| R | Relevant | 関連性 | 自身の職務内容や、所属部署・組織全体の目標と関連付ける |
| T | Time-bound | 期限設定 | 「いつまでに」達成するのか、明確な期限を定める |
例えば、「住民サービスを向上させる」という漠然とした目標ではなく、「住民からの問い合わせに対し、今年度末までに平均応答時間を30分以内に短縮する」のように設定します。こうすることで、目標が具体的になり、達成できたかどうかを客観的に判断できるようになります。
会計年度任用職員の人事評価で差がつく目標設定術

このセクションでは、基本的な知識を踏まえ、より実践的な目標設定のテクニックを紹介します。他の職員と差をつけ、高い評価を得るための具体的な書き方や注意点を解説します。
- 目標設定には何を書くべきですか?
- 【職種別】目標設定の書き方と例文
- 避けるべき目標設定の悪い例と改善点
- 目標達成を伝える自己評価の記入例と書き方
- 会計年度任用職員の人事評価と目標設定(まとめ)
目標設定には何を書くべきですか?
人事評価で良い結果を得るためには、他の職員と差をつける目標設定が鍵となります。ここでは、評価を高めるために目標に盛り込むべき3つの要素を解説します。
第一に、業務成果を可能な限り数値化することです。例えば事務職であれば、「書類の処理件数を前年度比で10%向上させる」や「入力ミス率を1%未満に抑える」といった定量的な指標を入れます。数値で示すことで、成果が客観的に伝わり、評価の納得度が高まります。
第二に、現状維持ではなく、革新性や業務改善の視点を盛り込むことです。単に与えられた業務をこなすだけでなく、「既存の申請手続きを見直し、デジタル化によって処理時間を20%削減する」といった、課題解決に向けた主体的な提案は高く評価される傾向にあります。コスト削減や住民サービスの向上に直接的につながる提案は、特に有効です。
第三に、自身の成長に関する目標を設定することです。任用期間を通じてどのようなスキルを習得したいか、という自己成長の視点も大切になります。「業務に関連する○○の資格を取得する」や「新しい会計システムの操作をマスターし、他の職員にも指導できるようになる」といった目標は、意欲の高さを示すことにつながります。
これらの要素を意識することで、ありきたりな目標設定から一歩抜け出し、評価者に良い印象を与えられます。
【職種別】目標設定の書き方と例文

目標設定は、職種や業務内容によって工夫が必要です。ここでは、代表的な職種ごとに、具体的な目標設定の例文を紹介します。
| 職種 | 目標項目 | 達成基準の例文 |
|---|---|---|
| 総務・事務職 | 書類管理の効率化 | 過去の書類を電子化し、検索にかかる時間を平均10分から5分に短縮する |
| 総務・事務職 | 経費の削減 | 消耗品の発注方法を見直し、関連経費を前年度比で5%削減する |
| 企画・政策担当 | 新規イベントの企画 | 若年層をターゲットにした新規イベントを企画し、アンケートで満足度80%以上を目指す |
| 窓口サービス職 | 住民対応の品質向上 | 問い合わせ対応マニュアルを改訂し、研修を実施することで、苦情件数を前年比で半減させる |
| 技能職(清掃等) | 作業品質の維持・向上 | 担当区域の定期巡回を週3回実施し、チェックリストに基づき常に清潔な状態を維持する |
これらの例文はあくまで一例です。大切なのは、自身の業務内容を具体的に分析し、組織目標と関連付けながら、測定可能で達成可能な目標を自分の言葉で設定することです。上記の表を参考に、自身の職務に合ったオリジナルの目標を作成してみてください。
避けるべき目標設定の悪い例と改善点
効果的な目標設定を行うためには、どのような記述が「悪い例」とされるのかを知っておくことも有効です。ここでは、よくある失敗例とその改善ポイントを解説します。
悪い例1:目標が抽象的すぎる
「業務効率化に努める」「住民サービス向上に貢献する」といった目標は、具体性に欠け、評価が困難です。何をどうすれば達成なのかが不明確なため、評価者も判断に困ってしまいます。
- 改善ポイント
SMARTの法則を意識し、数値や具体的な行動を盛り込みます。「レポート作成時間を2時間から1.5時間に短縮する」のように、誰が見ても達成度が分かるように記述します。
悪い例2:成果が測定できない
「コミュニケーション能力を高める」といった目標も、達成できたかどうかを客観的に測ることが難しい例です。
- 改善ポイント:
測定可能な行動目標に置き換えます。「月1回のチームミーティングを主催し、議事録を共有する」のように、具体的なアクションで成果を示せるように工夫が必要です。
悪い例3:組織目標と関連がない
「個人的に英語の学習を頑張る」など、職務や組織の目標と直接関係のない目標は、人事評価の対象として不適切と見なされる場合があります。
- 改善ポイント
個人のスキルアップ目標であっても、組織への貢献と結びつけます。「外国人来庁者向けの対応マニュアル(英語版)を作成する」のように、職務に活かせる形で設定し直します。
これらの悪い例を反面教師として、具体的で、測定可能、そして組織目標と関連した目標設定を心がけましょう。
目標達成を伝える自己評価の記入例と書き方
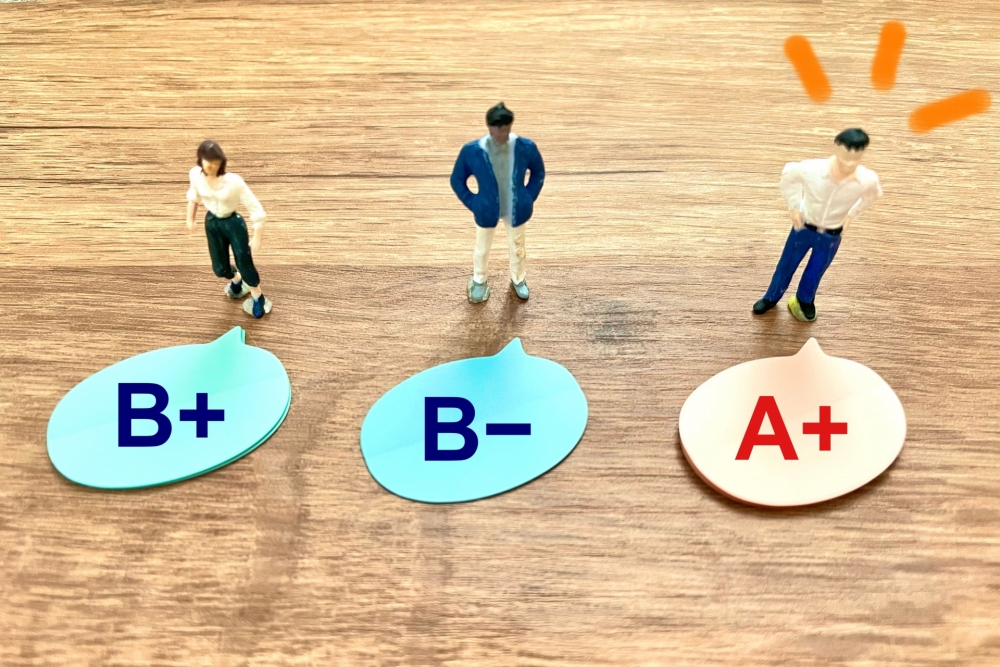
評価期間の終わりに作成する自己評価は、設定した目標に対して自分がどのように取り組み、どのような成果を上げたかをアピールする絶好の機会です。ここでは、説得力のある自己評価の書き方と記入例を紹介します。
自己評価を記入する際は、まず期初に設定した目標と、それに対する実績を明確に記載します。このとき、「頑張りました」といった主観的な表現は避け、具体的な数値や事実に基づいて記述することが大切です。
次に、目標達成のためにどのような工夫や努力をしたのか、具体的な行動プロセスを説明します。課題に直面した場合は、それをどのように乗り越えたのかを記すことで、問題解決能力もアピールできます。
もし目標が未達成だったとしても、正直にその事実と原因を分析し、今後の改善策を前向きに述べることが求められます。失敗から学び、次に活かそうとする姿勢は、むしろ好意的に受け取られるでしょう。
記入例
今年度の目標は「窓口業務の効率化と来庁者満足度の向上」でした。実績として、業務フローの見直しにより、平均対応時間を昨年度比で15%短縮できました。
また、来庁者アンケートでは満足度90%を達成し、目標を上回る成果を上げています。 取り組みとして、チーム内で週1回の情報共有会を主催し、課題解決に努めました。
一方で、繁忙期の待ち時間対応に課題が残ったため、来年度は応援体制の強化を提案したいと考えています。この経験を通じて得たチームでの課題解決力を、今後の業務にも活かしていく所存です。
成果・課題・改善策をセットで記述することで、説得力のある自己評価となります。
会計年度任用職員の人事評価と目標設定(まとめ)
この記事では、会計年度任用職員の人事評価における目標設定について、その基本から実践的な書き方までを解説してきました。最後に、重要なポイントを箇条書きで振り返ります。
- 目標設定は人事評価の根幹であり、自身の業務の方向性を決める
- 人事評価は「能力評価」と「業績評価」の2つの柱で構成される
- 業績評価は目標の達成度に基づいて行われ、勤勉手当に直結する
- 目標設定では公平性、組織目標との連動、柔軟な見直しが原則
- SMARTの法則(具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限設定)を活用する
- 目標設定から自己評価、フィードバックまでの一連の流れを把握しておく
- 差をつける目標には「数値化」「業務改善」「自己成長」の視点を入れる
- 事務職、企画職、窓口職など、自身の職種に合った具体的な目標を立てる
- 「業務に貢献する」といった抽象的な目標は避ける
- 測定不能な目標は、具体的な行動目標に置き換える
- 個人の学習目標も、職務への貢献と結びつけて記述する
- 自己評価では、目標に対する実績を具体的な数値や事実で示す
- 目標達成のための工夫や努力のプロセスも記述する
- 未達成の目標は、原因分析と前向きな改善策をセットで記す
- この記事で解説したポイントを実践し、自信を持って人事評価に臨む










