ICT支援員の仕事に興味があっても、ネットで「ICT支援員 きつい」と検索したとき、不安な気持ちになる人も多いのではないでしょうか。実際、仕事内容は幅広く、学校現場では一人で多くの業務をこなさなければならない場面もあります。また、年収や雇用形態が安定しづらいという声も見られます。
さらに、ICT支援員になるには資格が必要かどうか、未経験から目指せるのか気になる方もいるでしょう。一部では将来性がないとも言われていますが、本当にそうなのでしょうか。
この記事では、ICT支援員が「きつい」と言われる理由や、実際の仕事内容、年収の現実、求められる資格、そして将来性に関する情報をわかりやすくまとめています。ICT支援員として働くか迷っている方のヒントになる内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。
- ICT支援員の具体的な仕事内容とその負担の大きさ
- きついと感じやすい現場の環境やストレス要因
- 年収や働き方の実情と雇用の安定性について
- 未経験でも目指せる資格や将来性の可能性
ICT支援員がきついと感じる理由とは?

- ICT支援員の仕事内容をわかりやすく解説
- ICT支援員が「きつい」と言われる理由
- 年収と働き方
- ICT支援員に向いている人は?
- 楽しいと感じる瞬間とは?
ICT支援員の仕事内容をわかりやすく解説
ICT支援員の主な仕事は、学校でのICT(情報通信技術)の活用をサポートすることです。具体的には先生や生徒がパソコンやタブレットをスムーズに使えるように助ける役割があります。
日常業務は以下のように分かれます。
- 授業支援
- 授業前:機器やネットのチェック、教材の準備
- 授業中:先生や児童の機器操作のサポート
- 授業後:機材の片付け、記録、トラブルの振り返り
- ICT環境の整備
- パソコンやタブレットのメンテナンス
- Wi-Fiやソフトの更新作業
- 機器操作マニュアルの作成
- 校務サポート
- ExcelやWordを使った書類づくりの補助
- 成績管理ソフトの操作支援
- 学校ホームページの更新や保護者連絡ツールの整備
- 先生向け研修の企画と実施
- ICTツールの使い方を教える研修を計画
- 放課後や長期休暇中に短時間の勉強会を開催
これらの業務に加えて、授業で使う教材づくりの支援や、より良い授業のためのICT活用方法を提案することもあります。地道で幅広い仕事ですが、学校のデジタル化を支える大切な存在です。
ICT支援員が「きつい」と言われる理由

ICT支援員の仕事はやりがいがある一方で、「きつい」と感じる場面も少なくありません。現場では、思っている以上に負担が大きいと感じる場合があります。
理由は主に以下の5つです。
1. 対応が一人で完結する場面が多い
ICT支援員は1人だけで数十台の機器や複数の教室を担当することがあります。トラブルが同時に起こると対応が追いつかず、焦りや不安を感じやすいです。
2. 常に知識のアップデートが必要
ICTの技術は日々変化しています。新しいアプリやセキュリティ対策を学び続けなければなりません。勉強の時間を確保するのも一苦労です。
3. 突発的なトラブルが多い
パソコンが動かない、ネットがつながらないなど、授業中に急な問題が起きる場合が多く、対応力とプレッシャーが求められます。
4. 感謝されにくい立場
裏方の仕事が多いため、頑張っても気づかれないことがあります。感謝される機会が少ないのは、モチベーションが下がる一因です。
5. 雇用が安定しづらい
派遣や契約社員が多く、長く続けたいと思っても更新されないこともあります。安心して働きづらい環境にある場合もあります。
年収と働き方

ICT支援員の働き方は人によってさまざまで、自分の生活スタイルに合った形で仕事を選ぶことができます。働き方によって年収も変わってくるため、就職前にしっかりと知っておくと安心です。
まず、主な雇用形態と年収は以下の通りです。
| 雇用形態 | 平均年収 |
|---|---|
| 正社員 | 約300万〜350万円 |
| 契約社員・派遣社員 | 約240万〜324万円 |
| パート・アルバイト | 年収換算で100万〜200万円前後 |
正社員以外は比較的低めの年収になりやすいのが現状です。特に派遣や契約では勤務時間が短くなる場合があり、収入に直結します。
働き方の面では次のスタイルが選べます。
- 学校に常駐して勤務する
- 複数の学校を巡回する
- 在宅やリモートで業務を行う
自分の家庭の事情やスケジュールに合わせて働き方を調整できるのは大きな魅力です。特に育児中の方やWワークを考えている人には向いているでしょう。
一方で、フルタイムで働ける職場が少なかったり、契約更新のたびに不安を感じる人も少なくありません。将来的に安定した収入を求めるなら、経験を積んで正社員や上位資格取得を目指すのがよいでしょう。
ICT支援員は多様な働き方が可能ですが、年収や雇用条件にはばらつきがあります。事前に求人の内容をよく確認することが大切です。
ICT支援員に向いている人は?

ICT支援員に向いているのは、技術が好きなだけでなく、人と接するのが得意な人です。学校の中で先生や子どもたちと関わるため、コミュニケーション力がとても大切になります。
以下のような性格の人は、ICT支援員に向いています。
- 子どもが好きで、親しみやすい雰囲気がある
- 相手の話を聞きながらサポートができる
- 困っている人を助けたい気持ちがある
- 新しいことを学ぶのが苦にならない
- 一人でも冷静に行動できる
また、ICT支援員には基本的なパソコン操作の知識が必要です。WordやExcel、タブレットの操作ができるレベルが求められます。さらに、トラブルが起きたときに焦らず対応する力や、相手に分かりやすく説明する力も求められます。
次のスキルや特性もあると、さらに活躍の場が広がります。
| スキル・特性 | 内容 |
|---|---|
| 問題解決力 | 機器トラブルに対応できる力 |
| 柔軟性 | 現場の変化にすぐ対応できる |
| 学習意欲 | 最新のICT知識を吸収する意欲 |
逆に、機械が苦手だったり、説明するのが苦手な人には向かないかもしれません。ICT支援員は“人を支える”ことが仕事の中心にあるため、裏方で頑張ることを楽しめる性格も向いています。
まずは自分の得意や苦手を整理して、この仕事に合っているか考えてみましょう。
楽しいと感じる瞬間とは?

ICT支援員は「大変そう」と思われがちですが、実はやりがいや楽しい瞬間も多くあります。特に学校で働く場合は、子どもたちや先生とふれ合う中で前向きな気持ちになる場面がたくさんあります。
まず嬉しいのは、「ありがとう」と言ってもらえる瞬間です。パソコンやタブレットのトラブルをすぐに直せたとき、子どもたちや先生から感謝されることがあります。自分の知識や行動が誰かの役に立ったと感じると、大きなやりがいにつながります。
また、子どもたちがICTを使って「できた!」と喜んでいる様子を見ると、自分のサポートが学びに役立っていると実感できます。操作が苦手だった子が一人で使えるようになった時などは、思わず笑顔になってしまうかもしれません。
さらに、ICT支援員は先生たちの働き方を助ける役目もあります。例えば、書類作りを効率よくできるようにしたり、授業で使う資料づくりをサポートしたりします。こうしたサポートがうまくいった時、学校全体の雰囲気も明るくなるでしょう。
楽しいと感じるポイントは次のとおりです。
- 子どもたちの成長を見守れる
- 感謝の言葉を直接もらえる
- 問題を解決したときの達成感
- 自分の知識や工夫が役に立つ実感
ICT支援員は人とつながりながら働ける、やりがいのある仕事です。特に「誰かを助けたい」「裏方として支えたい」と思っている人には向いているでしょう。
ICT支援員がきついと感じた時に知っておきたいこと

- ICT支援員は資格が必要?
- 資格試験の合格率は?
- ICT支援員の将来性がないと言われる理由
- ICT教育が遅れている理由は何ですか?
- ICT教育の3つの柱は何ですか?
ICT支援員は資格が必要?
ICT支援員になるには、必ずしも特別な資格が必要というわけではありません。未経験の人でも目指せる仕事です。実際、現場で活躍している人の中には、前職がまったく違う業種だった人も多くいます。
とはいえ、持っておくと有利な資格もあります。以下が代表的なものです。
- ICT支援員認定試験
- ITパスポート試験
- MOS(Microsoft Office Specialist)
- 基本情報技術者試験
これらは、パソコンやネットワークの基礎知識が身についていることを証明できるため、採用の場でも安心してもらいやすくなります。
特に「ICT支援員認定試験」は、教育現場でのICT活用に特化しているため、学校勤務を希望している方におすすめです。試験内容は、基本知識のほか、現場での対応力も問われます。
未経験者にとって大切なのは、完ぺきを目指すより「学び続ける姿勢」を持つことです。現場に入ってからも新しい知識を取り入れながら、自信をつけていくことができます。
未経験でも目指せる理由は以下の通りです。
- 教育機関が現場での対応力を重視している
- 研修やマニュアルが用意されていることが多い
- コミュニケーション力や人柄も評価される
つまり、ICTの知識だけでなく、人との関わりを大切にできる人であれば、チャンスは十分にあります。
資格試験の合格率は?
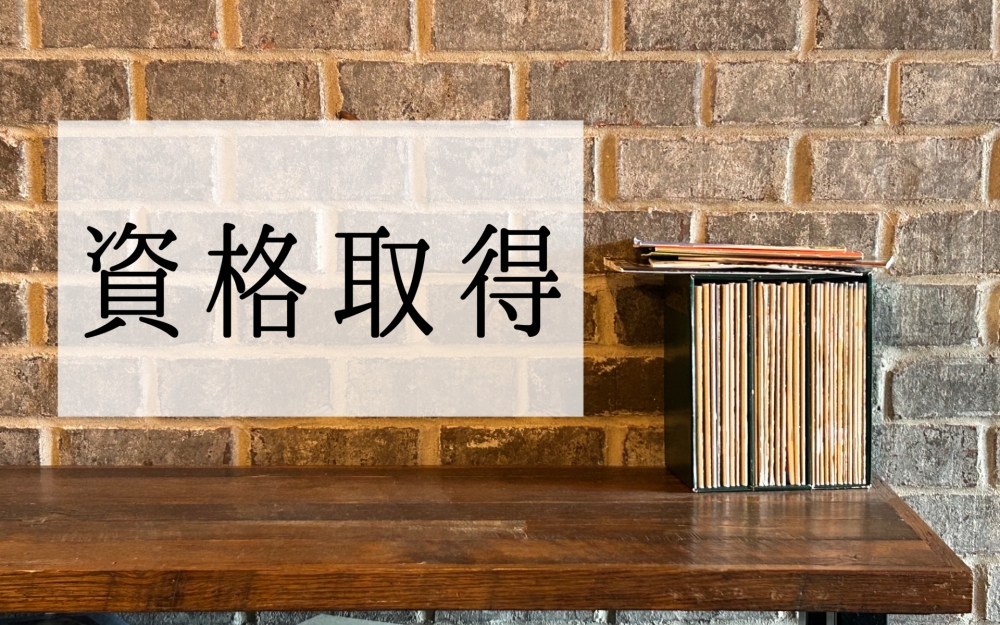
ICT支援員になるための代表的な試験として「ICT支援員認定試験」があります。この試験は、学校でICTを使うサポートができるかどうかをはかるもので、実務に近い内容が問われます。
この試験は「A領域(知識)」と「B領域(説明力)」の2つに分かれており、両方に合格する必要があります。
【試験の基本情報】
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| A領域 | ICTの知識、教育への活用例など(多肢選択) |
| B領域 | ICTが苦手な人に分かりやすく説明する力(動画提出) |
合格率はおよそ60〜70%といわれており、きちんと対策をすれば合格は十分に目指せます。ただし、試験勉強なしでは合格はむずかしいでしょう。
A領域は、ICTや教育の基本知識が問われます。過去問や参考書を使い、よく出る用語や操作を整理しておくと安心です。B領域では、動画を使って説明する力が見られます。相手の立場に立って、分かりやすく話せるかがポイントです。
勉強のポイントをまとめると
- A領域
用語の暗記より、内容の理解を重視する - B領域
伝え方の練習を動画でしてみる - 両領域
教育現場を意識した視点で答えること
合格に必要なのは知識だけではなく、「わかりやすく伝える力」や「学校で働く想像力」です。勉強の工夫次第で、誰にでも合格のチャンスがあります。
ICT支援員の将来性がないと言われる理由

ICT支援員は重要な仕事ですが、一部では「将来が不安」と言われています。これは、いくつかの現実的な理由があるためです。まず、ICT支援員の多くは契約社員や派遣社員として働いており、正社員に比べて雇用が安定していません。
また、ICT支援員という仕事は比較的新しいため、将来どのように役割が変わっていくのかがまだはっきりしていない点も、不安の声につながっています。
よく言われる理由を以下にまとめます。
- 雇用が不安定(契約・派遣が中心)
- 職種として歴史が浅く、認知度が低い
- 技術の進化に合わせてスキルの更新が必要
- 教育現場でのICT予算が限られている
さらに、学校のICT化が進んでいない地域も多く、ICT支援員の必要性がまだ十分に理解されていない場合もあります。そのため、「役割がなくなるのでは?」と心配されることもあります。
ただし、GIGAスクール構想やオンライン学習の広がりにより、今後のニーズが高まる可能性もあるため、将来性がまったくないとは言いきれません。むしろ、スキルを磨けば新しい形で活躍できる場も広がっていくでしょう。
ICT教育が遅れている理由は何ですか?

日本のICT教育は、世界の中でも「遅れている」と言われています。その原因はひとつではなく、いくつかの問題が重なっているためです。
まず、学校のICT機器の質や更新頻度に課題があるケースが目立ちます。パソコンやタブレットの数は増えていますが、性能が十分でなかったり、ネットが不安定だったりする学校も少なくありません。
次に、教員のICTスキルの差も課題です。多くの先生はICTの使い方を学ぶ機会が増えていますが、授業でうまく活用できないことがあります。
主な要因は以下のとおりです。
- ICT機器の質や更新頻度に課題がある
- 教員のICT活用指導力に差がある
- カリキュラムの見直しが遅れている
- ICT教育の必要性が十分に広まっていない
さらに、日本の教育現場は「昔ながらの方法」を大事にする風潮もあり、新しい技術の導入に時間がかかる傾向があります。海外では、デジタル教材やAIを使った学習が進んでいる国もあり、日本との差が広がっているのが現状です。
このような問題を解決するには、教員の研修を増やしたり、ICT予算をもっと充実させたりする取り組みが必要になります。子どもたちの学びの場をよりよくするためにも、ICT教育の改革は急がれる課題です。
ICT教育の3つの柱は何ですか?

ICT教育には、大きく分けて3つの柱があります。それぞれが学校での学びを支える大切な考え方です。この3つをバランスよく取り入れることで、子どもたちの力をしっかり育てることができます。
柱の内容と目的は次のとおりです。
1. 情報教育
情報教育とは、パソコンやインターネットを正しく使えるようにする学びです。調べた情報を見分けたり、使い方のルールを守ったりする力を育てます。
- 情報モラル(ネットのマナー)
- 調べる力・まとめる力
- 安全にICTを使う考え方
2. 教科指導におけるICT活用
これは、国語や算数などの教科の中でICTを使うことです。たとえば、動画で理科の実験を見たり、図を使って社会を学んだりすることで、理解しやすくなります。
- わかりやすい授業をつくる
- 子どもの集中力を高める
- 学びに対するやる気を引き出す
3. 校務の情報化
先生たちの仕事をICTで効率よくする取り組みです。出席の管理や成績の入力、保護者への連絡などをデジタルで行います。
- 先生の事務の時間を減らす
- 教える時間を増やせる
- 情報の整理や共有がしやす
この3つの柱は、それぞれに役目があります。学びを深めるためには、すべての柱をバランスよく進めていくことが大切です。
ICT支援員がきついと感じる理由とは?(まとめ)
記事のポイントをまとめます。
- ICT支援員は授業前・中・後のサポートを一人で担う場面が多い
- トラブル対応を同時に複数こなす必要があり、負担が大きい
- ICT機器やソフトの知識を常に更新し続ける必要がある
- 授業中に突然発生するトラブルへの即対応が求められる
- 裏方作業が多く、感謝されにくくやりがいを感じにくい
- 契約社員や派遣が中心で、雇用が不安定になりがち
- 年収は200万円台が多く、生活面の不安につながりやすい
- 正社員でも年収は比較的低めである
- ICT支援員はフルタイム勤務の求人が少ない
- スキルアップしないとキャリアの先が見えづらい
- 現場では柔軟な対応力と冷静さが求められる
- 子どもや先生とのやりとりに強いコミュニケーション力が必要
- ICT支援員の仕事は多岐にわたり、業務範囲が広い
- ICT教育への理解が現場に浸透しておらず、支援員の重要性が伝わりにくい
- 新しい仕事であるため、将来の役割が不透明な部分がある



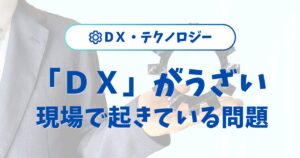
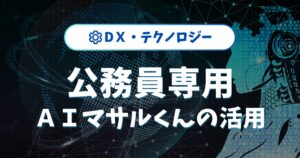
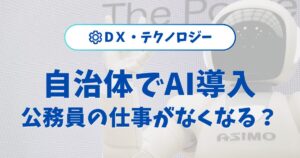
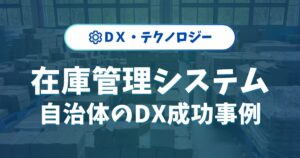

-300x158.jpg)