公務員の方が育児休業の取得を考えたとき、多くの方が経済的な不安を感じるのではないでしょうか。特に、育児休暇中のボーナス支給がどうなるのかは、家計に直結する大きな関心事です。
育休中の給料が原則として支給されなくなる中で、毎月受け取れる育児休業手当金に加え、ボーナスが支給されるかどうかは生活設計に大きく影響します。
また、近年取得者が増えている男性育休におけるボーナスの扱いや、支給の有無を左右するボーナスの基準日の仕組み、さらには具体的な育休中のボーナス計算方法など、制度は複雑で分かりにくい点も少なくありません。
この記事では、そうした公務員の育休とお金にまつわる疑問や不安を解消するため、最新の情報を基に、制度の仕組みから具体的な計算方法、注意点までを網羅的に解説します。
- 育休中のボーナスが支給される条件と基準日の仕組み
- ボーナス支給額の具体的な計算方法と減額される理由
- 育休中の給料や手当金など収入全体の流れ
- 男性の短期育休や長期育休といったケース別の注意点
公務員の育休とボーナス|基準日の基本を解説

- 育児休暇中のボーナス支給はどうなるの?
- ボーナスの基準日はいつですか?
- 育休中のボーナス計算方法を解説
- 給料はどうなる?原則無給?
育児休暇中のボーナス支給はどうなるの?

育児休業を取得した場合でも、条件を満たせばボーナス(期末・勤勉手当)は支給されます。育児・介護休業法では、育休の取得を理由として解雇や降格、減給といった不利益な取り扱いをすることを禁止しています。
このため、「育休を取得した」という事実だけでボーナスを支給しない、または一律で減額することは原則として認められていません。
ただし、これは無条件で満額が支給されるという意味ではない点に注意が必要です。多くの組織では、ボーナスは査定期間中の勤務実績に応じて支払われるものと位置づけられています。
したがって、査定期間中に育児休業で勤務していない期間がある場合、その日数分を支給額から減額して計算することは不利益な取り扱いには当たらず、合法とされています。
要するに、査定期間中に少しでも勤務した実績があれば、その実績に応じたボーナスを受け取れる可能性があるということです。逆に、査定期間の全てを育児休業で休んでいた場合は、勤務実績がゼロとなるため、ボーナスが支給されなくても法的には問題ないと考えられています。
ボーナスの基準日はいつですか?

公務員のボーナス支給において最も大切なルールが「基準日」の存在です。この基準日に在籍しているかどうかが、ボーナスを受け取るための大前提となります。
公務員のボーナスの基準日は、法律や条例によって明確に定められており、以下の通りです。
- 夏のボーナス:6月1日
- 冬のボーナス:12月1日
この日に職員として在籍していれば、ボーナスの支給対象者となります。例えば、6月1日に在籍していれば夏のボーナスが、12月1日に在籍していれば冬のボーナスが支給される権利を得るわけです。たとえ基準日の翌日に退職したとしても、基準日当日に在籍しているためボーナスは支給されます。
育児休業中であっても、この基準日に職員としての身分があれば支給対象となります。しかし、前述の通り、ボーナス額は基準日より前の6ヶ月間(査定期間)の勤務実績に応じて計算されます。
このため、基準日に在籍していても、査定期間の全てを育休で休んでいると、結果的に支給額がゼロになることがあります。
育休中のボーナス計算方法を解説

公務員のボーナスは、「期末手当」と「勤勉手当」という2種類の手当で構成されており、育休期間の扱いはそれぞれで異なります。
期末手当と勤勉手当の基本的な違い
期末手当は、民間のボーナスにおける生活補填的な意味合いが強く、在職期間に応じて一律の割合で計算される部分です。一方、勤勉手当は職員個人の勤務成績をより強く反映するもので、評価によって支給額が変わります。
育休を取得した場合、この2つの手当は以下のように異なるルールで減額調整が行われます。
- 期末手当
育休で休んだ期間の2分の1に相当する期間が、在職期間から除算される。 - 勤勉手当
育休で休んだ期間の全てが、在職期間から除算される。
具体的な計算の仕組み
ボーナスの支給額は、おおむね「(給料+各種手当)× 支給月数 × 在職期間に応じた割合」という式で計算されます。この「在職期間に応じた割合」を算出する際に、上記の減額ルールが適用されるのです。
例えば、査定期間6ヶ月のうち2ヶ月を育休で休んだ場合、勤勉手当の計算では勤務実績を4ヶ月分として計算しますが、期末手当の場合は4ヶ月(実勤務)+1ヶ月(育休期間の1/2)=5ヶ月分として計算されるため、勤勉手当よりも減額幅が小さくなります。
育休中は2種類の手当で減額率が異なるため、単純な日割り計算とはならない点を理解しておくことが大切です。
給料はどうなる?原則無給?

公務員が育児休業を取得している期間中は、原則として給料は一切支給されません。これは基本給だけでなく、扶養手当、住居手当、通勤手当といった各種手当も同様に支給が停止されます。法律上、育休期間中は職員としての身分は保障されますが、勤務していないため給与支払いの対象外となるのです。
このため、育休中の家計は、後述する「育児休業手当金」が主な収入源となります。給料がゼロになることは、育休取得を検討する上で最も大きな経済的変化と言えるでしょう。
ただし、給料が支給されない代わりに、経済的な負担を軽減するための制度も用意されています。その一つが、共済組合の掛金(民間の社会保険料に相当)の免除制度です。育休期間中は、申し出ることによって健康保険や年金などの掛金が全額免除されます。
この免除は、将来受け取る年金額が減ってしまうといった不利益が生じない仕組みになっています。掛金を支払っていなくても、納付したものとみなして年金額が計算されるため、安心して制度を利用できます。
公務員のボーナスと育休|基準日以外の重要知識

- 育児休業手当金は毎月いくらもらえる?
- 【男性公務員】短期育休とボーナスの関係性
- 「育休3年」を取得した場合のボーナスを解説
- 公務員のボーナス・基準日・育休の重要点(まとめ)
育児休業手当金は毎月いくらもらえる?

公務員の育児休業手当金は毎月いくらもらえる?
育休中に給料が支給されない代わりに、公務員は加入している共済組合から「育児休業手当金」を受け取ることができます。この手当金が、育休中の生活を支える中心的な収入となります。
支給額は、育休開始前の給料(標準報酬月額)を基に計算され、期間によって支給率が変動する2段階の仕組みになっています。
- 育休開始から180日間:標準報酬日額 × 67%
- 育休開始から181日目以降:標準報酬日額 × 50%
「標準報酬日額」は、標準報酬月額を22で割って算出します。育休開始から半年間は、より手厚い支援が受けられる設定です。
| 標準報酬月額 | 最初の180日(67%)の月額目安 | 181日以降(50%)の月額目安 |
| 250,000円 | 約152,000円 | 約113,000円 |
| 300,000円 | 約182,000円 | 約136,000円 |
| 400,000円 | 約243,000円 | 約182,000円 |
※勤務日数を20日として計算した概算額です。
支給期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、保育所に入所できないなどの特定の事情がある場合は、最長で2歳になるまで延長が可能です。また、この育児休業手当金は非課税所得のため、所得税や住民税がかからない点も大きな特徴です。
なお、2025年4月からは「出生後休業支援給付金」が新設され、条件を満たす共働き家庭などに対して育休開始後28日間は育児休業手当金に約13%の上乗せ給付があります(最長28日間)。こちらは別制度となるため、ご自身の状況に応じて共済組合や勤務先にご確認ください。
【男性公務員】短期育休とボーナスの関係性

近年、男性公務員の育児休業取得も増えていますが、特に1ヶ月程度の「短期育休」を検討する場合、取得するタイミングによってボーナスの手取り額が大きく変わるため注意が必要です。
最も効果的な戦略は、ボーナスにかかる社会保険料(共済組合の掛金)の免除制度を活用することです。この制度は、「賞与支給月の末日を含んで、連続して1ヶ月を超える育児休業」を取得した場合に適用されます。
具体的には、
- 夏のボーナス
6月中に月末をまたぐように、1ヶ月超の育休を取得する。 - 冬のボーナス
12月中に月末をまたぐように、1ヶ月超の育休を取得する。
このタイミングで育休を取得すると、支給されるボーナスから社会保険料が天引きされなくなるため、手取り額が数万円から十数万円単位で増える可能性があります。
逆に、育休期間が1ヶ月に満たなかったり、月末をまたがなかったりすると、この免除は受けられません。また、ボーナスの査定期間中に育休を取得すれば、その日数分ボーナス額自体は減額されますが、社会保険料の免除額が減額分を上回るケースも少なくありません。
短期育休を計画する際は、ボーナスの減額影響と社会保険料の免除メリットを天秤にかけ、自身の職場の給与担当者と相談しながら最適なタイミングを見極めることが賢明です。
「育休3年」を取得した場合のボーナスを解説
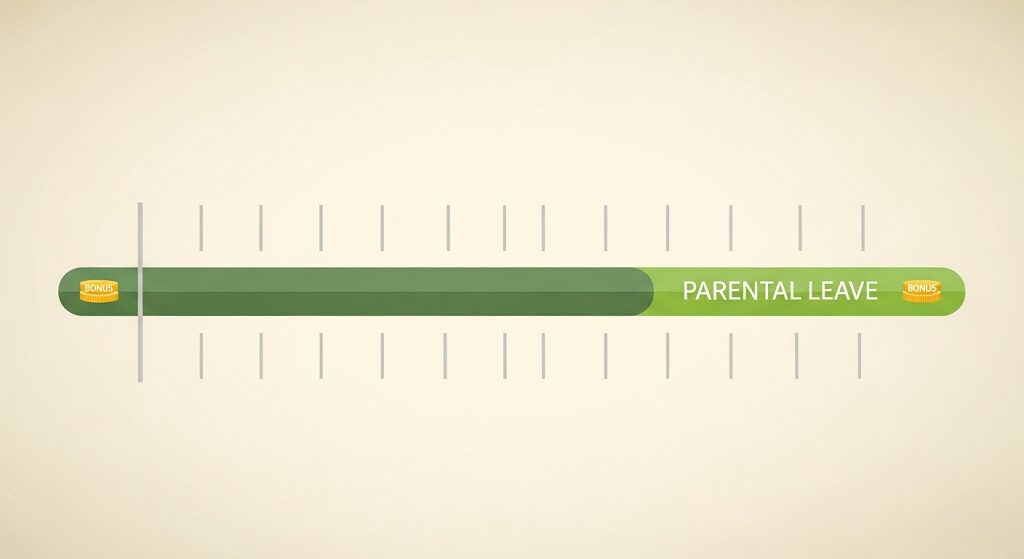
公務員は、子どもが3歳になるまで育児休業を取得できる制度がありますが、この「育休3年」を取得した場合のボーナスはどのようになるのでしょうか。
まず、育休を開始して最初のボーナスについては、査定期間中の勤務実績に応じて支給される可能性があります。例えば、4月から勤務し、9月から3年間の育休に入った場合、12月に支給される冬のボーナスは、4月から8月までの勤務実績に基づいて計算された額が支給されます。
しかし、その後、育児休業が継続している期間については、ボーナスは原則として支給されません。これは、ボーナスの算定対象となる査定期間(6ヶ月間)の全てにおいて勤務実績がゼロになるためです。
勤務実績がない場合はボーナスを支給しなくても法的に問題はないため、長期の育休期間中は支給がなくなるのが一般的です。
そして、3年間の育休を終えて職場に復帰すると、その復帰した時点から再び勤務実績がカウントされ始めます。
復帰後の最初のボーナスは、復帰日から査定期間の終わりまでの勤務日数に応じた額が支給され、その後、査定期間の全てを勤務するようになれば、満額が支給される流れに戻ります。
公務員のボーナス・基準日・育休の重要点(まとめ)
この記事のポイントをまとめます。
- 育休を理由にボーナスを不支給にすることは法律で禁止されている
- ただし査定期間に勤務実績がなければ支給なしも合法的な運用
- 公務員のボーナス基準日は夏が6月1日、冬が12月1日
- この基準日に職員として在籍していることが支給の大前提
- 産休期間は勤務扱いとしてボーナスが計算される
- 育休期間は勤務扱いにならずボーナスは減額される
- 期末手当は育休期間の半分、勤勉手当は全期間が減額対象
- 育休中の給料や扶養手当、住居手当などは支給されない
- 主な収入源は共済組合から支給される育児休業手当金
- 育児休業手当金は最初の半年間が給料の約67%
- 育児休業手当金は所得税や住民税がかからない非課税所得
- 育休中は共済組合の掛金、いわゆる社会保険料が免除される
- 掛金免除期間も将来の年金額は減らない仕組み
- 男性は賞与月の末日をまたいで1ヶ月超の育休を取得するのが最も有利
- 3年間の長期育休では勤務実績のない期間のボーナスは支給されない










